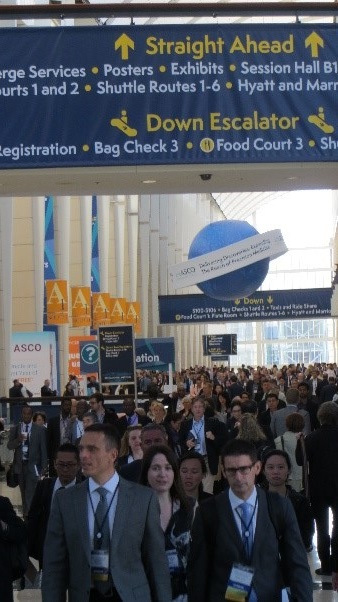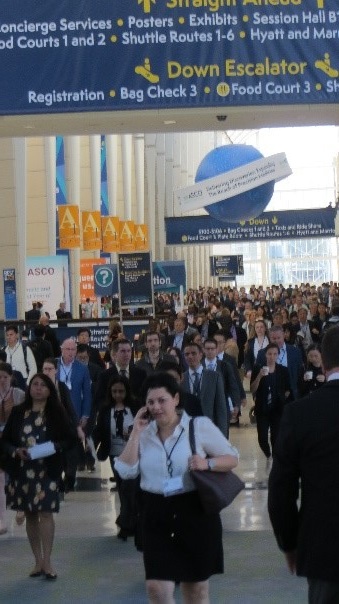米国臨床腫瘍学会 2018年年次集会(ASCO2018)レポート
<肺がん>
リキッドバイオプシーによる早期肺がん検出に期待~前向きのコホート研究の中間解析結果が報告される~
血液などの体液サンプルを用いて疾患の診断や治療効果を予測するリキッドバイオプシー。低侵襲性で患者の負担が小さく、腫瘍の遺伝子情報を踏まえた最適な治療につながることが期待され、世界中で研究開発が進められている。そうした中、今集会では、早期肺がん検出の可能性が有望視される前向きの縦断的なコホート研究「CCGA」の中間解析結果が報告された。
米国では、早期肺がんのスクリーニング(検診)には、低線量CTが推奨されているが、臨床的な採用率が低く、偽陽性リスクなどの問題点も指摘されている。一方、リキッドバイオプシーはすでに進行肺がん患者での標的治療の選択に活用されているが、早期がん検出については困難な課題もあり、まだ限られたエビデンス(科学的根拠)しか提示されていない。
CCGA研究は、米国、カナダの141施設で、12,000人以上(がん患者70%、非がん患者30%)を対象として行われているもの。今回の中間解析は、このうちの2,800人(training set:訓練事例集合1,785例:がん患者127例、test set:テスト事例集合1,015例:同42例)をサンプル対象としたサブスタディの解析結果。
cfDNA(血中循環腫瘍DNA)のシークエンスには、標的シークエンス、全ゲノムシークエンス(WGS)、全ゲノムバイサルファイトシークエンス(WGBS)の3つのアッセイ(定量分析法)が用いられた。
中間解析では、肺がん患者127人において、肺がんの生物学的シグナルは3アッセイともに同等であり、シグナルはステージ(病期)が進むにつれ強くなって(高まって)いた。
各アッセイの検出率は、
・WGBS:早期肺がん(ステージⅠ-ⅢA)41%、進行がん(ステージⅢB-Ⅳ)89%
・WGB:早期がん 38%、進行がん 87%
・標的シークエンス:早期がん 51%、進行がん 89%
と3つのアッセイ法を横断した同様な感受性を示していた。
報告者の米ダナファーバーがん研究所(ボストン)のGeoffrey R. Oxnard氏は「総合的なcfDNAシークエンスは、非侵襲性のがん検出を可能にさせるコピー数、メチル化など遺伝子特性のスペクトラムを横断した質の高い情報を提供するものである。このような特徴は、cfDNAをベースとしたアッセイの活用が、早期肺がん検出検に高い特異性をもたらすことをサポートしている。現在、CCGAを含めた大規模臨床研究において、より精度を高めるためにさらなるアッセイや臨床開発が進行中である」と述べている。
<プレシジョン・メディスン(最適化医療)>
プレシジョン・メディスンが、がん患者での有用な治療効果をもたらす~遺伝子変異に対する標的治療により生存期間が延長~
がん治療におけるプレシジョン・メディスン(最適化医療)の重要性が叫ばれるようになって久しいが、その有用性を示す長期的なレトロスペクティブ(後ろ向き)研究「The IMPACT Study」の結果が報告された。
The IMPACT Study(Initiative for Molecular Profiling in Advanced)は遺伝子異常を来した細胞内のシグナル伝達経路を標的とした治療が、長期間生存率などを含めた臨床アウトカム(転帰)に及ぼす影響を検討したもの。2007-2013年に分子的(遺伝子)検査を受けた3,743例のうち、34.9%にあたる1,307例に治療標的となる1つ以上の遺伝子変異が認められた。
研究初期では、単一の遺伝子変異を調べるアッセイが用いられたが、後期(2013年末まで)には20-50の異なる遺伝子を同時に解析する次世代シークエンス法が用いられた。
711例(54.4%)に変異に適合した治療(分子標的薬単剤、化学療法薬・その他治療法との併用)が施され、596例(45.6%)では治療法が見出せなかっために非適合治療が行われた。がん種の内訳は、消化器がん24.2%、婦人科がん19.4%、乳がん13.5%、メラノーマ(悪性黒色腫)11.9%、肺がん8.7%。対象患者の年齢中央値は57歳、男性が39%。前治療回数の中央値は4回、未治療患者の割合は2.8%であった。
分析の結果、適合治療群での全生存率曲線は、治療開始から3.2年の時点でプラトー(平坦)だった(11%が生存)。3年全生存率は適合治療群で15%であったのに対し、非適合治療群では7%。また10年全生存率はそれぞれ6%、1%だった。全生存期間(OS)の中央値は、非適合治療群に比べて適合治療群で有意に長く(9.3カ月vs.7.3カ月, p<0.001)、無増悪生存期間(PFS)も同様に適合治療群おいて有意に長かった(4.0カ月vs. 2.8カ月, p<0.001)。
報告者の米テキサスMDアンダーソンがんセンターのApostolia M. Tsimberidou氏は「IMPACT Studyは、複数のがん腫を横断してプレシジョン・メディスンによる長期間の治療効果を評価した初めての大規模試験である。試験結果は、次世代遺伝子シークエンスを活用した腫瘍の分子的(遺伝子)検査結果を最適化治療に用いることが可能であり、治療困難な患者への治療選択の際に考慮に入れるべきであることを示唆している」と述べている。
またTsimberidou氏らは、研究開始時の患者特性(baseline characteristics)の多変量解析に基づく予後因子評価スコアを開発。それによると、非適合治療、PI3K/AKT/mTOR経路の変異がOSを短縮させる危険因子であること。その他、肝転移、乳酸脱水素酵素(LDH)値の上昇、PS(全身状態)不良、アルブミン低値、血小板数の上昇、年齢60歳以上も危険因子となることが判明したという。
現在、腫瘍の分子的特性に適合した治療群と、分子的解析をベースとしない非選択治療群においてPFSを比較する第Ⅱ相試験「IMPACT 2」が進行中である。Tsimberidou氏は「次世代シークエンスや免疫療法などを活用したプレシジョン・メディスンの推進が、がん患者の臨床アウトカムの有意な改善をもたらすことを確証できるものと期待している」と述べている。