限られた生を、いつもと同じありふれた日常の中で過ごしたい 家族のあたたかな「気配」のそばで――在宅緩和ケアを訪ねる
看護師に女房の代わりは務まらない
井尾さんが語っているように、在宅緩和ケアの最大の特長は自宅で自分自身の暮らしを送りながら、ケアや治療に取り組めることにある。井尾さん自身、クリニックを始めて間もない頃に、それが患者さんに与える影響の大きさに衝撃を受けたことがあるという。
「ある高齢の男性がん患者さんの容態が悪化して、在宅ケアからホスピスケアに移行することになっていた。その患者さんがホスピスに入所する当日、『看護師さんは女房の代わりにはなれない』と入所を拒否したのです。その患者さんは不安が募ると、奥さんに添い寝してもらい、手を握ってもらいながら眠りについていました。ホスピスでいわばお客様として、至れり尽くせりのケアを受けるより、最愛の奥さんとともに、当たり前の暮らしを送りながら人生をまっとうしたいと考えたのです」
住み慣れた自宅で、長年にわたって生活をともにしてきた家族と接し続け、その「気配」を絶えず感じながら暮らし続ける――そのことによって、人は自分を取り戻し、ときとして思いがけない生命の力を解き放つことがあると井尾さんはいう。
実際、井尾さんとともに訪問した中にも、そうしたケースが少なからずあった。
自分たちでお父さんを助ける

同じ東京・立川市で左官業を営んでいた谷屋正雄さんに、がんがわかったのは08年12月のことだった。その数カ月前から下痢と便秘が交互に続き、食欲がまったくなくなったことから、立川市内の総合病院を訪ねると、胃がんが小腸に転移し、さらに重篤な腸閉塞を起こしていることが判明した。
点滴による栄養補給中にもかかわらず「治療の術がないから」と退院を迫られた谷屋さんの家族は別の総合病院でセカンドオピニオンを受診。そこで人工肛門を設置する腸閉塞治療の後、TS-1(一般名テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム)による外来抗がん剤治療を受け始める。この治療は劇的な効果をもたらし、谷屋さんはみるみる体調を回復する。治療を開始して数カ月後には体重が4キロも増加したほどだった。
しかし09年11月、TS-1の効力も消失、点滴によるタキソール(一般名パクリタキセル)投与に治療が切り換えられるが、効果確認の前に全身の激痛など重篤な副作用が現われ、谷屋さん一家は治療を中断、在宅での介護を開始する。井尾さんに在宅緩和ケアを依頼したのもこのときからだ。
「病院の医師からは在宅緩和ケアを受けながら���抗がん剤治療を継続することもできるといわれました。でも、お父さんが苦しむ姿を見ると、とてもその気にはなれなかった。それに実は、ずっと前から、私と2人の娘は自分たちでお父さんを助けようと決めていたのです」
と、奥さんの久代さんは語る。
1年3カ月無収入で介護を続ける
谷屋さんは久代さんにとって、これ以上は考えられない理想の夫だった。
「私は15年前に心筋梗塞を患っています。それからは汗を流して仕事から帰ってからも、私に体に障ることを一切させなかった。あんなに優しい人はこの世に2人といません」
と久代さんはいい切る。
谷屋さんはまた、自らの仕事を誇りに思う昔気質の職人でもあった。今年35歳と30歳になる2人の娘がまだ幼い頃から散歩に連れ出しては、「この公園はお父さんたちが手がけたんだ」「あの銅像の土台もつくったんだ」と伝えている。そして2人の娘もそんな父親を誇りに思い続けている。
その父親にがんが見つかった時点で、一家は総動員体制で介護に取り組み始める。「片手間ではお父さんを救えない」と娘たちは職を辞し、父親の救援に専念する。それから現在に至るまでの1年3カ月、谷屋家は無収入の状態で、貯えを切り崩しながら、父親の支援を続けている。
車に積まれたままの左官道具
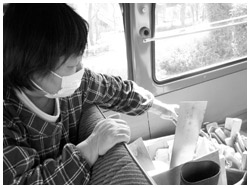
外来抗がん剤治療が続いている間は、医師に的確な質問をするために、がん治療について勉強を続け、抗がん剤治療が困難になってからは、インターネットや図書館を利用して、症状緩和に効果のありそうな民間療法を模索し続けた。丸山ワクチン、ビワの葉を用いた温熱療法、生姜湯による温湿布……。現在も谷屋さんが自宅で継続している治療はすべて、2人の娘が「少しでも症状が改善すれば」と調べ出したものだ。久代さんは毎朝6時前に起き出し、2時間かけて谷屋さんの朝食のお粥を作り続けている。「仕事に戻りたい」と繰り返す谷屋さんの生還を信じて、使い慣れた左官道具は今も愛車のワゴンに積み込まれたままだ。
「大好きなお父さんを助けなくてはならないのだから、これくらいのことは当たり前。大変だなんて感じたことはありません。でも生活費が底をついてきた。そろそろ何とかしなくてはね。アハハハハ」
と久代さんは笑い飛ばす。この明るさこそが家族たちの力の源泉であるに違いない。
そして、そうした家族総出の介護を支えているのが、井尾さんたちの在宅緩和ケアだ。
「在宅緩和ケアでは、先生自身に週に2度、看護師さんたちにも週に2度、訪ねてもらっています。処方してもらっている薬は鎮痛剤の貼り薬、胃腸薬など数種類ですが、うまく効果があがっており、痛みを感じることはほとんどありません。もっとも私たちにすれば、それよりも先生がついていてくれることの安心感が大きいですね。わからないことは何でも聞けるし、急な容態変化があっても、電話1本で対応してもらえる。だから何も心配はしていません」
と、久代さんはいう。
そうしたケアに家族の熱意が相まった結果だろうか、谷屋さんの症状は一時、改善の兆しを見せた。09年12月、自宅に戻ってひと月ほどした頃に食欲が回復し、顔色もよくなったと久代さんはいう。しかし10年2月、谷屋さんは再びやっかいな腸閉塞に見舞われ、病床に伏すことになる。もっとも谷屋さんはまだ希望を失っていない。
「妻や娘には転院したときと抗がん剤が効かなくなってからの2度命を救われています。その家族のためにもう少し頑張りたいのです」
と、病床で声を枯らしながら谷屋さんは話す。


