体験者の声で見えてきた在宅ホスピスの光と影 「わが家で最期」を選んだそれぞれの形
家族との時間を大切にするために
~夫・小川博司さんの場合~
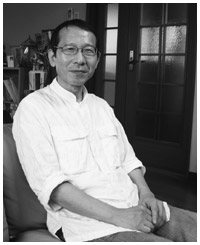
女性のがん患者の場合、「在宅ホスピス」で亡くなる人は少ない。妻が病気になった場合、家事に不慣れな夫が中心的な役割を担うことが難しいからだ。
その点、大学の社会学部の教授・小川博司さん(52歳)は1人暮らしの経験があり、料理や洗濯が苦にならなかった。医療者たちの予想を超え、2カ月10日間の看病の末、妻・圭子さん(当時52歳)を看取った。
圭子さんは看護師を経て、大学院で医療社会学の研究をしていた。3年前に乳がんだとわかったときには治療方針を自分で決めた。知り合いの医師、桜井隆さんに「私が悪くなったら最後まで家で診てね」と頼んでいた。
圭子さんは当時高校2年生だった1人娘の響子さんとともに、2003年4月、博司さんのイギリス留学に同行した。圭子さんは患者と医療者との関係をライフワークにしていた。イギリスでも調査を続け、論文「権利から双方向的責任への転換」を書き上げた。
その年の暮れ、脳や肝臓などへの転移がわかる。2月半ばに帰国・入院して、抗がん剤治療などを受けた。1カ月余り在宅ケアをするが、吐き気などがひどくなり再入院。3週間の入院後の4月下旬、「家に帰りたい」という圭子さんの希望で本格的な在宅ケアが始まる。
「私の仕事がある意味自由が利くのと、同僚の理解が得られたのがラッキーだったと思います」
2月半ばから3月末までは授業がなかったので、博司さんはほとんど家にいることができた。4月からは、授業をしながらの看護になった。週5日ホームヘルパーを頼み、博司さんが帰宅すると、交代にホームヘルパーが帰る、という生活だった。
大変だったのは、「イライラ」で圭子さんが眠れず、夜中に歩き回ったときだった。転倒すると危ないので、博司さんは眠れない。「寝てればいいのに」と喧嘩になった。寝不足で疲れ果てたときには、何度か付き添いを響子さんに交代してもらった、という。
亡くなる1週間前、圭子さんはほとんど話さないものの、何か楽しんでいるような穏やかな表情を見せるようになった。大きな目で宙を見上げ、赤ん坊のようだった。響子さんが呼ぶと、「はーい」と応えた。亡くなる2日前、博司さんが「あなたの論文は本にまとめるからね」と話しかけると、「ありがとう」と言った、という。
7月3日、圭子さんは朝から意識がなく、父や姉、博司さんの母、響子さん、博司さんに見守られて夕方、旅立った。圭子さんの希望で、BGMにはビギンの島唄が流れていた。桜井さんがやってきた。
「よくがんばりましたね……」
大の男が2人、握手して、抱き合った。
家での看取りは圭子さんにしてあげられる唯一のことだった、と博司さんは言う。
「再発がわかったころから、彼女はずっと泣いていました。私と娘も辛いわけですけど、いちばん辛いのは当人なんですよね。本人が家族との時間��大切にしたいと思うのであれば、家だと一緒にいられる時間が長いから。ある納得はしてもらえたかなと、思うんですけどね……」
やや間をおいて、博司さんが付け加えた。「でも、ある意味、彼女はずるい(笑)。僕のときは誰が看てくれるの? という話ですから」
大切な人を失った彼の寂しさが、「ずるい」といたずらっぽく言った一語に凝縮されているように感じた。
家の中に「日常」が戻ってきた
~夫・吉田利康さんの場合~
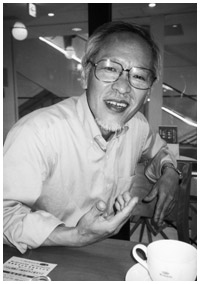
吉田利康さんは6年前、妻の章江さん(当時50歳)を家で看取った。
章江さんは看護師だった。白血病で1年半闘病した後の1999年2月、医師から「もう治療法がありません……」と告げられる。利康さんは退社し、看病と慣れない家事に専念した。当時、2人の息子は大学生と高校生だった。 しばらくしたころ、章江さんが言った。
「家に帰ってもいいやろか。ここにいたら治るものも治らんような気がする」
「帰っといで。自分の家やないか。お前がいたら家の中は明るぅなるわ」
当時、白血球は増減し、胸水がたまっていた。切れ痔と口内炎の痛みがひどかったものの、章江さんは歩くことができた。
主治医は在宅を快諾した。利康さんは紹介状を持って、近所のかかりつけ医をたずねた。が、「うちでは在宅ホスピスケアはできません」と断られてしまう。結局、緩和の処置は病院に頼み、死亡診断書だけかかりつけ医に書いてもらう約束になった。
在宅の初日、学校から帰ってきた次男が、居間のソファーでうたた寝している章江さんを見つけ、すごくうれしそうな顔をしたのを、利康さんは今でもよく覚えている。
男3人だとほとんど会話がないのに、次男は母親を相手に途切れることなくしゃべり続ける。家の中に「日常」が戻ってきた。
通院時には、自発的に子どもたちが付き添った。かつて病院への見舞いを父に勧められ、長男は吐き捨てるように言った。
「病院は母さんをとっていったやろ。病院なんて、大きらいや!」
その長男が自分からハンドルを握った。病院の医師に、「父は何もしなくていいと言うが、納得がいかない」と意見をぶつけたこともあった、という。次男は車イスを押した。彼らは自分の「役割」を得たのだ。
章江さんはモルヒネを拒否し続けた。妻が痛みに悶絶する姿を見るのが、利康さんは辛くてたまらなかった。
「もう逝かせてやりたい。でもそれでいいのか? そんな自問自答が苦しくて、倒れそうでした。誰か、俺を支えてくれ!と心の中で叫んでいました」
死の前日、章江さんの意識が薄れていった。お尻の傷口の処置をして、「気持ちいいか?」と息子たちと顔をのぞきこんだところ、章江さんはにっこりと笑顔を見せた。冷たくなっていく手足を、息子たちが「お母さん、お母さん……」と泣きながらさすった。そして章江さんは帰らぬ人となった。「わが家」に戻って17日目のことだった。
親戚たちが家に集まり、章江さんの死装束を相談し始める。子どもたちは利康さんに「僕らのお母さんなのに、なんで勝手に決めるんや。ふだん着でお母さんを送りたい」と言った。
「だから僕、叫びました(笑)。『すいません!わがまま言いますが、この子たちがお母さんにできる最後の瞬間だから、服は子どもに選ばせてやってください』って」
子どもたちが選んだのは、いつもの白いブラウスに、着古したベージュ色のスカートだった、という。
家での死は「日常の中で、あるがままの姿でその人の人生が完結すること」だ。そこでまた、本人と家族との関係が構築される。自分の最後の姿を家族に認知してもらうことに、意味がある。
ただ、いろいろな家族の形がある。本人や家族にとって必ずしも「わが家」がいいとは限らないし、さまざまな事情で実現が難しい場合もあるだろう。
それでも、自分の終焉が見えてきたとき、「わが家での最後のとき」を実現できるかどうか、考えてみる価値はあるように思える。


