尾道方式 医療と介護、民生委員まで加わり患者を支える「尾道方式」
新たな「地域医療連携」がはじまる
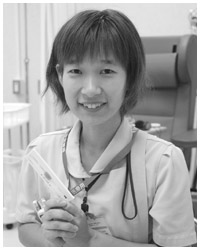
もう1人、片山医院から急いで帰ってきた人がいる。いまは尾道市立市民病院の内科外来に所属する渡辺陽子さんだ。「地域連携室」のような科に属しているわけではない渡辺さんが、なぜ開業医のケアカンファレンスに参加していたのだろう。
「緩和ケアチームでかかわった患者さんの退院前のカンファレンスに参加した場合は、1週間以内に同行訪問させていただき、その後の経過を開業医の先生とフォローできるようになったんです」
市民病院では、2004年から緩和ケアチームががん患者さんの緩和ケア相談を受けるなどの活動を開始。「緩和ケア認定看護師」という専門資格をもつ渡辺さんも、今年の4月まで所属していた外科病棟の看護業務に加え、チームの一員として病棟内の緩和ケアに奮闘してきた。
それが今年の2月、「退院前カンファレンス」を行った佐々木好文さん(仮名・49歳)のケアをめぐって、大きな変化を遂げることになる。
「ご本人が家に帰りたいとおっしゃったので、片山先生にお願いしたんです。佐々木さんの場合、入院自体がストレスだったんだと思います」
自宅に戻ったことで、佐々木さんの痛みは激減した。痛みを計る10段階評価が退院時には「3~4」だったが、自宅ではほとんど無い「0~1」になったという。
「なんとかもう少し痛みの緩和ができないかと思いつつ退院されたんですが、片山先生から同行訪問の連絡を受け、自宅でお会いしたときにはほとんど痛みが無い状態だったんです。入院中は痛くて動かせなかった膝を曲げたり、起き上がることもできたんで本当に驚きました」
その秘密を片山ドクターはこう明かす。
「鎮痛剤は十分に処方しますが、入院時と同量です。緩和に関して薬に頼りがちな医師が多いようですが、生活の不自由さを解消することでも痛みは減らせるんです」
身長が184センチもある佐々木さんのため、真っ先に片山さんは最大で、もっとも硬いマットをレンタルした。
「脊椎転移している人が、ふわふわしたベッドに寝てるって考えただけで痛くありませんか。脊椎に転移しているので、排便が頻回になるほど痛いので、腹部の張りも軽減させ、便の回数を減らせるように薬も変えました」
抗がん剤を中止し、余分な薬を減らすことでトイレの回数を減らして痛みを軽減。鎮痛補助に使ったガバペン(一般名ガバペンチンという薬も、佐々木さんには抜群に合った。
「それまでは痛くて横向きにもなれず腰椎に硬膜ブロックもうてなかったのに、ニコッと笑って横向きでできるようになったんです」
片山さんの豊富な臨床経験も役立ったようだ。膝の痛みを訴えられたときには、膝をさすりながら、
「ここをなでたらどう?」
「あ、すごい楽です」
「ここをなでたり、動かしたりしたら治るから、奥さんにやってもらって」
体を動かさないことによって関節などが固くなる「拘縮」をマッサージで解きほぐせば、転移の不安も解消される。佐々木さんが上半身を起こしたときの写真を見せてもらうと、単なる笑顔を超越し、何かを成し遂げた達成感に目を輝かせていた。
渡辺さんはこうした体験を市民病院の上層部に進言。今年4月から科を変わり、病棟と在宅の橋渡し的な役割も担えることに。「退院前カンファレンス」を行った患者さんには、退院後のフォローアップができることになったのだ。
「市民病院は訪問看護の部門がなく、これまでは開業医の先生や訪問看護ステーションの看護師さんにお願いをしていましたが、地域連携強化ということで患者さんのご自宅へお伺いできるようになったんです。『急変時にはいつでも市民病院で支援します』とお伝えすれば、患者さんも在宅を選びやすくなると思うんです。少しでも住み慣れた自宅での生活を望まれる患者さんを支えていきたいと考えています」
片山さんや渡辺さんによって、新たな「地域医療連携」が模索されている。
民生委員も参加し始めた

「尾道方式」はいまも進化しつづけている。
02年からは市の社会福祉協議会との連携で「社医連協」を設置、さらに04年には市の民生委員との連携で「社医民連協」を誕生させた。民生委員も地域の高齢者などの情報を知る者としてケアカンファレンスへの参加が要請されている。
廣安武司さんは、民生委員になって9年目。大手企業の研究開発部門を定年後、尾道市に依頼されて民生委員になった。
「民生委員は月に3度は1人暮らしの高齢者の方の家をまわることになっています。その情報をケアカンファレンスに生かしてほしいということなんです」
尾道市の民生委員は現在、372名。もちろんケアカンファレンスに参加しているのは、まだ限られた人たちだ。
「私がこれまでに出席したのは3回ですし、人によって参加を嫌がるなど、温度差があるのも事実です。でも、私は普段の活動が地域の人たちのために還元できるのはいいことだと思います」
医師たちと同じ勉強会や研修会などにも誘われ、ドクターの印象も変わってきたという。
「それまでお医者さんというのはふんぞり返っているイメージしか無かったんですが、片山先生を知ってから変わりましたね。本当に熱心で気さくな方なんです」
生ききることを全力で補助する

片山さんを幼少時から知る、片山医院の杉田貞子師長もこう笑う。
「実家がすぐそばにあったので、兄妹のように育ってきました。先生からは『腐れ縁』なんていわれますが」
「この道しかない」と自然に看護師になって以来、何10年も片山医院で勤務。病院をおとずれる患者さんはみんな顔馴染みだ。
片山医院も昨年4月に新設された「在宅療養支援診療所」に認定されているが、往診はいまのように特別なものではなく、医者なら当然の風景として目にしてきた。
片山さんは懐かしそうに言う。
「親父は最初に自転車、その次が原付自転車、それからスーパーカブで往診に行ってましたね。昔は家に木の雨戸があったでしょう。夜中に庭から雨戸をコンコンと叩いて往診を頼まれ、『よし、わかった。家で待っとれ、すぐ行く』と出かけて行ったりしていましたから」
そうした経験のためか、「在宅ホスピス」という言葉にも違和感をもっている。
「いまやっているのは在宅医療であって、ホスピスなんていうものとは違います。緩和ケアっていうのも楽に死なせてあげるのではなく、生ききるのを助けること。あくまでも生きることで、死ぬ人なんて考えちゃダメなんです」
片山医院は壽さんで3代目。代々つづく医者家系だが、継承へのこだわりはまったくない。先日、長男から「オレ、医者になんなくてもいい?」と聞かれ、こう答えたそうだ。
「ああいいよ、お前の人生なんだから自分の目指す道に行きなさい。3代で110年やってるんだからご先祖もOKだろう。お前が医者になるって言ったら、いい医者になるまでが気になるけど、ならなきゃリタイアしやすいからな」
片山さんの夢は、病院長などを経験した同級生たちと最高の医療チーム「ベテランズ・クリニック」を結成し、悠々自適に生きながらも患者さんのために力を尽くし、「団塊の世代の底力を見せる」ことだそうだ。


