ペインクリニック小笠原医院 患者さんに「もう1つの家」としての安心感をあげたい
古民家ホスピス「和が家」


国による急激な在宅医療への政策誘導で、昨年から急に老々介護の家庭や、やむを得ず家で療養している独居の方の在宅医療が増えてきているという。
「1人は淋しい。でもそれは自分が生きてきた結果なんだよなあと諦めざるを得ない人もとても多いんです。そういう人は、病院でも誰も見舞いに来てくれず、まわりとも上手くいかない。決して温かい家族に囲まれたハッピーな物語にはなりませんが、そういう方が家に帰るのも『その人らしさ』といえるのかもしれません」
逆に自宅を望んでも、さまざまな事情で家にいられない人も多い。そういう患者さんのため、小笠原さんが4年前にはじめたのが古民家ホスピス「和が家」だ。養蚕農家の1軒屋を借りあげ、「もう1つの家」として看取りなどをおこなっている。
介護士1人が常駐し、訪問医療や訪問看護で患者さんをサポートする。これまで家庭の事情などで家にいることが難しいがん患者さんなど20人ほどを看取ってきた。
病院の延長線上にある、いまの緩和ケア病棟に違和感をもつ小笠原さんは、生活とともに大切に使い込まれた家だけがもつ独特の空気のようなものを気に入ったようだ。
「畳の部屋で寝ころぶと、すうっと眠気がおそってきます。窓を開け放つと心地よい風が吹きとおり、セミの鳴き声や、プールで泳ぐ子供たちの声が聞こえてくる。10代の少年時代の夏を思い出し、そこが現世なのか、来世なのかわからなくなるんです」
木造2階建てで、取材時には1階と2階に計8名の方が、個室やふすまで仕切った部屋などで生活していた。7名が認知症の方で、がん患者さんは1名だけになる。
2階の個室の窓際にちょこんと腰かけ、庭を眺めていた上品な女性が佐藤春代さん(仮名)。入居した1カ月前には卵巣がんによるリンパ浮腫で左足が丸太のように腫れていたが、いまは症状緩和が上手くいって小康状態を保っているという。
病気は違えど、思いやりで支えあう
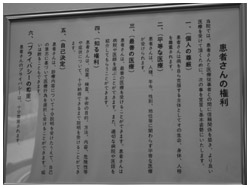

だが、認知症の方々との同居生活は気を遣うのでは――という記者の質問に、佐藤さんは微笑をうかべてこう答えた。
「病気はそれぞれ違いますが、お互い病気をもった者同士ですから。相手も気持ちよく、お互い気持ちいいような話ができればそれでいいんじゃないでしょうか」
認知症といっても、まったく会話が通じないわけではない。いいときもあれば、悪いときもある。お互いを思いやる気持ちがあれば、伝わるのかもしれない。
佐藤さんの2人の娘はすでに嫁ぎ、自宅では1人暮らし。「和が家」では常にヘルパーさんなど誰かがいるので、それが安心感につながるのだという。
また、佐藤さんは「音」が重要だという。
「シーンと静かなのは嫌だし、音が聞こえてきてもそれがまったく自分と無関係な音だとさびしいものです。いろんな音が、普通の家のようにしているのが落ちつくんです」
ちょうどお昼どきで、階段の途中あたりからはヘルパーさんが包丁を使うトントンという小気味のいい音が聞こえ、煮物の和風だしのいい匂いが漂っていた。3度の食事も、その日にある材料を見つくろってヘルパーさんがつくってくれている。
佐藤さんも、給仕や皿洗いを手伝うそうで、
「気がまぎれるんですよ」
と、にっこり微笑んだ。
本当の家族にはなり得ないだろうが、家族のような安心感がこうして芽生えているようだ。
がんの告知を受けている佐藤さんだが、もっと詳しい情報を得たいという気持ちはないらしい。リンパ浮腫がひき、痛みもないことに今は満足されているようだ。
小笠原さんはこう言う。
「ホスピスの概念は、患者さんが自分の病名を理解し、余命をしっかり受け止めて、自分の判断で緩和ケアを選びとって有意義で充実した最後を過ごすこととされ、最初のうちはぼくもそう考えていました。だけど、そんなに簡単なものでもない。 いまは何でも自己決定、自己責任というけど、そこには“安心感”がありません。長期間にわたって不安と闘わなければならないがん患者さんに、24時間、1人で闘えなんていうのはあまりにも酷。安心しなさい、大丈夫ですよって言葉を90パーセントぐらいは伝えるべきだと思うんです」
ホスピス医としての孤独な15年間の闘い
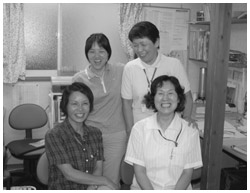
「和が家」での取り組みを知り、島根県から1年限定で移住し、看護業務に携わってきたのが青木佐恵美さんだ。島根県に戻ったあと、同じような看取りの家をつくるのが夢だ。
「ここに就職するか、近くの病院に勤めるかのどっちかだと思って電話したら、『1年だけでいいよ』と小笠原先生が言ってくださって。 多くのことを学びましたが、とくに痛感したのが仲間の大切さですね。小笠原先生には志を同じくする仲間がたくさんおられる。私も1人ではできないので、帰郷後に、まず仲間づくりからはじめたいと思っています」
こうした希望が見えはじめたのは近年になってから。小笠原さんはずっと県内の開業医に在宅ホスピスが広がらないことを思い悩んできた。患者さんや家族には感謝され、一般市民には少しずつ理解されても、同じ開業医は「あそこは特別」と白眼視された。気持ちが塞いでしまった時期もあったようだ。
「2年ぐらい前までは、本当に悲観的でしたね。開業医が中心となった在宅ホスピスケアの拠点は、地域ではいつまでもまばらな点としか存在せず、面として広がっていかないのかなあと思っていました」
それが解消されたのが2年前。長女の結婚相手が、同じ道を目指すと言ってくれたのだ。小笠原さんが24時間気が抜けない在宅ホスピス医になって15年。これまでいかに孤独な闘いだったかは次の言葉が如実に示している。
「本当にうれしかったですね。人間のモチベーションなんて、そんなもんなのかもしれません」
次の世代へ伝えていく

在宅ホスピスのパートナーとなった竹田幸彦さんは、ひょろりと背が高く、優しい雰囲気がにじみ出ているドクターだ。実はこの竹田さんにも「暁の大脱走」ならぬ、患者を「小脱走」させた経験があるという。
「研修2年目ですから、いまから9年前になります。呼吸器をつけた肺がんの患者さんに何かしたいことがありますかと聞いたら、『家に帰りたい』とおっしゃったんです。 酸素が大量に必要で家に帰れる状況じゃなかったんですが、こっそり病院から連れ出して自宅に連れて帰りました。家のソファーに横になれたのは10分程度だったんですが、『ああ、帰ってきて良かったあ』と、心の底から喜んでくれているのが伝わり、ぼくも嬉しかったんです」
そのときから在宅医療に関心をもったが、10年ほどは大学病院の消化器内科医として研鑚を積んだ。病院を辞職後、1年ほど別の診療所で在宅医療を学び、昨年の4月からクリニックで働いている。奥さんの果南さんも週2日ほど非常勤医師としてサポートしてくれている。
2人にとって自然なことだったのか、「暁の大脱走」と「小脱走」についてはお互いに知らず、小笠原さんに記者が伝えると、
「へえ~、やるねえ、彼も」
と、心底うれしそうだった。
やっとひと息つける状態になり、趣味のギターをいかして熟年バンドを結成した。
「会計士さんとか、ハム屋のおっちゃんとか、50代の仲間と2年前からフォークソンググループをやっています。楽しいですよ」
記者も1度ギターの生演奏を聴かせてもらったことがあるが、腕前はまさに「玄人はだし」。
孤独のつらさを知るドクターが、音楽でも「和が家」の入居者や、市民などを癒しはじめた。


