花の谷クリニック 自宅に代わる医療のサポートを備えた生活の場の提供を目指して
最期を看取るだけではダメ
「花の谷」は国の認可を受けた緩和ケア病棟のように施設が充実しているが、1日3800点(3万8000円)の診療報酬を受けない、一般の有床診療所だ。
「最期を看取るだけのホスピスにしたくなかったからなんです。病気の発症から闘病中もずっと支えられる、ターミナルケアだけでない緩和医療を目指しています」
国内の緩和ケア病棟は、ターミナル患者しか入院できないのが現状だ。それを変えるためには、「積極的治療を行わない」と決めるべきではないと伊藤さんは言う。
「10数年前までの緩和ケア医の役割は、積極的な治療をやめ、ターミナルケアをすることにありました。緩和ケアができていなかったためですが、これからはそこに安住せず、最新医療も併せて行っていく必要があると思います」
ここ数年、急性期の患者を受け入れる病院は3カ月で診療報酬が下がることもあり、まだ治療があると思われる患者でも退院させる傾向が強まっているという。
「だから、治療のために病院へ押し返すことに大きなエネルギーを使っています」
2006年の暮れにも、がんが脳転移した1人の患者さんが、「年は越せない」と総合病院から紹介されてきた。まだ治療はあると思い、別の病院で検査を受けてもらうと、「ガンマナイフという放射線治療なら可能」と診断された。全国にまだ50台ほどしかないガンマナイフだが、その患者は2月に治療を受けて脳転移は消え、いまも「花の谷」で穏やかな生活を送っている。
「完治したわけではありませんが、その5カ月を無駄な延命っていうんでしょうか。延命治療という言葉はものすごいマイナスのイメージでとらえられていますが、誰だって延命したいんです」
QOL(生活の質)が保たれた状態での延命なら、望まない人はいない。信頼できる医師による、こうした「橋渡し」をこそ、患者は望んでいるのではなかろうか。
地域の人たちも参加する「気功教室」

多目的ホールにはグランドピアノも置かれていた
毎週金曜日は、「気功教室」が開かれる日だ。
伊藤さんに誘われて、記者も飛び入り参加させてもらう。食堂を兼ねた多目的ホールに集まったのは総勢約10人。ほとんどが近所の主婦のようだが、1人だけ入院患者らしき男性がいる。
気功は、呼吸が大切だ。先生は頻繁に呼吸のアドバイスをする。
「はい、ゆっくり吸って。それからゆっくり吐きま~す」
足の血行を良くするため、座って足指を1本ずつ回す運動をしているとき、1人の女性が、
「手が反対よ、こっち」
と、教えてくれた。どうも回しづらいと思っていたら、左手の指で左足の指をつかんでいたので不恰好だったのだ。この女性、ポーズが様になっていると思ったら、
「6年やってます」
というベテランさんだった。
気功教室は、入院病棟の開設時から続けていると伊藤さんはいう。
「とにかく病院が、患者さんだけの集まる場所っていうのを崩したかったんです。健康な方でも気軽に利用できるようになればいいと思って始めたのがこの気功教室なんです。気功は動きがゆっくりなので、高齢の方や障害者の方にもいいんですよ」
家にいるような安らぎを感じる「花の谷」
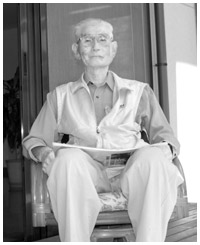
根本昌さん
気功をごいっしょした、根本昌さんに話をうかがった。
「口がなあ、もう少し上手くしゃべれればいいんだけどね。痛みはないけど、歯茎が腫れてっからね。ただ、1人でいると考え事をするから、話し相手がいたほうがいいんだ」
根本さんが咽頭がんと告げられたのは2006年7月。放射線と抗がん剤治療をするよう医師から勧められるが、それを断った。
「せがれが苦しむ様子を見ていたからね」
根本さんの長男は、47歳の若さで大腸がんで亡くなった。そのときの抗がん剤治療の苦しみを見て、「77歳の自分にはきつい」と、積極治療を控えた。
「でも、紹介された伊藤先生は、もう1回別の病院で診てもらえって言うからね、総合病院の耳鼻科に行ってきたんです。するとそこの先生は、『これ以上良くなるか、悪くなるかはわからない』って。本人がやるといえばやるけど、無理には勧められないって言われたからね」
根本さんは、ちょっと口が動かしづらいだけで、日常生活に支障はない。短期入院で、自宅と「花の谷」とを2週間ずつ行き来することになっている。
自宅は「花の谷」から車で1時間ほどのところにある。妻が認知症(痴呆症)をわずらった4年前から、介護しながらの家事をこなしてきた。根本さんが入院するにあたり、妻は自宅近くのグループホームに入居。離ればなれの生活に。それが何よりつらいようで、ひとり暮らしの「自宅」より、「花の谷」と妻のいるグループホームが根本さんにとっての“家”なのかもしれない。
「ここ(花の谷)の人はね、何か欲しいとすぐに車で連れてってくれたりね、本当にありがたい。先生も話しやすいしね。でも、ばあさんに会いに行くのが生きがいだな。黒糖入りの蒸しパンが好きでね、買っていってやると喜ぶからねえ」
入院以来、根本さんは院内に飾られた生け花の鉛筆画を書いている。絵を見せてくれながら、こうつぶやいた。
「こんな病院がね、いっぱいできてくれるといいんだけどね」
自宅の近くにあれば――というふうにも聞こえた。
自然な環境のなかで生きていたい

歩いて数分で、すぐに紺碧の太平洋が広がる
去年の4月からデイセンター「庄左ヱ門」に通っているのが藤城俊子さんだ。
藤城さんは、2年前の7月23日に起こったことは記憶にない。
「お手洗いで倒れてたらしいんです。私の意識が戻ったのは、入院してから2~3週間たってからなんです」
なぜ、どのようにして倒れたのかはわからない。打ちどころが悪かったらしく、頸椎損傷にいたった。もちろんショックだったが、リハビリをすれば回復すると思い、退院してからはリハビリ病院で機能回復訓練に取り組んだ。
が、さらなる不幸が藤城さんを襲う。リハビリで立ったり、数メートル歩けるようなった矢先のことだった。
「2006年の7月の末ぐらいから痺れが出てきて、もう歩けないっていわれて……。真っ暗闇に引きずり落とされたんです。それからは毎日、涙、涙、涙です」
「死」の文字も何度も頭をよぎり、自分はみんなのお荷物とばかり思いつづけた。
そんな絶望感に苛まれているとき、何度もお見舞いにきてくれていた友達が、「俊子ちゃんが笑ってる顔を見たら、勇気づけられる」と言ってくれた。
「ああ、こんな私でも生きていて価値があるんだって初めて思えたんです。家族の支えはもちろん大切ですが、友達のありがたさにも気づきました」
2度のどん底をなんとか乗り越え、前向きに生きようとリハビリに取り組んでいた2007年4月、3度目の試練が藤城さんを襲う。
乳がんだった。
そのときに藤城さんが感じたのは、驚きや恐怖ではない。
「がんって聞いてうれしかった」
と言う。
ベッドで寝たきりの状態で命を長らえるより、乳がんの治療をしなければ、余命はかぎられてくる。人の世話になりつづけることの負担感は、当人しかわからない。
そんな藤城さんを家族全員が力づけ、医師の伊藤さんや看護師たちも、乳がん治療を勧めた。多くの人の思いが、藤城さんに届く。
「自分ひとりの意見って偏ってるんですよね。だからいろんな人と話ができるっていうのがプラスになるんです。人の意見を聞きつつ、何回も同じところを行ったり来たり。悩んだり、嘆いたりしながら、やっと整理がついたんです」
だから今、「死は怖くない」と言う。
「人間にとって何が幸せかといったら、自分の思うようにやってきたことに対して、自分が満足すること。私は自分がやりたいように、精いっぱい生きてきたという自信があるんです。気持ちの整理さえつけば、怖いことなんてありません」
藤城さんはいま、乳がんの治療を受け、退院後にもう1回歩けるようにリハビリにチャレンジしたいと思っている。
「手術を受けて元気になれたら家に帰りたいですよ。でも、もしダメでもここでお世話になりたい。ここは人のやさしさっていうようなものが感じられる病院なんです」
そのとき、ガラス戸の外のウッドデッキ上をコロコロと太った猫が、こちらを見向きもせず、まるで映像のように横切って行った。
「ここにはね、太ったネコが2~3匹いるんですよ」
と、根本さんは声を出して笑った。
「昔からできるだけ家で死にたいっていうことを言うでしょう。もし自分がそうであれば、自然な環境のなかで生きていたいって思いますね」
根本さんは確かに「自然な環境のなかで生きていたい」と、おっしゃった。


