佐久総合病院 専門科を越えて地域ケアを展開してくれる総合病院
入院中からかかわる緩和ケアチーム
「地域ケア科とは、在宅が決まった時点からのかかわりです。でも、緩和ケアチームはそれより前、入院中から症状緩和で患者さんやご家族にかかわっています。以前より早く関係性が築けるようになったんです」
2006年10月から自宅で暮らす木場博人(仮名・85歳)さんもその1人だ。木場さんは87年に大腸がんの手術をした。2006年9月に下血をしたことから詳しく検査、その結果再発がわかった。持病の肺閉塞性疾患も抱え、通院も息切れがしてつらい状態だった。
しかし、手術がまったく不適応というわけではない。依頼を受けた山本さんも悩みに悩んだ。カルテには、こう記している。
《本人〈手術はしたくない。様子をみて良いと思う。症状が出れば対処してもらう〉 妻〈90まで生きてもらわないと。私たちでは決められないので〉》 v 在宅を決める場合、患者さんや家族だけでなく、親戚などの周囲の人間関係への配慮も必要になる。木場さんの親戚にはドクターがおり、詳細を聞きたがっているということを伝え聞いた山本さんは、症状について詳しく説明した手紙を書いた。その末尾には、こうある。
《以上が、これまでの経過と行った検査の結果です。必要なら全ての資料をお送りし、ご検討いただくことも可能です。よろしくお願いいたします》
本人と家族が苦悩の末に決断したあと、遠い親戚などから反対されることも少なくない。遠方にいると情報が届きにくいから心配が募る。患者のためを思う近親者だからこそ、真摯にうったえれば伝わるのだ。
「いろいろ言われて、いちばん苦労なさるのはご家族です。全員にできるわけではありませんが、必要であれば手紙を書いたりしないといけないと思います」
親戚のドクターにも納得してもらい、木場さんの在宅生活が始まった。
患者と家族の心配をひとつずつ解決する

縁側の軒下にはツバメが巣づくりに励んでいた

裏庭の果樹園は信州らしい美しい風景
木場さんの自宅は、病院から車で5分ほどの広い庭のある立派な1軒家だった。
記者がお伺いすると、木場さんはちょうど庭を散策中だった。裏庭はリンゴや梨の果樹園になっており、満開の季節は終わったものの梨の白い可憐な花が咲いている。
ゴールデンウィークに帰省していた関東在住の子供たちとドライブに行ったという話から始まり、すぐに下痢の話を奥さんがはじめる。
「ちょっと気を緩めてうな丼を食べたんです。どうも油っぽいものに弱いみたいなんです」
奥さんは夫の食事にかなり神経質になっているようだ。肉も鶏肉や脂身の少ないしゃぶしゃぶ用の肉にし、漬けている野沢菜も繊維が多いため食卓にあげないという。
「あまり神経を使っちゃうと食べるものなくなるんですけど……。ほかの方はどうやっているんでしょう」
山本さんはあまり神経質になり過ぎないように諭すが、やはり心配はぬぐいきれない。2人の会話を聞いていた木場さんが冗談まじりに言った。
「そんな心配するから世界旅行に出てしまうんだ」
もちろん本当の旅行ではない。夫の看病に必死になり過ぎ、1度めまいをおこして倒れたことがあり、それを同じようにグルグルまわる「世界旅行」という言葉で明るく笑い飛ばしているのだ。救急車を呼んで事なきを得たが、もし奥さんが寝込むようなことになれば、木場さんの在宅生活はむずかしくなる。
しかし、奥さんの心配は自分ではなく、夫に向かう。
「お父さんは先生の顔を見ると安心するみたいで、いますごくいい顔していますけど、今朝はこんな顔してなかったんです。朝計ったら熱も34度8分だったんですよ」
と、奥さん。
山本さんはすぐに返す。
「34度8分はないよ、さっき計ったら36度8分でしたよ。体温計が変だったんでしょう」
みんなが一斉に笑った。
手術をせず、自宅で様子をみようと決めた理由を聞いてみると、夫に代わって奥さんが答える。
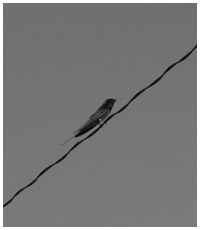
巣づくりが終われば、新しい命が誕生する
「そこのところなんですけどねえ、私も思い悩んでねえ。先生にいろいろとお聞きしたり、小言いったりして申し訳なかったと思うんですけども、寝ても覚めてもどうしたらいいかって……。でも、転移しなければ90ぐらいまで生きられるかしらって気を大きくもったら、少し楽になりましたけどね」
もと高校の先生だったという木場さんは終始にこにこしながら心配を口にする妻をやさしく見守っていた。
そのとき、外でツバメが旋回しながら気持ちよさそうに甲高い声をあげた。例年のことだが、いまは軒下での巣づくりの真っ最中。
「やっぱり家はいいですよ」
と、ご夫婦の言葉が耳に残った。
研修医の「緩和ケアへの気持ち」に変化が
医師の山本さんが絶大な信頼を寄せるのが、緩和ケアチームの専属看護師、松川喜代子さんだ。松川さんは東京から移り住んで10年以上佐久病院に勤務。緩和ケアチームが発足する前に、先輩が立ち上げた「ホスピスケア研究会」に参加したことから、いまの仕事に抜擢された。
松川さんは、この1年間で研修医の緩和ケアへの興味の持ち方が変わってきたことを実感している。
「実際に山本先生と一緒に患者さんを診て、研修医のほうから積極的に質問してきたりするようになったんです。将来、緩和ケアをやってみたいという声もあるようです」
佐久病院は、研修医がそのまま就職することも多く、山本さんもその1人だ。
また地方の病院では研修医が足りずに困っているところが多いが、佐久病院では2006年も15人の定員に60人の応募があった。
村井ひかるさんは、2年の初期研修を別の総合病院で終えたあと、佐久病院での後期研修2年目に入った。
「内科の一般的な勉強をしながら、在宅もやってみたかったんです。決して教科書どおりにはいかなくて、いまは毎日毎日この患者さんの問題はなんだろうということに悩みながら、向き合っている状況です」
「一般の患者のため」を胸に、イベントも開催

こうしたチームがうまく機能するのは、自分のことより「どうすれば患者さんにとって幸せか」という考え方が徹底されているからではなかろうか。
地域ケア科の医長・北澤彰浩さんはこう語る。
「違う科との敷居を低くするためには、やっぱり人の交流だと思うんです。うちでは研修生の全科ローテーションを昔から取り入れています。全病棟をまわりますと、みんな知り合いになりますよね。一緒に働いたことのある顔見知りになると、やっぱり話しやすいんです」
2007年で61回目となった「病院祭」などの行事も、職員間はもちろん地域住民との大切な交流の場だ。ここでは、毎年1回、週末に病院を地域に開放し、病気や最新医療についての説明をしたり、自分の心音を聞いたり、「白衣を着てみませんか」といった体験コーナーもあったりする。野外では職員らが屋台で焼き鳥を焼いたり、餅をついたりする楽しい催しも行い、医療を身近に感じてもらうお祭りだ。
職員にとって、もっとも大変なのが準備作業。「地域ケア科」看護師長の関真美子さんは言う。
「準備のための1週間は、本当に毎晩、毎晩夜の12時ぐらいまで、みんな作業に追われるんです。2006年も2005年も、よくあんなに熱くなったなあと思います」
各科ごとにパネルをつくるのだが、とくに毎年の「メインテーマ」の担当科は大変になる。そして祭りの前に、担当の医師がパネルの説明を故・若月総長の前などで行うのが慣わしだ。
「パネルの内容の言葉が、医療用語で難しかったりすると『これが一般の人にわかるのか』ってダメ出しがあったりもするんです」
ボランティアで作業したスタッフに不満がないはずはない。が、医療側の押しつけでなく、「専門家ではない患者のため」という強い信念に基づいているので徹夜をしてでも直すのだ。
この姿勢が、患者重視になって表れる。
医師の山本さんは田植えシーズンなどにはこう頼まれたりする。
「先生、週末は田植えでみんな忙しいから、退院は来週にしてくんねえかい」
病院サイドの事情を考えつつも、山本さんは小声で「はい」というそうだ。


