さくらいクリニック ふわっとフィットした距離感での在宅ケアが人気の秘密
異常な病院死が8割以上の日本

クリニック2階は独居の方々などの「体と心のリハビリルーム」
また先日、40代の子宮がん患者の症状コントロールが上手くいかず、稀なケースだが入院させてしまう結果になった。
反省することしきりだったが、1つだけうれしいことがあったという。
「その方がね、こんなに苦しいのに高校生の息子さんが何もしないってずっと批判されてたんですが、入院の前に一生懸命お母さんの背中をさすってたんですよね。その姿をみて、在宅の意味も少しはあったかなと思ったんです」
病院で亡くなる方が、在宅死の数を超えたのが昭和54年のこと。
「たった30年しか経ってないんです。それまで匠の技のように、親から子へ、さらに孫へと伝わってきたことが、病院という箱のなかに閉じこめられ、死が日常から喪失してしまった。それには医者の責任もあります」
医者として、病院での死が満足のいくものになりにくいことを知っているからこそ、在宅医療をすすめてきた。
「8割以上の方が病院で亡くなる今の日本は明らかに異常です。オランダでは、病院、施設、家で亡くなる人がほぼ3分の1ずつになってるんです。自由に選択できれば、そうなるのかなと思うんですよ。アメリカでも病院4、施設2、家が3です。人類数千年の歴史で考えても、家以外の場所でほとんどの人が亡くなるのは、今の日本だけなんです」
おかえりなさいプロジェクト
桜井さんと同じ考えをもつ人たちが、1つの計画を成し遂げた。その「おかえりなさいプロジェクト」の発起人は、福島県にある東日本国際大学講師の服部洋一さん。米国ホスピスを13カ月フィールドワークし『米国ホスピスのすべて』(ミネルヴァ書房刊)などを著している。在宅医療の進んだアメリカに比べ、日本の遅れを痛感。一般の人向けの冊子を作ろうと桜井さんらに声をかけたのだ。
「服部くんは弱冠32歳。若手の文化人類学の研究者なんです。以前、うちの病院にも調査研究に来られた関係でぼくに声をかけたんでしょう。ぼくのほうも必要性を感じていたため、やりましょうとなったんです」
2006年8月、小冊子『あなたの家にかえろう』が完成。全32ページのほぼすべてにわたって1軒の家での日常風景が描かれている。そこに人の姿はなく、ちゃぶ台に蚊取り線香、アイロン、グローブにバット……と、どこの家にでもあるようなモノから家族の物語へと空想がふくらんでくる。
こうしたイラストの必要性を主張し、知人のプロに頼んだのが吉田利康さん。医療関係者中心のメンバーのなか、市井の遺族の視点を冊子にもりこんだ立役者だ。
吉田さんは平成11年に、看護師だった妻の章江さんを急性骨髄性白血病で失った。入院期間は約1年半。ターミナルの宣告を受けた妻が口にしたのは「家にかえってもいいやろか?」という言葉だった。
大学病院の主治医に退院を申し出ると、「死亡確認をしてくれる医師を見つけなさい」。長年世話になってきた近くの開業医に往診をたのむと、「緩和ケアはできません」。
とにかく開業医に死亡診断書記載の約束だけはとりつけ、男だけの親子3人によるケアがはじまった。長男は車で通院を手伝い、高校生だった次男も車椅子を押したり、母親の最高の話し相手になった。吉田さんも見よう見まねで必死に食事をつくった。
「おかえりなさい」という言葉からスタート
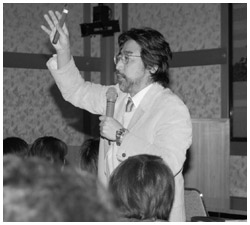
講演でも「あなたの家にかえろう」を配って理解を訴える
「でもね、なにしてもダメじゃないですか。それは見ててわかるんです。早く逝かしてやりたいという気持ちが自然にわく一方、死なれたらぜったい困ると揺れつづけました」
別れの2日前。壁にもたれている妻が、吉田さんの顔をのぞき込んでこう言った。
「お父さん、疲れてるみたいよ。まぶたが腫れてる。私のことはいいからちょっと横になりぃ」
「お前のしんどそうな顔を見てたら、つろうて1人で泣いてたんじゃ。まぶたぐらい腫れるわい」
強がりのつもりだったが、妻は顔をぐちゃぐちゃにして泣きだし、2人で手をとりあって号泣した。
吉田さんは妻を看取った約1年後、ホームページですぐ近所に「さくらいクリニック」があったことを知る。
「自転車で行ける距離に桜井さんがいたんですよ……それを知ってればと悔しくて、悔しくて……」
そのあと、遺族会や遺族のための掲示板を主催。今回の冊子にも遺族の視点を入れようと奮闘した。
多くの人の思いがぎっしり詰まった冊子を桜井さんらは今、あちこちに配布している。財団法人の助成金で最初の5千部を刷り、ポケットマネーと寄付金を募ってなんとか4万部にまでこぎつけた。
「1冊刷るのに50円かかるんです。企業なんかの大口の寄付があれば、10万部も夢じゃないと思ってます」
この「おかえりなさいプロジェクト」と同じように、桜井さんは在宅医療をはじめるときには「おかえりなさい」という言葉からスタートする。患者の多くはにっこり笑って「ただいま」と、応じてくれるそうだ。


