ホームホスピス宮崎 「宮崎全体を他人に思いやれるホスピスに」を目指して
在宅を実現するために必要なバックアップベッド
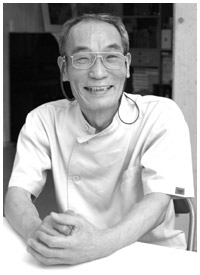
そんな市原さんをバックアップしてきたのが夫の市原美宏さん。「いちはら医院」のドクターで、19年前の開業時からずっと在宅医療に取り組んできた。このドクター市原にとって、奥さんはどんな存在なのだろうか。
「普通はほら、院長のカミサンっていうのは院長の背中からものを言ったりするでしょう。彼女(妻)はね、向こう側にいるんですよ。極端にいえば批判者であったりもするんです」
と、ドクター市原。1人の市民の目線で夫の仕事を支える妻に対し、初心を忘れないよう仕事に取り組む夫の姿勢は、妻のこの言葉が証明する。
「(夫は)悩む人なんですよ。患者さん1人ひとり症状も性格も違うでしょう。どうしてあげたらいいのか、しょっちゅう悩んでます。でも私、それが大事だと思うんです」
「宮崎市郡医師会病院」(1市3町の医師会員の病院)に緩和ケア病棟をつくることが決まったとき、往診や外来を行わず、在宅医のための後方支援(バックアップベッド)にすべきだと提案したのはドクター市原だった。
「そのころぼくは緩和ケア病棟はいらない、それぞれの開業医が地域でターミナルケアに取り組めばいいと思っていました。でも、もし医師会病院につくるんだったら医師会員全員がかかわるシステムにし、緩和ケア病棟は『仮の宿』にすべきだと話したら、執行部が聞き入れてくれたんです」
とんとん拍子で事は運んだが、肝心の医師が見つかっていない。ドクター市原が探していると、たまたま夫の実家が宮崎のため夫婦で帰郷を考えているという女医さんの存在を耳にする。しかも、緩和ケアと在宅ホスピスの両方に取り組んでいる医師だった。
「何なの、これはって感じがしたもんね。とてもじゃないけどあり得ない。ラッキーですよ」
と、ドクター市原は笑顔でいう。
地域全体で緩和ケアのレベルアップを


それが、川崎市立井田病院に勤務していた黒岩ゆかりさん、いまの医師会病院緩和ケア病棟医長だ。井田病院は、古くから在宅医療にも取り組んできた先進的な病院だが、その現場にいたからこそ、問題点も感じていた。
「井田病院のように��和ケア病棟と在宅医療の両方をする病院があると、結果的に地域の開業医の先生に在宅ケアが広がりにくいという点も残念ながらあるんです」
地域全体の底上げがあってこそ、本当の意味で在宅ホスピスは可能になる。緩和ケア病棟の設立当初から開業医とともに疼痛緩和などの症例検討会を毎月開催。いっしょに緩和ケア技術のレベルアップを図ってきた。
しかし、ある1点において当初はつまずいた。在宅に誘導したいがために「入院期間は2週間」という期限を設定。これが患者と家族を不安にさせ、最初の2年間は12床のベッドのうち利用されるのが半数に満たない状態が続いた。
「でも、3年目から長期の入院も受け入れる形に方向転換すると、稼働率が8割から9割になりました。開業医の先生との連携もとれているので、目指したものは間違いではなかったと思っています。緩和ケア病棟は、死に場所というイメージをもっておられる方が多いのも事実なんです」
医師会病院の緩和ケア病棟は、入退院を繰り返すこともできる。家族の介護疲れを理由とする入院や、患者の病状変化に対する緊急入院を必ず受け入れる態勢も整えている。
「宮崎市郡内で在宅医や訪問看護師がいないから退院して自宅に戻れないということはほとんどないと思います。問題は、家族の介護力をどうサポートしていくかです」
本人が希望し、家族の気持ちがあれば
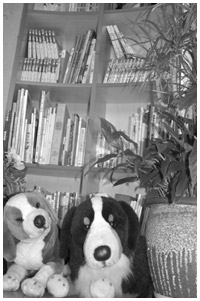
去る9月、医師会病院から在宅へ引き継いだ1人のがん患者を「いちはら医院」のスタッフが見送った。
その女性Aさんは、まだ47歳。告知を受けた際にも冷静だったので、総合病院の看護師らも驚いていたという。3人の子どもに恵まれ、夫婦それぞれの両親が健在だったこともあって、家族介護力は十分。在宅への引き継ぎのため入院先を訪問した看護師の田原信子さんとは、たまたま同郷ということもあってすぐに心を開いてくれたそうだ。
「普通は私たちが入ってサポートしながら在宅療養の流れをつくって行くのですが、Aさんの場合は最初から出来上がっていました。Aさんの家族ほど意思が固まっているところは稀ですが、本人が帰りたいと言い、ご家族がそれを叶えようという気持ちさえあれば、在宅は可能なんです」
と、田原さんはいう。
Aさんは、子どもが大好きな保母さんだった。入院中にも大勢の見舞い客が訪れ、体がつらくても笑顔で応対し、あとで疲れが出てベッドに倒れ込む姿をご主人は何度も見ている。他人に気を遣う人ほど、「家に帰りたい」と思うのかもしれない。ご主人はこう話す。
「入院してしばらくしてから黒岩先生が『うちへ帰ってみませんか』って。あのときの喜びはなかったですね。最高の笑顔でした」


