にのさかクリニック 人と人とがつながっていく。それこそが在宅ホスピス
妻の死を機に人生が180度変わった脳外科医
こうしたニノ坂さんの活動を耳にし、たった1度の面会で意気投合。2006年からクリニックの仲間になったのが小野道夫さんだ。
小野さんは、東京大学医学部の脳神経外科医として教授への道を歩んでいた。が、82年に留学先のアメリカで妻が第1子を安産した後、20時間目に肺塞栓症で突然亡くなった。命をつなぐように誕生した長男の笑顔を見ながら、生きる意味について考えた。
「これしかないと思っていたエリートコースが全く意味の無いものになってしまったんです。なぜか自分でも分かりませんが、それ以来アフリカに行きたいと思うようになって……」
結局、アフリカにたどり着くまでに11年を要するが、その間にブラジルやアルゼンチンで医療活動に従事した。 「ワールドビジョンというNGOのザンビア駐在員をさせていただいて。僻地に診療所を作ったり、干魃の地域に井戸を掘ったりのお手伝いもしました。またネパールでは僻地農村の婦人の識字率アップや、源づくり、子ども達への保健衛生教育など地域保健開発に取り組んだりしました」
04年にはインドのケララ州に行き、在宅での緩和ケアや日本より遥かに進んだボランティア文化に目を見開かされた。
「診療所がない、医者がいない、病院に入れないで、インドは家族や地域住民主体のコミュニティ緩和ケアとしてボランティアが大活躍しています。愛する家族や親しい隣人に囲まれて痛みもなく過ごせることはすばらしいことだと感じました。このケララ州のボランティアによる地域緩和ケアはWHO(世界保健機構)のモデルにも選ばれています」
アフリカ行きで共感した女医の惠さんと再婚。たまたま帰国していた05年に夫婦でニノ坂さんに会い、インドの話などで盛り上がって、ともに在宅緩和ケアに取り組むことになった。
「ニノ坂先生の目指すコミュニティケアは、具体的なケアシステム構築と同時に、生命に対する意識変革や、人々の温かな心の通い合いをもう1度復活させたいということがあると思うんです。日本での在宅医生活はまだ数カ月ですが、自宅で過ごすことの持つ力は確信しました。みなさん平安になられるし、本当にお元気になられるんです」
クリニックを拠点に広がる「ニノ坂つながり」の人々


小野さんだけではない。クリニックで事務などを担当する岡村和久さんは、福祉施設で働いていたソー���ャルワーカー。自ら「ニノ坂先生のもとで勉強したい」と、5年前に飛び込んできた。
ニノ坂さんの魅力にとりつかれた患者さんもいる。木村喜郎さんは、15年ほど前に食道がんの手術を行った際に「余命1~2年」と宣告をされたが、「でも、気がつくと15年経ってました」。
手術の影響で声はいまもかすれているが、いつも笑顔を絶やすことがない。がん患者と家族の会「希来の会」を主催し、大学に再入学。生涯学習インストラクターの資格も得た。カナダ、ニュージーランド、バングラディシュに続き、2005年はピースボートで世界1周もした。
「ニノ坂先生と出会えたので、がんになって良かったと思うくらいなんです。先生のまわりにはすばらしい方が多く、行くところ行くところで癒される。エネルギーをもらったから今があるんです」
こうした人の輪を「ニノ坂つながり」と呼ぶ。「ニノ坂つながり」は、クリニックを拠点にどんどん広がっている。
楽器のオカリナ教室、毎週火曜日には「健康教室」と題してニノ坂さんや病院スタッフが講演する会を行うなど、趣味や勉強会でつながっていく。
終末期の選択「レット・ミー・ディサイド」
その健康教室で9人の参加者とともに「レット・ミー・ディサイド」についての話を聞いた。
「レット・ミー・ディサイドを訳すと『わたしの選択』、つまり事前指定書という意味です。意識不明になったり、重い病気のために意思決定ができない状態となったときのために、前もって自分の希望する治療を指定したり、代理人を指定しておく書類です」
事前指定書は、誕生したカナダ国内ではすでに数10万人の方が持っているという。ニノ坂さんは「福岡レット・ミー・ディサイド研究会」をつくり、勉強会や普及活動を行ってきた。
「みなさんが82歳になったとき、消化器内出血で救命救急センターに運ばれた場合にどう選択するかを考えてください」
と、ニノ坂さんは参加者に尋ねた。症例として挙げられたのが、3年前にアルツハイマーを発症し、住所や名前もいえず、血圧は70くらいに低下した場合だった。この状態で、健康教室に参加していた9人に(1) 集中治療、(2) 外科的治療、(3) 限定治療、(4) 緩和ケアの4つのうちどれを選ぶかと聞くと、
「緩和ケアです」
と、9人中7人が答えた。
本人は「治療しないで」、家族は「助けて」のギャップ
「そしたら立場を変えて、自分の家族がこういう状態になったらどうしますか」
と問われると、逆にほぼ全員が「集中治療」を選択。驚いた表情の参加者に向かってニノ坂さんが言う。
「自分のときと家族のときとでこんなにも違うんです。医者としての立場になれと言われても想像つきにくいと思いますが、医者も困るんです。本人は治療するなと言っておった。家族は助けろ、それで医者も悩む。そのために事前指定書があるといいんです」
特筆すべき点は、家族など2人の代理人の署名とともに「かかりつけ医」への相談と署名が入っているところだろう。専門家と話し合うことで、少しずつ見えてくるものもあるはずだ。文書には自分の意思が伝えられる間は「効力を発揮しない」と明記され、考え方が変わればいつでも書き換えられる。しかし、健康教室の参加者のなかでは、1人しか書いていなかった。
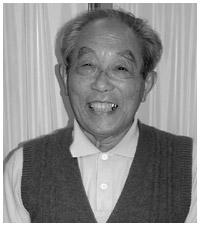
その竹田照さんはこう話す。
「身内に管まみれのいわゆるスパゲッティ症候群の人がいたんで、それは絶対イヤだと思って書きました。最初は自分のためだったのに、結局まわりまわって、私の子どもたちやお医者さん、国家財政のためにもなると最近では思い始めたんです」
竹田さんは5年前にアルツハイマーの妻を自宅で看取った。その際、食事介助しながら「おいしいか」と聞くと頷く妻を見た体験から、認知症で全介助状態になっても「回復可能な状態」とすることにした。事前指示書の「個人的要望」の欄にはユーモアをまじえてこう書いている。
「この世に生の神がいる以上、死の神もいる筈です。私の枕辺に死の神が佇んだとき、医師及び身内各位は余りそれに抗うことなく、気持ちよく死の神の手に私を委ねて下さい。死の神も又、優しい神であることを信じます」


