- ホーム >
- 検査・治療法 >
- ホルモン療法 >
- ホルモン療法の副作用
からだに異常を感じたら早めに対処することが大切 QOLを高める前立腺がんホルモン療法の副作用対策あれこれ
骨粗鬆症
男性ホルモンの低下によって骨芽細胞の活性が鈍り、骨密度が低下することは意外と知られていません。
LH-RHアゴニスト、外科的去勢術またはMAB療法で起こりやすく、1年に1~9パーセント(平均3パーセント)骨密度が低下すると報告されています。個人差も大きく、半年から1年ほどで急激に骨密度が低下し、骨粗鬆症になる人もいます。
問題は、骨粗鬆症が進むと大腿骨頸部や椎体(背骨)を骨折しやすくなることです。ホルモン療法施行者は、無治療の人に比べて骨折率が高くなる(注3)という有名な報告もあります(図3)。骨折すると寝たきりになりやすく、肺炎等の合併症も増え、死亡率が高くなることが統計的に証明されています(図4)。
注3 米国の前立腺がん患者50613人を対象に、ホルモン療法施行群と未施行群の骨折率を比較。19.4パーセント対12.6パーセントでホルモン療法施行群の骨折率が有意に高かった(New England Journal of Medicine 2005 Jan)
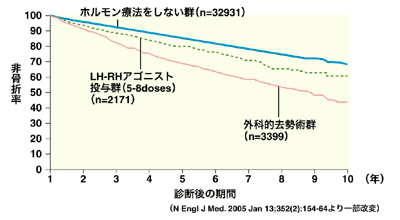
[図4 大腿骨頸部骨折者の生存率と期待生存率]
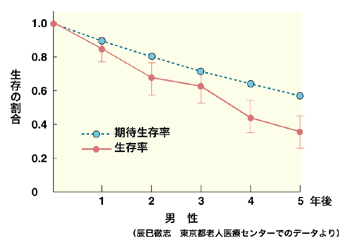
【対策】
骨粗鬆症を予防するには、カルシウムやビタミンD、ビタミンKを十分に補給しましょう(表)。
| 種類 | 薬剤名 | 作用と効果 |
|---|---|---|
| 骨の吸収を抑える | ビスフォスフォネート製剤(商品名ベネット、アクトネル、ゾメタなど) | 骨量を明らかに増加させ、骨折を予防する |
| カルシトニン製剤(商品名エルシトニン注20Sなど) | 骨量の減少を抑え、背中や腰の痛みを和らげる | |
| イソフラボン製剤(一般名イプリフラボン) | 骨量の減少を抑える | |
| ラロキシフェン(一般名塩酸ラロキシフェン) | 骨量を増加させ、骨折を予防する | |
| 骨の形成を助ける | ビタミンK2(一般名メナテトレノン) | 骨量の��少を抑え、骨の形成を助ける |
| 吸収と形成を調節する | ビタミンD3(一般名カルシトリオール、アルファカルシドール) | 腸からのカルシウムの吸収と骨の形成を助ける |
| カルシウム製剤(一般名乳酸カルシウム、リン酸水素カルシウムなど) | 食事からのカルシウムが十分摂れない場合、長期に服用すれば骨量減少の防止に |
ビスフォスフォネート製剤が有効です。当科でホルモン療法を行った人で、ベネット(一般名リセドロネート)の投与に同意を得て治療した群と無治療群を比較した結果、骨密度の低下を抑制できる可能性があることがわかりました(図5)。
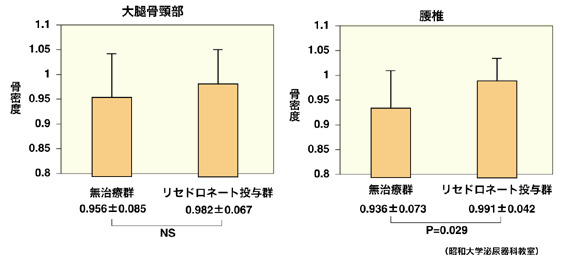
リセドロネートの経口薬ベネット、アクトネルは健康保険が利きます。1日1回起床時に180ccの水とともに飲み、服用後30分は横にならず、食事も避けるなどの注意が必要です。最近では、週1回の服用ですむ簡便な7日間製剤も出ています。
ゾメタ(一般名ゾレドロン酸)も骨粗鬆症に有効ですが、固形がんの骨転移の場合に保険適用となります。
フレアアップ
LH-RHアゴニスト単剤の投与開始直後、進行前立腺がんで骨痛、排尿障害、脊髄圧迫などの症状が一時的に増悪することがあります。これをフレアアップと呼んでいます。
LH-RHアゴニストは、男性ホルモン(テストステロン)を一時的に大量に分泌させ、結果として男性ホルモンを抑える薬剤です。そのため、投与直後の2、3日は一過的なテストステロンの上昇により、これらの症状が起こるのです。
【対策】
経口の抗アンドロゲン剤を先行投与して、分泌されたテストステロンが前立腺組織内で働かないようにすれば、これらの症状は予防できます。
女性化乳房・乳房痛
乳首の先が痛くなったり、乳房がふくらんだりする女性化乳房は、抗アンドロゲン剤単独使用の場合に多く、3~4割にみられます。MAB療法でも1割程度に認められたとの報告もあります。
抗アンドロゲン剤により、消費されずに上昇したテストステロンが、体内で女性ホルモンに変化するために起こります。
【対策】
抗アンドロゲン剤単独使用の場合は、LH-RHアゴニストを併用すると軽快する可能性があります。
海外では、乳腺に放射線を照射することで予防できた、という報告があります。
乳首の痛みは肌着などの刺激によって増加するので、救急絆創膏などを貼って刺激を避けるのも1つの方法です。
貧血
LH-RHアゴニスト、外科的去勢術、MAB療法では、貧血になるケースがあります。個人差が大きく、ヘモグロビン値が10~20パーセント低下する場合があります。
原因は、テストステロンの低下により赤血球を増やすホルモン、エリスロポエチンの活性が下がり、赤血球が減少するためです。
【対策】
理論的には、エリスロポエチンの投与が有効ですが、臨床的に問題になることは少なく、無治療で経過を見守ることがほとんどです。
血液検査で貧血の傾向がみられたら、鉄分を多く含む食品を十分に摂りましょう。
肝機能障害
薬剤の副作用として発生する肝機能障害は、抗アンドロゲン剤、とくにオダイン(一般名フルタミド)使用時に多く、10~15パーセントにみられます。
【対策】
オダインの服用開始後2~3カ月でまれに劇症肝炎となる例があるので、月1回定期的に採血して肝機能をチェックしましょう。GOT、GPT、LDHなどの数値に異常がみられたら、原因薬剤を中止します。
黄疸が出た場合は生命に関わるので、すぐに医師に連絡してください。
その他の副作用
テストステロンの低下は、前述の症状以外にも全身倦怠感、うつ、筋力の低下、体重増加、肥満、高脂血症、身体的・精神的活力の低下など、さまざまな体調の変化を引き起こす可能性があります。これらの症状はまとめてキャストレーション・シンドローム(Castration syndrome=去勢症候群)と呼ばれています。
患者さんが高齢で合併症を伴うことも多く、ホルモン療法の副作用であるか否かを判別するのは難しいものです。これらの持病がホルモン療法によって加速することもあります。
【対策】
適度な運動をしたり、身体をよく動かしたりして、身体機能を維持することが大切なポイントです。肥満や高脂血症、糖尿病は、心血管障害などの誘因にもなるので、食生活にも注意しましょう。
もともとメタボリックシンドロームの傾向がある人は、定期的に血圧を測ったり、心電図をとったりして、日ごろからこまめに体調をチェックすることを心がけてください。異常を感じたら、すぐに担当医やかかりつけ医に相談して、早めに対処することが大切です。
同じカテゴリーの最新記事
- がん治療中も後も、骨の健康が長生きの秘訣 ホルモン療法に合併する骨粗鬆症を軽視しない!
- ホルモン療法の副作用対策 抗がん薬とは異なる副作用が発現
- ホットフラッシュ、関節痛、倦怠感を抑えられるか?古くて新しい薬 ホルモン療法のつらい副作用を漢方で乗り切る
- ホットフラッシュ、関節痛、うつに対処し、治療を完遂する方法 ホルモン療法中のつらい副作用は、こうして乗り切る!
- 整形外科との協力で関節痛などの副作用を緩和している 副作用をコントロールして乳がん術後ホルモン療法を乗り切る
- 骨粗鬆症など、骨関連事象の対処法と生活上の留意点 乳がんホルモン療法の副作用と対策
- からだに異常を感じたら早めに対処することが大切 QOLを高める前立腺がんホルモン療法の副作用対策あれこれ
- ホルモン療法の大家、アラン・モニエさん特別インタビュー 患者さんのQOLを第一に考えた乳がんホルモン療法
- 前立腺がんホルモン療法後の副作用 ほてりに対するSSRIの効果


