知っておきたい免疫の基礎知識
免疫細胞のがん攻撃メカニズム
がんに対しては、この自然免疫と獲得免疫が2段構えで攻撃をする仕組みになっています。
まず、最初に異物(がん)を発見すると、自然免疫のマクロファージや樹状細胞などが働きます。片っ端から食べて分解します。しかし、食べる量には限界があり、満腹になると死にます。また、NK細胞などは全身をパトロールしていて、怪しいものを見つけ出すと、やっつけます。ただ、敵が強力だと自然免疫でも限界があり、その場合は、第2段階として、獲得免疫が発動します。
その際、重要な働きをするのが、先のマクロファージや樹状細胞です。実はこれらにはもう1つの働きがあり、「あいつが敵だ!」と獲得免疫のヘルパーT細胞に知らせるのです。これを専門的に「抗原提示」と呼んでいますが、とりわけこの能力に優れているのが、樹状細胞です。
すると、ヘルパーT細胞はキラーT細胞やB細胞に攻撃目標を知らせて攻撃命令を出します。この攻撃命令を受けたキラーT細胞やB細胞は、そのがんに照準を絞って攻撃にかかります。B細胞は抗体といって、液状のミサイルのような武器を発射します。これに対してキラーT細胞はがんに向かって飛んでいき、がんに取り付いて弾丸を放ち殺しにかかります。このキラーT細胞の殺傷力はとりわけ優れていて、NK細胞のそれよりも3倍以上の能力を持っているといわれています。
こうして1度攻撃したキラーT細胞などの獲得免疫は、これを覚えていて、再び同じがんが現れると、直ちに出動するという仕組みになっています。
こうしてみると、がん攻撃の主役は、獲得免疫のT細胞、なかんずくキラーT細胞であり、がん免疫療法ではいかにこのキラーT細胞を強力に誘導するかが大事であることがわかるでしょう。
本格的ながん免疫療法の時代へ
こうした観点からこれまでのがん免疫療法を見直してみると、かつての免疫療法がいかに的外れなものであったかが明らかです。
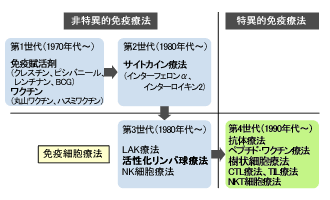
最初に登場したのは、1970年代、キノコから抽出された成分のクレスチンなどの免疫賦活剤です。第1世代の免疫療法です。現在も6種類が保険で認められていますが、抗がん剤などと併用する場合に限られています。
次いで、80年代に出てきたのが、第2世代、インターフェロンなどのサイトカイン(細胞分泌物質)療法です。インターフェロンは当時“夢の抗がん剤”と騒がれたものですが、今や腎臓がんや多発性骨髄腫など、一部のがんで使われているだけです。
さらに、第3世代として出現してきたのが、患者からリンパ球を採取し、体外で活性化して患者に戻すという、活性化自己リンパ球療法で、ここから免疫細胞療法の時代が始まることになります。ここまでは、非特異的免疫療法と呼ばれる療法で、とくにがんに照準を定めず「免疫全体を上げる」ものです。ですからがんに対してどのくらい攻撃しているかがわかりません。効果が上がらないのはこのためと思われます。
90年代に入って、前述のような免疫のメカニズムが解明され始め、ようやくがんに狙いを定めてがんだけを攻撃する方法が開発されました。「特異的免疫療法」と呼ばれる療法で、先の樹状細胞療法、CTL(キラーT細胞ともいう)療法、がん抗原ワクチン療法などがそうです。ここに至ってようやく、本格的ながん免疫療法の時代に入ったというわけです。
同じカテゴリーの最新記事
- 1人ひとりの遺伝子と免疫環境で治癒を目指す! がん免疫治療が進んでいる
- 自分の免疫細胞も活用してがんを攻撃 PRIME CAR-T細胞療法は固形がんに効く!
- 頭頸部がんに対する「光免疫療法」の第Ⅲ相試験開始 第Ⅱ相試験の好結果を受け、早期承認への期待高まる!
- 白血病に対する新しい薬物・免疫細胞療法 がん治療の画期的な治療法として注目を集めるCAR-T細胞療法
- 進行膵がんに対する TS-1+WT1ペプチドパルス樹状細胞ワクチン併用療法の医師主導治験開始
- がん患者を対象とした臨床試験で証明された、米ぬか多糖体(RBS)の免疫賦活作用
- 先進医療の結果次第で、大きく進展する可能性も! 進行・再発非小細胞肺がんに対するNKT細胞療法
- 現在3つのがん種で臨床試験を実施中 がんペプチドワクチン療法最前線
- 免疫力アップで照射部位から離れた病巣でもがんが縮小 アブスコパル効果が期待される免疫放射線療法


