化学療法と免疫療法の上手い組み合わせが相乗効果をもたらす 休眠療法と樹状細胞療法の出会いから生まれた化学免疫療法
低用量化学療法は血管新生、悪玉免疫細胞を抑える
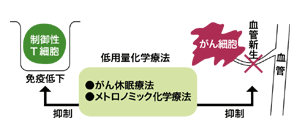
副作用を指標にして化学療法を行えば、使用する抗がん剤の量は人によって違ってくる。高橋さんの研究によれば、継続可能な抗がん剤の最大投与量は、患者ごとに異なっていて、3倍以上の開きがあるという。使用量がそんなに違っていても、効果に差はないのだ。
「樹状細胞療法は、その人のがんだけを標的にした究極のオーダーメイド治療と言えます。実は、がん休眠療法も、その人に合わせた量の抗がん剤を用いるという点で、まさにオーダーメイド治療なのです」
樹状細胞療法とがん休眠療法を組み合わせた化学免疫療法は、1人ひとりの患者に合わせた治療法といえそうだ。
また、がん休眠療法などの低用量化学療法には、がんの血管新生を抑えたり、がんを攻撃する免疫を抑えてしまう「悪玉免疫細胞(制御性T細胞)」の増殖を抑えたりする働きが認められている。こうした働きが、免疫化学療法では重要な役割を果たすことになる。血管新生ができるのを抑えられれば、がんは増殖できなくなるからだ。さらに、悪玉免疫細胞の数が減れば、それだけ免疫が上昇することになる。
つまり、低用量化学療法によって、免疫を上げることができるのだ。
繰り返していた転移が化学免疫療法で止まった

樹状細胞療法と低用量化学療法の組み合わせによって、よい結果が現れたケースがあるので紹介しよう。
患者は60歳代後半の女性。過去に頸部悪性リンパ腫、乳がんの既往歴があり、どちらも手術でよくなっていた。乳がんの手術から約10年が経過した2001年4月、定期健診で腹部の腫瘍を発見された。摘出手術を受け、平滑筋肉腫というがんであることが明らかになった。
03年10月に右の上腕を骨折。平滑筋肉腫の再発転移によるもので、摘出手術を受けた。04年9月には、平滑筋肉腫の腹膜への転移が発見され、これも手術。05年1月、肋骨、肝臓、肺に再発転移が発見された。4月に肋骨の腫瘍を摘出。6月の手術では、肝臓の一部を切除し、新たに転移が発見された左副腎を摘出した。
7月に某大学付属病院の医師から、樹状細胞療法を目的にセレンクリニックを紹介されて受診。そのときの状態は、介助付での、歩行、軽労働、座業ができるというレベルだ。
成分採血を行って樹状細胞の元となる単球を取り出し、それに患者自身のがん組織を溶かした液を加えて培養。細胞に患者のがんそのものの抗原を覚えさせるわけだ。このようにして培養した樹状細胞を、8月から2週間に1回のスケジュールで、計5回投与した。また、9月からは、樹状細胞療法と並行して、低用量の化学療法を某大学付属病院で開始している。
この樹状細胞と低用量抗がん剤治療の併用によって、肺の転移巣の進行が止まり、数カ月に1回のペースで出現していた平滑筋肉腫の新規の転移病変が現れなくなった。
また、10月からはPSが0に改善。最初は1人で来院するのが困難な状況だったが、1人で外出してもまったく問題がない状態にまで回復していた。
樹状細胞による副作用は、とくに認められなかった。樹状細胞が終了した後も、低用量の化学療法は継続されていて、平滑筋肉腫の進行や転移は良好にコントロールされている。継続されている低用量化学療法に加え、樹状細胞療法のワクチン機能によって、現在でも標的を記憶したリンパ球が体内を巡って再発を防ぐ働きをしていると考えられる。
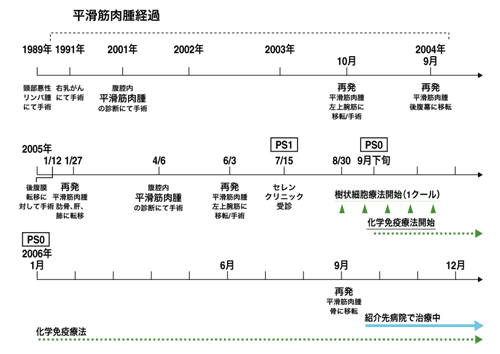
今必要とされているのはセカンドがん治療
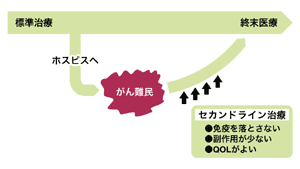
ここに紹介した免疫化学療法のような治療法が、現在の日本のがん医療にはとくに必要なのだと高橋さんは力説する。
「数年前までは標準治療を受けられない人を『がん難民』と呼びましたが、最近では、標準治療で治すことができないことから、もう治療法はないと見放された患者さんが『がん難民』になってきています。
厚生労働省の大号令で標準治療が推進されてきましたが、その標準治療でよくならなかった患者さんには、早々と、もう治療法は残されていないと病院で宣告がくだされます。まだ標準治療からはずれただけなのに、残されているのは緩和医療だけということになってしまうのです。こうした新しいがん難民を救うことが大切で、そこで必要になる治療を、私は標準治療の次の治療という意味で『セカンドがん治療』と呼んでいます」
標準治療と終末医療の間を埋めるのが、高橋さんの提唱するセカンドがん治療だ。標準治療をはずれたからといって、多くの患者さんは全面的な緩和医療を必要とはしていない。それどころか、普通に生活し、場合によっては仕事もしているような状態で、もう治療法はないと宣告されている。標準治療はないとしても、そうした人たちが必要としているのは、全面的な緩和医療ではなく、まさにセカンドがん治療なのである。
「セカンドがん治療で大切なのは、体の免疫を落とさない低侵襲の治療であること。樹状細胞とがん休眠療法のような低用量の化学療法は、セカンドがん治療の条件にかなっているといえます」
高橋さんのいうように、樹状細胞療法と低用量化学療法を併用する免疫化学療法は、現代のがん医療の欠落部分を埋める新しい治療法となる可能性を持っている。今後の研究が期待されるところだ。
同じカテゴリーの最新記事
- 1人ひとりの遺伝子と免疫環境で治癒を目指す! がん免疫治療が進んでいる
- 自分の免疫細胞も活用してがんを攻撃 PRIME CAR-T細胞療法は固形がんに効く!
- 頭頸部がんに対する「光免疫療法」の第Ⅲ相試験開始 第Ⅱ相試験の好結果を受け、早期承認への期待高まる!
- 白血病に対する新しい薬物・免疫細胞療法 がん治療の画期的な治療法として注目を集めるCAR-T細胞療法
- 進行膵がんに対する TS-1+WT1ペプチドパルス樹状細胞ワクチン併用療法の医師主導治験開始
- がん患者を対象とした臨床試験で証明された、米ぬか多糖体(RBS)の免疫賦活作用
- 先進医療の結果次第で、大きく進展する可能性も! 進行・再発非小細胞肺がんに対するNKT細胞療法
- 現在3つのがん種で臨床試験を実施中 がんペプチドワクチン療法最前線
- 免疫力アップで照射部位から離れた病巣でもがんが縮小 アブスコパル効果が期待される免疫放射線療法


