実用化樹状細胞療法第1号として認められた理由 科学的な研究から甦った古典的な免疫「BCG-CWS療法」
BCG-CWSががんを攻撃する道程
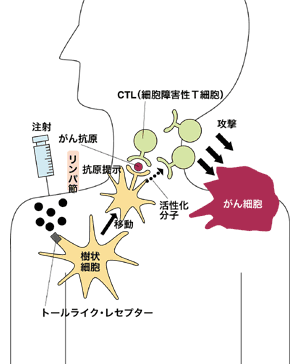
BCG-CWS。結核菌の細胞骨格成分である。膀胱がんで標準治療として使われているBCGとは違う。
研究の一翼を担った府立成人病センター研究所の赤澤隆さんが説明する。
「BCGは牛結核菌を弱毒化したもので、生の菌そのものですが、BCG-CWSはその菌から抽出・精製した成分です。主成分はミコール酸アラビノガラクタン・ペプチドグリカンという特殊な構造をしたもの。結核菌をがんに用いる研究からさまざまなものが開発されていますが、BCG-CWSもその1つです」
研究の中心になったのは、現北大大学院教授の瀬谷司さんだが、BCG-CWSががんに効果を発揮するメカニズムを調べ、その全容をほぼ解明したのだ。
「その結果、BCG-CWSは、リンパ球に直接働くのではなく、人間が本来持っている自然免疫を刺激、それがリンパ球のT細胞を動員してがんを攻撃することがわかったんです」(赤澤さん)
もう少し詳しくいうと、BCG-CWSワクチンは皮膚に接種する。すると、皮内には自然免疫の1つである樹状細胞(正しくはランゲルハンス細胞)が存在し、それがBCG-CWSに出会うと、それを認識し活性化される。樹状細胞の表面にはトールライク・レセプター(トール様受容体)と呼ばれるBCG-CWSの識別装置を持っていることも解明されている。すると、活性化された樹状細胞はリンパ節に移動し、そこにいるT細胞を活性化してがんを攻撃するというわけだ。
つまり、樹状細胞は普段は自陣で守っているが、刺激を受けると、ゴール(がん)前に出て「そこのがんを殺せ!」とフォワードのT細胞に司令を発し、キラーパスを送るようなものである。フォワードのT細胞はそのキラーパスを受けてがんめがけてシュートを放つのである。
ただし、最後の攻撃役は、実は、T細胞以外にも、NK細胞、NKT細胞なども考えられ、この部分はまだ明確には分かっていないという。動物実験では、がん抗原とBCG-CWSとを一緒にしてマウスに投与すると、細胞障害性T細胞(CTL=キラーT細胞)が誘導されることが分かっているので、T細胞と記したわけだ。
そんなわけで、2004年、カナダのモントリオールで開催された国際免疫学会で、このBCG-CWS療法は実用化樹状細胞療法第1号として認知されたそうだ。
本格的な臨床試験が開始された
ざらではなく、本物かもしれないという感触が出てきた。そこで、成人病センターでは、本格的な臨床試験をしてそれを確かめようと考えた。その中心になったのは外科部長の児玉憲さんらの外科グループである。
「難治がんの肺がんは、5年生存率が低く、15パーセント程度です。手術で取り切れたと思っても、再発し死亡するからです。この生存率を5パーセント引き上げるのは並大抵ではない。そこで、手術で取り切れた患者さんをはじめ、抗がん剤や放射線の治療が良好だったがこれ以上はそうした治療ができない患者さんに対して、再発を防止し、さらには再発がなく、生存期間を延ばすことを目的に、2002年から臨床試験を始めました」
臨床試験は、最初は1週間間隔で4回、BCG-CWSを100~200マイクログラムずつ患者さんの肩の部分に皮内注射する。すると、免疫応答がうまく活性化されると、血中にインターフェロンγという物質が増加してくる。4回終了した時点でこの物質が出ているかどうかを測定する。インターフェロンγが出ていなければ、効果が期待されないので、そこでこの治療を中止し、出ていれば、以後は1カ月ごとにこの治療を2~3年間続けるというものだ。
肺がん患者の生存期間が延長
「結果はまだ出ていないので言えませんが、そこそこの感触は得ています」(児玉さん)
感触は、ケース・コントロール・スタディという臨床研究から得ているようだ。症例対照研究と呼ばれる研究で、完全な比較試験ではないが、過去にさかのぼって、年齢や性別など、患者の背景を揃えて、比較する研究だ。肺がんで、術後にBCG-CWSを投与した群としなかった群、両群71例ずつを比較検討した結果、BCG-CWS投与群のほうが生存期間が延長(術後5年経った時点で10パーセント弱の生存率の上積み)されていたというのだ。
「ただし、有意差は出なかったんです。ということは、BCG-CWS療法はそう強力な治療ではないということでしょう。もっとも、BCG-CWS療法といっても、がんに特異的な抗原を与えているわけではないですからね。そこがこの治療の弱みです。だから、レントゲンに写るようながんに対してこの治療が効くというのは、まやかしだと思いますね。
なぜなら、レントゲンに写るほどのがんになると、10の7乗から9乗個ものがん細胞がいる。体中のリンパ球をすべて集めても、リンパ球の数はそんなにはならない。数だけでいってもがんに対抗できないからです」(児玉さん)
微小ながんに効果 大きながんは苦手
では、このBCG-CWS療法はどんな患者さんに効果が出ているのか、成人病センターでの代表的な事例を紹介してみよう。
非小細胞がんの腺がんの70代男性。病期は2期。肺門近くのリンパ節に転移があったが、手術をした。しかし、その甲斐もなく、7カ月後に今度は首のリンパ節と肺の両方に転移。肺には小さながんが10個ほど見られた。多発転移だ。
児玉さんらが考えたのは、まず、首の転移については50グレイの放射線をかけて縮小させることだ。これは見事に当たり、1~2カ月後に完全に消失した。
もう1つの肺転移に関しては、BCG-CWS療法を行うことにし、8コース行った。これまたずばり当たって、肺の影はすっかり消えてしまった。そして10年後の現在も元気に生存中だという。
しかし、すべてが万歳ではなかった。数年前に反対側の肺に別のがんができた。それもまたもや腺がん。重複がんである。新しくできたがんは直径3センチ大と大きかったので、BCG-CWS療法では太刀打ちできないと考え、すでに承認になっていた分子標的薬のイレッサ(一般名ゲフィチニブ)を用いた。すると、またまた劇的な効果が出て、がんが消失した。イレッサが劇的に効いた患者さんでも、1年くらいすると耐性が出て効かなくなるケースが多い。イレッサの治療で2年以上効いている例はほとんどないが、彼はその稀有な例となった。
むろん、これは著しく効果を発揮した例で、効いていない例もたくさんある。しかし、この例からもわかるように、どうやらこのBCG-CWS療法は大きながんは苦手で、目に見えるか見えないか程度のがんなら、ある程度の効果は期待できるようだ。
そのあたりを踏まえて児玉さんはこう期待をかける。
「BCG-CWS療法だけでは効力はそれほどではないですが、このBCG-CWSと阪大のWT1ワクチンを組み合わせると、理論的には格段に効果を発揮する。強力にCTLを誘導できる可能性があるんです」 うれしいことに、この組み合わせによる治療の研究は、すでに阪大で始まっている。
同じカテゴリーの最新記事
- 1人ひとりの遺伝子と免疫環境で治癒を目指す! がん免疫治療が進んでいる
- 自分の免疫細胞も活用してがんを攻撃 PRIME CAR-T細胞療法は固形がんに効く!
- 頭頸部がんに対する「光免疫療法」の第Ⅲ相試験開始 第Ⅱ相試験の好結果を受け、早期承認への期待高まる!
- 白血病に対する新しい薬物・免疫細胞療法 がん治療の画期的な治療法として注目を集めるCAR-T細胞療法
- 進行膵がんに対する TS-1+WT1ペプチドパルス樹状細胞ワクチン併用療法の医師主導治験開始
- がん患者を対象とした臨床試験で証明された、米ぬか多糖体(RBS)の免疫賦活作用
- 先進医療の結果次第で、大きく進展する可能性も! 進行・再発非小細胞肺がんに対するNKT細胞療法
- 現在3つのがん種で臨床試験を実施中 がんペプチドワクチン療法最前線
- 免疫力アップで照射部位から離れた病巣でもがんが縮小 アブスコパル効果が期待される免疫放射線療法


