再発防止や難治がんに対する研究も広がっている ようやく脚光を浴び始めた「がんペプチドワクチン」、その本当の効果
免疫療法の評価が高まってきた
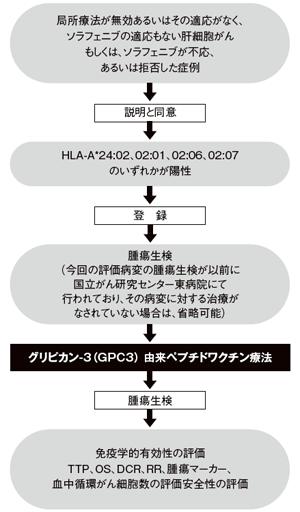
そんながんペプチドワクチン療法だが、つい最近まで、日本ではあまり評価の高い治療法ではなかったといえるだろう。
効果が明確に確認されていないから、もちろん保険診療は受けられないし、唯一、治療を受ける機会である臨床試験も、標準治療が効かなくなった進行再発がんの患者さんでないと参加できないなど、枠は狭かった。
2004年、アメリカのがん免疫療法の第1人者のローゼンバーグが、「がんワクチンに効きめなし」という論文を発表した影響も大きかったという。欧米の研究者はがんワクチン研究からかなり撤退し、日本でも「がんワクチンには期待できない」という空気が広がった。
しかし、状況は変わってきているようだ。そもそも、分子生物学の発達によって、細胞内のさまざまな物質の働きが急速に解明されつつある。加えて、医師主導試験という日本の独特の試験スタイルでコツコツと効果を検証してきた結果が、少しずつ積み上がってきたという。
日本では保険承認をめざす厳密な試験が、がんペプチドワクチンでは組みにくかったため、08年に厚労省が「先進医療開発特区」に認定した3つのグループを中心に、医師主導試験が行われてきた。その中から、がんが消えた、小さくなったなどの報告が増えてきている。結果、「私が現職についた5年半前、がんペプチドワクチンに製薬会社は見向いてくれませんでした。けれども、ここ2、3年、製薬会社が研究に関心をもち、共同研究に参加する機会も増えました。時代が変わってきているのを感じます」
早期がんを視野に入れた研究を
次に必要なのは、「がんが進行していない、元気な患者さんにがんペプチド療法を行い、効果を検証すること」と中面さんはいう。
「患者さんの免疫力をもとにした治療ですから、元気な患者さんで大きな効果が得られる可能性は高い。今までは治療法のなくなった進行再発がんの患者さんにしか治療が行えず、1度がんが大きくなっても、あとから小さくなるといった���も、免疫療法ではありえるのですが、ちょっとでもがんが大きくなったら、治療を中止することがきびしく求められました。
けれども、09年にはアメリカの食品医薬品局(FDA)が、より元気な患者さんを対象に試験を組み直すよう指示を出し、また、今年3月、メラノーマ(皮膚がんの1種)の治療薬として、アメリカで承認されたイピリムマブに関しても、FDAは『1度がんが大きくなっても、再び小さくなる可能性があるので、治療を続行してよい』という考え方を出しました。イピリムマブはキラーT細胞を抑制している分子を抑える薬です。免疫療法の開発においては大きな出来事だと思います」
薬ができて承認されれば、次々と続く可能性も
こうした大きな動きを受けて、がんペプチドワクチンの研究も別な広がりを見せている。これから増えてくると思われる臨床試験は、抗がん剤との併用療法だ。すでに、膵がんの抗がん剤、ジェムザール(*)との併用に関する第2相、第3相試験や、胆道がんに対してジェムザールと併用する第2相試験などが進められている。
今後、こうした研究の成果を広く使える薬にし、保険承認につなげていくことが必要と中面さんは語る。
「そうでなければ、治療法がなくて困っているたくさんの患者さんたちにメリットがありません。ですから、従来通りの医師主導試験でさらに効果を積み上げながら、製薬会社とも共同研究を進め、保険承認を視野に入れた臨床試験をさらに行って、有効性を証明する必要があります」
薬の開発そのものも、がんペプチドワクチンのベンチャー企業であるオンコセラピー・サイエンス社など、数社が進めているという。
「どれか1つが薬になると、あとはバタバタと続く可能性があると思います。がんペプチドワクチンは副作用が少なく、従来の治療が打ち切られてしまった患者さんにも最後まで無理なく使ってもらえる可能性があります。私たちは今後も『生存期間が本当に延びるか』というところで勝負していく必要があると思います」
*ジェムザール=一般名ゲムシタビン
がんペプチドワクチン 問い合わせ先
事務局 国立がん研究センター東病院臨床開発センター がん治療開発部
機能再生室長 中面哲也
〒277-8577 柏市柏の葉6-5-1
TEL: 04-7131-5490 (直通) / FAX: 04-7133-6606
同じカテゴリーの最新記事
- 1人ひとりの遺伝子と免疫環境で治癒を目指す! がん免疫治療が進んでいる
- 自分の免疫細胞も活用してがんを攻撃 PRIME CAR-T細胞療法は固形がんに効く!
- 頭頸部がんに対する「光免疫療法」の第Ⅲ相試験開始 第Ⅱ相試験の好結果を受け、早期承認への期待高まる!
- 白血病に対する新しい薬物・免疫細胞療法 がん治療の画期的な治療法として注目を集めるCAR-T細胞療法
- 進行膵がんに対する TS-1+WT1ペプチドパルス樹状細胞ワクチン併用療法の医師主導治験開始
- がん患者を対象とした臨床試験で証明された、米ぬか多糖体(RBS)の免疫賦活作用
- 先進医療の結果次第で、大きく進展する可能性も! 進行・再発非小細胞肺がんに対するNKT細胞療法
- 現在3つのがん種で臨床試験を実施中 がんペプチドワクチン療法最前線
- 免疫力アップで照射部位から離れた病巣でもがんが縮小 アブスコパル効果が期待される免疫放射線療法


