玉石混交の免疫療法の中からホンモノを見つけるコツ どの治療法が勝れているか、どのクリニックがよいか
注目を集めるがん狙い撃ち
こうした活性化リンパ球療法の泣きどころは、培養したリンパ球ががん細胞を狙った治療ではなく、がん細胞以外のさまざまな外敵(異物)にも働きかける非特異的な治療法であることだ。培養したリンパ球にがんを狙って叩くCTLがどの程度含まれているかがはっきりしていない。そのことが治療法の限界にもつながっているわけだ。
これに対して、この限界を打ち破ろうと新たな免疫療法として期待されるのが、体内でがんを叩くCTLを活性化する各種ワクチン療法だ。なかでもとくに今後に期待を持たれているのが樹状細胞と呼ばれる細胞を体外で活性化して体内に戻す樹状細胞療法だ。
この新しい治療法を積極的に導入する免疫ベンチャーも現れている。東京女子医科大学附属病院の外科医だった谷川啓司さんが01年8月に設立したジェー・ビー・セラピュティクス(JBT)という免疫事業を推進する会社もその1つ。その中核の医療機関であるビオセラクリニックも開院し、谷川さんはこの院長も兼ね2足のわらじを履いている。これまで同クリニックで免疫細胞療法を受けた患者数は900名あまり。クリニックの治療方針について院長の谷川さんはこう語る。
「樹状細胞療法というのはがん情報を記憶させた樹状細胞を体内に戻すことで、がん攻撃の主力となるCTLに情報を伝えてCTLにがんを攻撃させようという治療です。しかし、実際には情報が伝えられてもCTLが活性化された状態に至っていないことも考えられる。そこでより確実にがん細胞を叩くために2つの治療法を併用しています。樹状細胞療法で活性化自己リンパ球の効果を少しでも高められればと考えているのです」
樹状細胞療法は半分以下
同クリニックで手がけている樹状細胞療法は3タイプに区分される。1つは患者のがん組織を徹底的に破壊して抽出したがん抗原を樹状細胞に食べさせたうえで体内に戻す方法、2つ目はすでに製品化されている人工のがん抗原ペプチドを体内に戻す方法、そして3つ目は樹状細胞を直接患部に注入する方法だ。それぞれどのように使い分けられているのか。
「残念ながら1つ目のがん組織を使う方法はすべての患者さんに適用できるわけではありません。これから手術を行う患者さんの場合は、手術で摘出した新鮮ながん組織を入手してもらい、がん組織を用いた樹状細胞療法をやってみてはどうか、それで効果がなければ今度は人工のがん抗原ペプチドが適合するかどうか調べて見ましょうと話してい��す。また患部に樹状細胞を直接注入する方法は効果が高い反面、がん組織が融解して全身に広がる危険性があるので、体の表面近くに腫瘍がある場合に適応が限られる。そうしてみると樹状細胞療法が可能な患者さんは全体の半数以下というのが実情です」(谷川さん)
当然ながら、樹状細胞療法が受けられない場合は、患者の選択肢は従来と同じ活性化リンパ球療法単独の治療ということになる。ちなみに1回の投与に要する費用は樹状細胞療法と活性自己リンパ球療法を併用した場合は約35万円で、1クール4回の投与が標準的で、その費用は140万円だ。
樹状細胞療法単独の治療
もう1つ、樹状細胞療法の臨床研究で高い評価を得ているのが東京大学医科学研究所附属病院先端医療部だ。そこで、その先端医療部教授の山下直秀さんらが積み上げた成果を臨床に活用しようと04年6月に設立されたのが免疫ベンチャー、テラとその拠点医療機関であるセレンクリニックだ。まだ産声を上げたばかりだ。
同クリニックの治療メニューは3種類の樹状細胞療法と活性化自己リンパ球療法とビオセラクリニックに共通する。しかし樹状細胞療法の位置づけがまったく異なり、基本的にはこの治療単独による治療が主体になっている。
その理由はどこにあるか。1つは、前述の山下さんらの研究成果が背景にある。山下さんらはこの治療法で10例の悪性黒色腫(メラノーマ)で2例を腫瘍の縮小・消失、1例を進行停止に、6例の甲状腺がんで2例を進行停止に導いた実績をあげている。腫瘍が縮小・消失したケースでは、腫瘍血管の内皮細胞が破壊されているのが確認されているともいう。
それにこの免疫細胞療法の分野に後発で乗り出す以上、先発組みを凌駕する効果のある治療を掲げて実績を上げる必要がある。そこでテラ代表取締役の矢崎雄一郎さんらは、世界中の免疫療法の現況を調べた。その結果、樹状細胞療法だけで十分とはいえないが、活性化リンパ球療法にさほどの価値を見出せなかったという。それが樹状細胞療法を軸にしたクリニックの開設に結びついたわけだ。
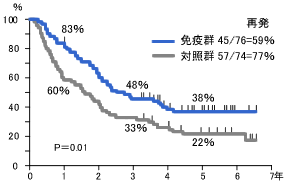
樹状細胞療法の威力について矢崎さんはこう語る。
「樹状細胞療法は進行中のがんには効果が現れにくい。しかしすでに進行し巨大化した腫瘍には、組織をつぶして消失に導く働きがあることがわかっています。果物が腐っていく状況を想像すると分かりやすいと思いますが、がん細胞を内側から腐敗させていくのです。活性化リンパ球療法にはこのような働きがありません」
もっとも、樹状細胞の培養はリンパ球の培養に比べて技術的に格段に難しい。が、矢崎さんは「樹状細胞の培養に関してはどこにも負けない」と豪語する。どうやら東大医科研教授の高橋恒夫さんのグループで培った技術力の高さに裏打ちされているようだ。
ちなみに治療費用はがん組織を用いた場合、1クール5回投与で総額140万円。人工がん抗原を用いた場合はその実費が必要になる。取材を行なった05年11月時点でのセレンクリニックの患者数は10名程度だ。
もっとも他の標準治療と連動することで、より有効に免疫細胞療法の効果を活用する方向性は他のクリニックと変わらない。
「大学病院など、大規模な医療機関との提携にも積極的に取り組んでおり、一部の病院では抗がん剤との併用の仕方や治療タイミングなどの側面で、治療プランづくりにも参画しています」(矢崎さん)。
樹状細胞療法は実用化されてまだ数年という研究段階の治療法だ。今後に期待が持てるとはいえ、患者側から見れば適応範囲の拡大など、クリアしてもらいたい課題が残されているのも事実だろう。
患者のがん組織からワクチン
樹状細胞療法とは別に、がんを狙って攻撃する治療法として注目を集めているのががん抗原を用いたワクチン療法だ。もっともすでに何種類もの人工がん抗原を用いたワクチン療法が行われているが、1部を除けばほとんど成果はあがっていないのが実情だ。そんな中で異彩を放っているのが、理化学研究所で細胞培養の研究に取り組み続けてきた大野忠夫さんが中心になって設立したセルメディシンの自家がんワクチン療法だ。この治療法はその名称どおり、患者のがん組織をワクチンとして用いるが、新鮮なものではなく、ホルマリン漬けになって固定されたがん組織などを使えるようにしたところがミソだ。
「手術後保存されている患者さんの固定されたがん組織を原料にします。これを細かく砕き、免疫刺激剤を混ぜてワクチンを作り、体内に戻します。もちろんその時点でがん細胞は死んでいる。しかし、その死んだがん細胞に反応して体内では、がん細胞を攻撃するCTLやNK細胞が強力に活性化されるのです。これまで誰も死んだがん細胞に免疫が反応するとは考えなかった。その意味ではコロンブスの卵といっていいでしょう。ただし、患者さん個人にしか使えないので、オーダーメードの薬剤ということになります」
この大野さんの言葉からもわかるように、この治療法の適応は手術を行ったがん患者に限られており、進行がんの治療よりも再発予防、転移防止に主眼が置かれている。実際の治療では、まず同じワクチン接種による免疫反応テストが行なわれる。その結果が陽性であれば本格的な治療に移行する。ワクチン接種は3回にわたって行なわれ、費用は総額で140~150万円。もっとも免疫反応テストの判断基準はあいまいで、接種後にできる赤斑が1センチ以下の陰性の場合でも、体内では免疫が活性化していることもあるという。
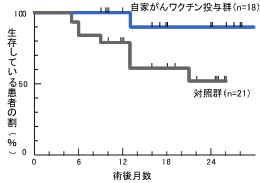
効果はどのようなものか。大野さんは04年に論文発表された中国の中山大学附属病院での臨床研究結果を指し示しながらこう語る。
「この研究は39人の平均直径5.3センチの大きな腫瘍を手術で切除した肝がん患者を対象にしたもので、そのうち18名に手術後にワクチンが投与されています。2年後の対照群の無再発率が30パーセント強だったのに対して、ワクチン投与群のそれは80パーセント近くに達しており、明確に有意差が生じています」
中山大学附属病院の臨床研究は、精度の高さに定評があると大野さんはいうが、中国での研究発表は今ひとつ信頼性にかける面があり、国際的には評価が低い。そこで現在は、肝がんに続いて日本国内で、筑波大学脳神経外科などと共同で、脳腫瘍の中でももっとも予後が悪いグリオブラストーマ(膠芽腫)の臨床研究が行われている。すでに05年1月時点で11例中完全寛解、部分寛解が1例ずつ出ている。
過大評価のクリニックは要注意
ここまで見てきたように、ひとことで免疫細胞療法といっても、その種類は多様で適応範囲や効果も違っている。実際にこの治療法を利用する場合、そのなかで、どうクリニックを選択すればいいのだろうか。
ここでとりあげた免疫ベンチャー、クリニックは、いずれもがん治療に積極的で技術力に対して一定以上の評価が与えられている。しかし現実には確たる技術力を持たず、ただ時流に乗ってこの治療を手がけるクリニックが少なくないのも事実だ。いわば玉石混交の状態にあるのが現在の免疫細胞療法の現状だ。そんななかで治療を委ねるクリニックを的確に選択するにはそれなりの視点が必要だ。
「設立以来、どうすれば患者さんのためになるかということを考え続けています。具体的にはどう安全管理を徹底し、治療の有効性をどう高めていくか。そのためには施設の充実強化、研究ネットワークの広がりが欠かせません」と語るのは、前述のメディネットの代表取締役の木村さんである。この言葉はそのままクリニックの選別にも当てはまる。治療実績とともに背景となる提携医療機関の有無、その研究成果についても慎重な吟味が必要だろう。さらに言えばそうした高品質の医療を維持するには一定の資金も必要だ。その点で言えば、治療費があまりに低価である場合も要注意と考えるべきだろう。そしてさらに木村さんはこんな疑問をも投げかける。
「免疫細胞療法を行なっているクリニックの中にはウチがいちばんというところが多すぎるような気がします。まだ研究段階の域を脱していない先端医療分野だから、実績は控えめに考えるべきでしょう。どうしてそんなことがいえるのか不思議でなりません」
患者のニーズに根ざしたホンモノの医療を提供してくれるクリニックを見定めるためには、この言葉も有力な武器になるのではないだろうか。
同じカテゴリーの最新記事
- 1人ひとりの遺伝子と免疫環境で治癒を目指す! がん免疫治療が進んでいる
- 自分の免疫細胞も活用してがんを攻撃 PRIME CAR-T細胞療法は固形がんに効く!
- 頭頸部がんに対する「光免疫療法」の第Ⅲ相試験開始 第Ⅱ相試験の好結果を受け、早期承認への期待高まる!
- 白血病に対する新しい薬物・免疫細胞療法 がん治療の画期的な治療法として注目を集めるCAR-T細胞療法
- 進行膵がんに対する TS-1+WT1ペプチドパルス樹状細胞ワクチン併用療法の医師主導治験開始
- がん患者を対象とした臨床試験で証明された、米ぬか多糖体(RBS)の免疫賦活作用
- 先進医療の結果次第で、大きく進展する可能性も! 進行・再発非小細胞肺がんに対するNKT細胞療法
- 現在3つのがん種で臨床試験を実施中 がんペプチドワクチン療法最前線
- 免疫力アップで照射部位から離れた病巣でもがんが縮小 アブスコパル効果が期待される免疫放射線療法


