がん細胞を殺す能力はNK細胞の3倍以上 進行・再発肺がんで効果を上げつつあるNKT細胞療法
31カ月間生存中
培養した細胞数10億個の点滴を受けた3人のうち2人は、以下のような経過である。
Aさん(66歳 女性)は、非小細胞肺がんの腺がんで手術を受けた。術後、肺と胸膜に再発した。そこで、胸水を抜く処置として胸膜癒着術を行った。そのあとで、臨床試験を受けた。臨床試験後の14カ月目に骨転移を起こし、放射線治療を行った。経過観察中、肺内の再発腫瘍は試験後30カ月までまったく変化なく、臨床試験後36カ月間生存中。通常の治療では考えられないような良好な経過をたどっている。
Bさん(74歳 女性)は、原発性の非小細胞がんの腺がんだった。肺、胸腔、骨に転移してステージ4と診断され、胸膜癒着術後に化学療法を受けた。その後、臨床試験を希望し、受けた。臨床試験後、良好なQOLを確保していた。しかし、14カ月目、肺がんとは関係のない膵炎が原因で残念ながら亡くなった。
転移移抑制、再発防止に適している
A、Bさんを含む9人の臨床試験(第1相)はすでに終了。臨床試験は、次の第2相試験に進んでいる。
「04年春からは、同大学院助教授の本橋新一郎さんがNKT治療グループのリーダーとしてNKT細胞療法の治療効果を判定するための第2相の臨床試験を始めました。この臨床試験も第1相と同じく、肺がんが進行して手術ができないか、術後に再発した患者さんを対象にしています。すでに10人に実施しています。目標は20人です。同時に、05年5月からは、原発性肺がんで根治手術を受けた患者さんを対象に、術後の再発防止を目的にした臨床試験にも取り組んでいます。この臨床試験も20人が目標です。現在、この臨床試験を3人に行っています」(中山さん)
中山さんは、NKT細胞療法による肺がん切除後の再発防止に大きな期待を寄せている。前述したNKT細胞の2つの作用を最も発揮できると考えているからだ。

「手術で切除したあとも、小さな微小がんが残存している可能性があります。NKT細胞療法は、小さながんを抑え込んで増やさないようにする転移の抑制、再発の防止に最も適した治療法ではないかと考えています」と中山さんは語る。
臨床試験問い合わせ先:
電話 043-226-2966
期待できる放射線との併用
また、NKT細胞は放射線に強く、照射されてもその影響を受けない細胞である。そのため、放射線治療との併用が期待できる。前述したBさんは、NKT細胞療法の臨床試験後、骨転移の放射線治療を受けているが、照射による障害はまったく受けていないと考えられる。「現在の標準治療の放射線治療に合わせて、NKT細胞療法を併用することで、治療成績の向上が期待できます」と中山さん。
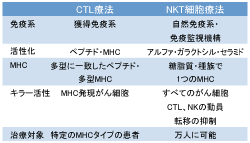
さらに、他の免疫療法との併用も期待できそうだ。例えば、CTL療法との併用が考えられる。CTL療法は、注射でがん抗原を身体の中に注入して、CTLを増やしてがんを効率よく攻撃する免疫療法だ。治療した患者のうち10~20パーセントに有効だという。この療法がピタッと当てはまるとがんが劇的に小さくなることもある。NKT療法とCTL療法の両方を用いることで、治療の相乗効果やお互いの弱点をおぎなえる可能性がある。
試験管内でNKT細胞を人工的に作り出して、それを患者に投与する方法も考えられている。この方法ならNKT細胞がもともと少なくて、点滴によるNKT細胞免疫療法ではNKT細胞を増やすことが難しい患者にも治療効果が期待できそうである。2つの療法を併用すれば、NKT細胞免疫療法の治療効果を向上させられるかも知れない。
現在、アルファ・ガラクトシル・セラミドという糖脂質を用いたNKT細胞療法は、千葉大学を含めて、アメリカのロックフェラー大学、オーストラリアのクイーンズランド病院の世界3カ所で行われている。ロックフェラー大学では悪性リンパ腫などの血液がん、クイーンズランド病院では大腸がんや胃がんを対象に臨床試験を実施中だ。
「科学的な根拠を持ち、きちんとした方法を考えて、少しずつ進めています。治療法の基本形が決まれば、世界中に普及すると思います」と中山さんは慎重だが、NKT細胞療法への確かな手ごたえと自信が伝わってきた。
同じカテゴリーの最新記事
- 1人ひとりの遺伝子と免疫環境で治癒を目指す! がん免疫治療が進んでいる
- 自分の免疫細胞も活用してがんを攻撃 PRIME CAR-T細胞療法は固形がんに効く!
- 頭頸部がんに対する「光免疫療法」の第Ⅲ相試験開始 第Ⅱ相試験の好結果を受け、早期承認への期待高まる!
- 白血病に対する新しい薬物・免疫細胞療法 がん治療の画期的な治療法として注目を集めるCAR-T細胞療法
- 進行膵がんに対する TS-1+WT1ペプチドパルス樹状細胞ワクチン併用療法の医師主導治験開始
- がん患者を対象とした臨床試験で証明された、米ぬか多糖体(RBS)の免疫賦活作用
- 先進医療の結果次第で、大きく進展する可能性も! 進行・再発非小細胞肺がんに対するNKT細胞療法
- 現在3つのがん種で臨床試験を実施中 がんペプチドワクチン療法最前線
- 免疫力アップで照射部位から離れた病巣でもがんが縮小 アブスコパル効果が期待される免疫放射線療法


