免疫の最先端治療、第4のリンパ球、NKT細胞免疫療法 NK細胞とT細胞の両方の機能を持つ細胞の力でがん細胞を攻撃
細胞を取り出し、処理して戻すことで効果が飛躍的に高まる
NKT細胞免疫療法による治療効果は、すでにマウスを用いた動物実験で実証されている。
「脾臓にがん細胞を移植したマウスは肝臓へ転移するのが普通ですが、糖脂質を投与したマウスとNKT細胞のみを持つマウスは、肝臓への転移が見られませんでした。しかし、NKT細胞のないマウスは、肝臓への転移を防ぐことができなかったのです。
糖脂質の投与でNKT細胞が目覚め、免疫力が強化され、がんの転移が抑えられたようです」(中山さん)
また、すでに肝臓へ転移している場合は、たとえ糖脂質を投与してもがんは消失しないが、この糖脂質を*樹状細胞と呼ばれる細胞に取りこませ、それをマウスに戻したところ、がんは見事に消失したのである。
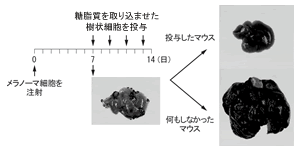
にがんができる。この状態からαガラクトシルセラミドを取り込ませた樹状
細胞を投与すると、1週間後には右上の写真のように完全にがんを退治
できることが確認された
[NKT細胞による抗腫瘍効果のメカニズム]
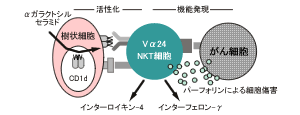
のものとして認識してパーフォリン(がん細胞膜穿孔因子)を放出し、
がん細胞を攻撃する。同時にインターフェロン-γを大量に分泌し、
自然免疫と獲得免疫を総動員して免疫力の強化を図る
樹状細胞は、NKT細胞やT細胞等のリンパ球に、がんの抗原を細胞の表面に押し出す免疫細胞で、専門的には抗原提示細胞と呼ばれる。
「樹状細胞は、投与された糖脂質を取りこみ、それを細胞の表面に浮きあがらせるのです。NKT細胞はそれを認識して、増殖と活性化のスイッチが入るのです」(中山さん)
実は、このような動物実験を紹介したのは、そこには重要な意味があるからにほかならない。NKT細胞の受容体��は、マウスと人間で互換性があるのだ。つまり、αガラクトシルセラミドという糖脂質は、種を越えてNKT細胞を刺激し、免疫力を強化するということなのである。
*樹状細胞=情報をリンパ球に伝え、リンパ球に攻撃する相手を認識させる機能を持ち、さらにリンパ球を活性化させる細胞。このような機能を持った細胞は数種類確認されているが、樹状細胞はもっとも効率よくこの機能を発揮する
NKT細胞免疫療法で肺がんに効果
NKT細胞免疫療法の第2相臨床試験は、2004年4月からスタートした。この臨床試験を受けた一人が、再発肺がんの河村啓溢さんだ。
彼が受けた治療は、まず腕の静脈から血液を採血し、必要な血液成分のみを取り出し、不必要なそれを戻すという方法(アフェレーシス)で単球とリンパ球のみを取り出す。
「約1時間半で200ccほどが取り出されました」(河村さん)
次に、採取した単球とリンパ球を7日間培養し、抗原提示細胞の樹状細胞をつくる。
投与直前に糖脂質を樹状細胞にまぶし、それを提示する樹状細胞にしたうえで、腕の静脈から点滴で患者の体内に戻す。
「樹状細胞の点滴投与は15分くらいですみます」(河村さん)
樹状細胞は合計4回投与する。第1回目の投与から1週間後に第2回目を行う。その後、4週間置いて再び患者から血液を採取して同じように樹状細胞をつくり、1週間後と2週間後に第3回目と第4回目の投与を行う。
いずれも樹状細胞を投与した翌日と、第2回と第4回の投与後1週間目と2週間目に、血液検査と胸部レントゲン検査を行う。最終の第4回目の投与から4週間の経過観察をもって、一連のNKT細胞免疫療法は終了する。
「通常、肺がんの患者さんの場合、NKT細胞は健康な人の10分の1以下、全白血球中の0.01パーセント以下であることが少なくありません。しかし、糖脂質の提示能力の高い樹状細胞を投与すると、NKT細胞はたちまち急増するのです」(中山さん)
これまでのデータによれば、少なくとも5~6倍、多い場合で20~30倍にNKT細胞が増えるという。ただし、NKT細胞が増えるのは樹状細胞を投与してから1~2週間の間で、その後は徐々に減少し元の数に戻っていく。
からの体内のNKT細胞数の推移]
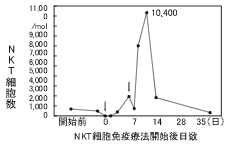
から1~2週間の間で、その後は徐々に減少し元の数に
戻っていくが、その間殺傷力を高めたNKT細胞ががん
細胞を次々と殺していく
その間、殺傷力を高めたNKT細胞ががん細胞を次々と殺していく。さらに、がん免疫システムを活性化させる*サイトカイン(インターフェロン-γ)を多量に分泌し、自然免疫と獲得免疫を総動員させる。
NKT細胞の数が再び元に戻っても、強化された免疫力が維持されるのは、免疫システムの再建の口火が切られたからである。
ちなみに、第1相臨床試験では樹状細胞の投与直後に一過性の有熱感や頭重感、倦怠感など軽度の副作用を覚えた人もいるが、重篤な副作用は見られなかった。
「私の場合、副作用らしきものは一切ありませんでした。むしろ樹状細胞を点滴投与した後は、少し元気になったような気がします」
と河村さんは微笑む。実際、再発肺がんの患者とは思えないほど、河村さんの顔色はよい。がんと共存状態を維持・継続している患者にとって、NKT細胞免疫療法は頼もしい援軍といえる。
*サイトカイン=細胞が産生する蛋白で、それに対するレセプターを持つ細胞に働き、細胞の増殖・分化・機能発現を行うもの
再発予防から再発・進行がんの治療まで大きな期待
NKT細胞免疫療法の治療効果の有無や、その程度を確かめる第2相臨床試験は第1相臨床試験に引き続き、キリンビールの作成したαガラクトシルセラミド(KRN7000)を使用し、千葉大学大学院医学研究院免疫発生学(中山俊憲教授)と医学部附属病院胸部外科学(藤澤武彦教授)との強力なチームによって進められる。
「NKT細胞免疫療法の最大の目標は、手術などでがんをすべて切除できた患者さんの再発の予防ですが、進行・再発がんの患者さんにも試み、その治療効果をしっかりと確かめていきたいと考えています」(中山さん)
NKT細胞免疫療法を受けたいと希望する患者は、千葉大学大学院医学研究院免疫発生学/胸部外科学(TEL 043-226-2969)に問い合わせてみてください。
同じカテゴリーの最新記事
- 1人ひとりの遺伝子と免疫環境で治癒を目指す! がん免疫治療が進んでいる
- 自分の免疫細胞も活用してがんを攻撃 PRIME CAR-T細胞療法は固形がんに効く!
- 頭頸部がんに対する「光免疫療法」の第Ⅲ相試験開始 第Ⅱ相試験の好結果を受け、早期承認への期待高まる!
- 白血病に対する新しい薬物・免疫細胞療法 がん治療の画期的な治療法として注目を集めるCAR-T細胞療法
- 進行膵がんに対する TS-1+WT1ペプチドパルス樹状細胞ワクチン併用療法の医師主導治験開始
- がん患者を対象とした臨床試験で証明された、米ぬか多糖体(RBS)の免疫賦活作用
- 先進医療の結果次第で、大きく進展する可能性も! 進行・再発非小細胞肺がんに対するNKT細胞療法
- 現在3つのがん種で臨床試験を実施中 がんペプチドワクチン療法最前線
- 免疫力アップで照射部位から離れた病巣でもがんが縮小 アブスコパル効果が期待される免疫放射線療法


