大腸がん、膵臓がん患者さんが悪液質タイプから脱却し、免疫老化まで改善か 栄養成分EPAを軸にした新機軸の栄養療法
青背魚に多く含まれる栄養成分EPAががんの炎症を抑える
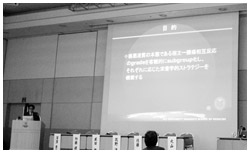
免疫栄養療法とは、がん患者に特定の栄養を補給することで、そうしたがん細胞周辺での炎症の拡大に歯止めをかけ、前述したがんのタイプをより大人しいタイプに転換させることを目的としている。さまざまな試行錯誤の中で、三木さんが着目したのが魚類、とくにイワシやサバなどの青背の魚に多く含まれる栄養成分でEPA(エイコサペンタエン酸)と呼ばれる脂質の効用だった。
「EPAは血液の循環を促進する作用などが認められていましたが、最近になってIL6の産生を抑制して筋たんぱくの崩壊を抑える働きがあることもわかってきました。そこでがん周辺の炎症の沈静化にも効果があるのでは、と考えたのです」
そこで、三木さんは昨年6月からEPAを豊富に含む栄養食品(商品名プロシュア)を用いて臨床研究を開始する。そうした経緯のなかで、EPAの効用の高さを痛感させられたのがステージ4の男性直腸がん患者Tさん(75歳)のケースだった。
発病前は70キロだったTさんの体重はがんの進行とともに激減し、手術直後の2009年6月には50キロまで落ち込み、歩くこともままならない状態にまでQОL(生活の質)も低下する。
そのため、術後の抗がん剤治療も行えずにいた。ちなみに、Tさんのがんは前のタイプ分類ではD群に属する典型的な悪液質タイプである。そこで、本人の「生きる意志」を確認したうえで栄養療法を実施する。具体的には摂取食事カロリーの増加により、D群からC群に変えたうえで抗がん剤とともにEPA配合栄養食品の投与を開始した。
するとまずCRPが減少し、次いでアルブミンが増加を始める。そうして2週間のEPAの投与により、Tさんのがんは悪液質タイプのD群から正常群のA群へと劇的な変化を���げる。と同時に、体重が増加に向かい、何の苦もなく自力歩行ができるまでにQОLも向上した。こうした変化を踏まえて、より強力な抗がん剤治療が行われ、腫瘍マーカーも正常化した。現在、在宅での化学療法を継続中だ。
三木さんは、この直腸がん患者Tさんの研究内容を、2009年10月に神奈川県横浜市で開催された日本癌治療学会で発表。そして、このTさんの研究内容に続き、三木さんの研究の中でさらにEPA配合栄養食品の効力の高さを物語る事例が浮かび上がってきているという。
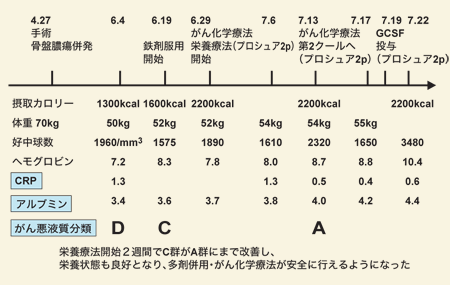
膵臓がん患者の研究で免疫機能老化の可能性が浮上
膵臓がんの女性、Hさん(79歳)が他院からの紹介で三木さんの診察を受けたのは昨年10月中旬のことだった。紹介元の病院のカルテでは、がんが見つかっているのは膵臓の膵体尾部と肝臓に限られており、三木さんは当初は外科手術の適用も考慮した。しかし念のため、再度検査を実施すると脾臓、胃に直接がんが浸潤し、さらに肺や全身の皮下、筋肉にも転移していることが判明した。ステージは最悪の4b期の進行がん。そのため、抗がん剤による全身治療に治療方針が切り換えられた。
Hさんは高齢であることに加え、がんが見つかってから60キロだった体重が4キロ近く減少、体力がかなり低下しており、さらに膵臓周辺の神経叢が圧迫され、腰に強い痛みを訴えていた。
また、それらの条件に加え、初診時の検査ではアルブミンは3.9と正常値だったものの、CRPが2.45と高値を示しており、がんのタイプは悪液質予備軍というべき、C群に属することも判明している。Hさんの「積極的治療を受けたい」という意思を確認し、初診の3日後からジェムザール(一般名ゲムシタビン)、TS-1(一般名テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム)の2剤併用による抗がん剤治療と、EPAをベースにした栄養食品を投与。そして、痛みを除くための緩和治療を同時にスタートした。
治療の効果は、驚くべきものだった。治療を開始すると、食欲も回復し、体重減少に歯止めがかかった。がんの悪性度にも明確な変化が現われた。ジェムザール投与直後は、連日の39度の発熱とともにCRPが4.9にまで上昇したものの、開始後9日目の検査では初診時の2.45からわずか0.6に激減、アルブミンの値も、抗がん剤治療中であるにもかかわらず、3.9から4.0に微増。2回目のジェムザール投与では、発熱も全くなく、また白血球減少などの抗がん剤治療による副作用もすぐに回復し、全身状態も良好に。さらに化学療法開始3週間後にはCRPも0.21となり、腫瘍マーカーCA19-9値は2300U/mlから1300U/mlへと半減していた。
「治療開始後3週間で、正常域であるA群へ移行。治療開始後1カ月間の体重減少はわずか400グラムです。病気との闘いが、ついに本来のスタートラインに立てた、といった感じです。もともと外見上はとても元気な人でしたが、その元気がホンモノになったという印象です。体の状態が良好なこともあって、化学療法を継続しながら11月には旅行も楽しまれています」
栄養成分EPAががんの栄養療法を変える
Hさんのケースは、EPA配合栄養食品に秘められた可能性を強く実感させるものだった。
「一般に老化が進行すると、全身の炎症反応が起こりやすくなることがわかっています。これは、リンパ球が外的刺激に過剰に反応することによって生じる反応で、免疫老化と言われています。予後が悪いがん悪液質の人たちは、この免疫老化が進行しているとも考えられます。今回のケースで、EPAはただ単純に炎症を抑えて悪液質を改善するのではなく、この免疫老化を改善しているという可能性も浮かび上がってきました。免疫老化により衰弱していた全身の免疫機能を、がんと闘えるように再び若返らせる働きがEPAにはあるのではないか。その1つの結果として、悪液質が正常化しているということも十分に考えられます」
三木さんは、「今後、国内外の施設と協力し、より多くのデータを集めていきたい」という。
現在、医療現場での栄養療法の位置づけは高いとはいえない。
「栄養強化が、生存率などのエビデンス(科学的根拠)に直結してこなかったことが致命的な弱点かもしれません。がん治療の中核を担う外科医や腫瘍内科医から見れば、手術や術後の化学療法に耐えるための体力づくりのための手段、あるいは術後の合併症の予防のための処置という程度でしか捉えられていないのが実情でしょう」
しかしEPAを中心とした栄養療法の今後の治療実績によっては、そうした認識が一変する可能性も決して小さくはない。
「栄養療法によって患者さんの全身状態を改善し、がんそのものの性格も予後のよい穏やかな性格に移行させながら集学的治療を実施する。そのことで、外科手術や化学療法の奏効率も飛躍的に高まり、その結果、生存期間延長のエビデンスも得られると考えられます」
EPAを中心とした栄養療法には、患者の体内の働きを高めることで、外科治療や化学治療をよりスムーズで効果的なものに強化する効用がある。免疫栄養療法という新たな観点から、今また、がん治療に新たな地平が築かれようとしている。
それがどんな未来につながっていくのか、新たな治療法への期待は膨らむ。
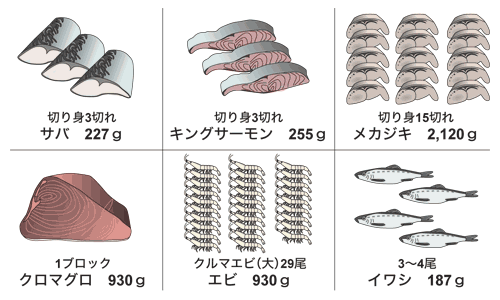
がんの栄養療法へのお問い合わせ
三重大学大学院医学系研究科 消化管・小児外科 准教授・病院教授 三木誓雄さん
Eメール
※三重大学医学部付属病院(tel:059-232-1111)外来日 毎週月曜日・水曜日午前
EPA配合栄養食品(プロシュア)に関するお問い合わせ
アボット・ジャパン株式会社(フリーダイアル 0120-744-100)
同じカテゴリーの最新記事
- 栄養療法+消化酵素補充療法で予後が改善! 膵がんは周術期の栄養が大事
- 術前のスコア評価により術後合併症や全生存率の予測も可能に 進行胃がんに対するグラスゴー予後スコアが予後予測に有用
- 高齢進行がん患者の悪液質を集学的治療で予防・改善 日本初の臨床試験「NEXTAC-ONE」で安全性と忍容性認められる
- 体重減少・食欲改善の切り札、今年いよいよ国内承認か がん悪液質初の治療薬として期待高まるアナモレリン
- 脂質で増殖する前立腺がんには脂質の過剰摂取に注意! 前立腺がんに欠かせない食生活改善。予防、再発・転移防止にも効果
- 闘病中や回復期、症状が安定していれば、健康な人以上に栄養を摂ることが重要
- がんと診断されたら栄養療法を治療と一緒に開始すると効果的 進行・再発大腸がんでも生存期間の延長が期待できる栄養療法とは
- 体力が落ちてからでは遅い! 肺がんとわかったときから始める食事療法と栄養管理
- がん悪液質に対する運動介入のベスト・プラクティス


