EPAががんによる炎症を抑え、QOLを改善 「あきらめないがん治療」を支える新たな栄養療法
炎症を抑える栄養素は青魚に多く含まれるEPA
こうした負のスパイラルを断ち切るために、三木さんは試行錯誤を繰り返してきた。たとえばがん細胞に抗炎症性サイトカインの遺伝子を導入することにより、IL6の放出を抑える手法の研究にも取り組んできた。しかし、そのためには莫大な費用が必要で現実的な方策とはいえないこともわかってきた。そんななかで三木さんが着目したのが、魚類とくにイワシ、サバなどのいわゆる青背の魚に多く含まれるEPA(エイコサペンタエン酸)と呼ばれる脂質の効用を活用する栄養療法だった。
「これまでもEPAには血液の循環をよくする作用などが認められていましたがそれ以外にIL6の産生を抑え、筋たんぱく質の崩壊を抑える作用があることもわかってきました。そこでがん組織の炎症の抑制にも効果があるのではないかと臨床に取り入れてみることにしました」
1日あたり2グラムのEPAを摂取すると体重減少を抑制できるという英国での臨床データもある。しかし、2グラムを食品から摂取しようと思うと黒マグロやエビで900グラム、メカジキなら2000グラムを摂取しなければならない。
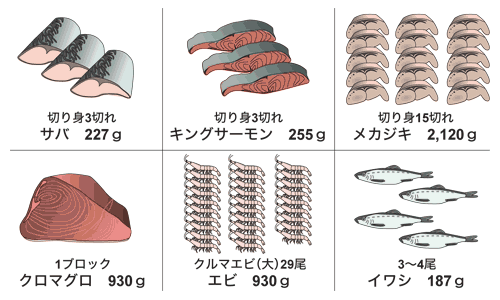
大腸がん患者を対象にした臨床研究を開始
そこで三木さんはEPAを豊富に含む経腸栄養剤(商品名プロシュア)を利用して、今年6月から臨床研究に着手する。ここで、その1例を紹介しよう。研究対象としたのは男性直腸がん患者Tさん(75歳)。もともと70キロだったTさんの体重は、がんの進行とともに激減し、病期がステージ4に達していた手術の後、今年6月には50キロにまで落ち込んでいた。当然ながら体力も著しく落ち込み、歩くこともままならない状態で、術後の抗がん剤による薬物治療も開始できない状態に陥っていた。
「高齢ということもあって、ご家族の中にはターミナル医療を行うほうがいいという意見もありました。しかし、生きたいと強く願う本人の意思を尊重して抗がん剤とEPAによる治療を並行して行うことにしました」
栄養療法を行う前の6月4日の時点では、血中のCRP値は1.3、血中アルブミン値は3.4。前の分類ではD群に区分される典型的ながん悪液質タイプである。それがまず摂取食事カロリーの増加により、C群に変化、さらに6月下旬から、抗がん剤とともにEPAの投与を始めると、まずCRPが減少し、次いでアルブミンが増加を始めるようになった。そうして栄養療法開始後の2週間後の7月13日には、Tさんの検査値のなかでCRPはわずか0.5にまで低下し、逆にアルブミンは4.0に増加していた。つまり、わずか2週間のEPA製剤の投与により、Tさんのがんは悪性がんの象徴ともいうべき、がん悪液質型(D群)から正常なA群へと変化したのである。
そうした変化の中でTさんのQOLも順調に推移した。Tさんは食欲が戻り、一時は1日1300キロカロリーしか摂取できなかったのが、2週間後には2200キロカロリーにまで回復し、体重も54キロに増加した。そんななかでQOLも向上し、1人で何の苦もなく歩行が可能になった。さらにその後、強力な化学療法を継続することができ、腫瘍マーカーが減少に転じ、化学療法開始後3カ月で、ほぼ正常化したという。またこの間、EPA製剤の服用を続けたことにより、体重もさらに増加を続けた。現在は退院され、在宅がん化学療法を継続中である。
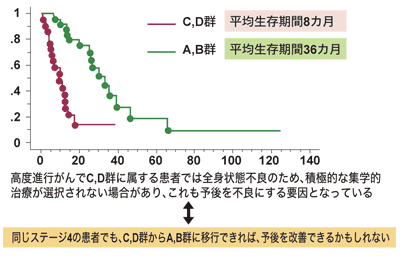
もちろん、すべてのケースでこのような効果が期待できるわけでもない。しかし、このTさんのケースはEPA効果の可能性を十二分に示唆している。
「Tさんのケースなどを見ると、血中のCRP値の推移から、この栄養成分ががん組織の炎症促進の元凶ともいうべきIL6の産生を阻害している可能性が極めて高いと思われます。そのことが分子生物学的に実証されれば、がん治療に新たな方向性が開けることでしょう」
「あきらめないがん治療」をサポートするのが栄養療法
がんの治療技術は日進月歩で進んでおり、化学療法、放射線治療、手術、ラジオ波療法など最新の治療が並行して施される集学的治療が常識となりつつある。もっとも悪液質型で進行が早いがんの場合には、体力の衰弱に治療が追いつかず、せっかくの技術革新も「宝の持ちぐされ」に終わることが少なくない。
「炎症の進行に伴って生じていたがん増殖の悪循環のメカニズムを断ち切り、好循環に転換させます。そのことでそれまでは治療をあきらめていた患者さんも、さまざまな手法による積極的な治療を受けることができるようになるでしょう。さらにそれに加えて、がん周囲の炎症が抑えられることにより、抗がん剤や放射線治療の効果が最大限に発揮できる可能性もあります。そのことでどれだけ多くの患者さんが救われることでしょう。EPAを中心とした栄養療法で、がん治療はまた新たな可能性を得たといってもいいでしょう」
化学療法をはじめとする多様な治療を側面から支える新たな栄養療法。「あきらめない、もう1度みんなで頑張ってみるがん治療」が現実に置き換えられようとしている。
がんの栄養療法へのお問い合わせ
三重大学大学院医学系研究科 消化管・小児外科 准教授・病院教授 三木誓雄さん Eメール
プロシュアに関するお問い合わせ
アボット・ジャパン株式会社 (フリーダイアル 0120-744-100)
同じカテゴリーの最新記事
- 栄養療法+消化酵素補充療法で予後が改善! 膵がんは周術期の栄養が大事
- 術前のスコア評価により術後合併症や全生存率の予測も可能に 進行胃がんに対するグラスゴー予後スコアが予後予測に有用
- 高齢進行がん患者の悪液質を集学的治療で予防・改善 日本初の臨床試験「NEXTAC-ONE」で安全性と忍容性認められる
- 体重減少・食欲改善の切り札、今年いよいよ国内承認か がん悪液質初の治療薬として期待高まるアナモレリン
- 脂質で増殖する前立腺がんには脂質の過剰摂取に注意! 前立腺がんに欠かせない食生活改善。予防、再発・転移防止にも効果
- 闘病中や回復期、症状が安定していれば、健康な人以上に栄養を摂ることが重要
- がんと診断されたら栄養療法を治療と一緒に開始すると効果的 進行・再発大腸がんでも生存期間の延長が期待できる栄養療法とは
- 体力が落ちてからでは遅い! 肺がんとわかったときから始める食事療法と栄養管理
- がん悪液質に対する運動介入のベスト・プラクティス


