痛いときに自分ですぐに鎮痛薬の投与ができるスイッチ1つで痛みを緩和 秘密兵器、電動式PCAポンプとは?
安全に、痛みをすぐに緩和する
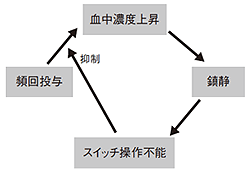
5月上旬に疼痛治療のため山梨大学に入院した肺がん患者Aさん(54歳、男性)は、放射線治療の影響で食道に炎症が起きてしまい、強い痛みのために入院日まで食事はおろか、飲み物も飲めないという状態が続いていました。
「この患者さんには、入院したその日から電動式PCAポンプを使用しました。直後に痛みが緩和され、すぐに飲み物や食べ物を摂取できるようになりました」
患者さんが自らスイッチを押す際の安全性に関しては、基礎持続投与量、ボーラス投与量ともに安全な量があらかじめ設定されているので、何回押しても「投与しすぎる」ことのない設定量となっています(図6)。
「山梨大学では、呼吸抑制などの重篤な副作用が生じないように「安全」を第一に投与量を設定しています。12年の間1万人を超える患者さんに術後のPCA治療を行いましたが、呼吸抑制による死亡例は1例もありませんでした。危険な量が投与されないように薬剤量を設定していますので、患者さんにはスイッチを1回押しても効かなければ『10分後にもう1回押してみてください』『何回押しても大丈夫』と説明しています」
診療報酬、インフラ整備などPCA普及の課題は山積
メリットの一方で、電動式PCAポンプを取巻く医療環境は現在、多くの課題が山積しています。
電動式PCAポンプは1970年に北米で開発された医療機器ですが、日本での普及は遅れたままです。
日本で普及が遅れている背景には、2つの理由が考えられています。
理由の1つは、診療報酬(医療行為等の対価として医療機関に支払われる報酬)に関する問題です。
PCAポンプには、大きく分けて2種類あります。電動式PCAポンプと、シリコンバルーンに薬液を充填するディスポーザブルタイプですが、日本ではこのディスポーザブルタイプが普及しています。
このディスポーザブルタイプが診療報酬の対象となっている一方、電動式PCAポンプは診療報酬の対象となっておらず、これが電動式PCAポンプの普及をさまたげる要因の1つと考えられています。
もう1つの理由は、電動式PCAポンプは医療用麻薬を患者さん自身が自由に自己調節できる機器であるため、使用にあたっては患者さんの管理体制など、病院側がインフラを整えておく必要がある点です。
「山梨大学では2000年から術後の患者さんを対象に使用を開始し、どのくらいの頻度で電動式PCAポンプや患者さんの状態を確認していけばよいのかなどの経験を積み重ね、患者さんが安全に、そして簡単に使用できる体制を整備しています」
電動式PCAポンプで「痛みのない病院」を目指す
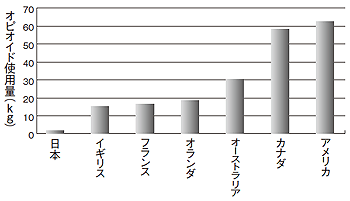
前述のように、電動式PCAポンプはいまだ普及体制が十分に整っていません。そのため、電動式PCAポンプを使用している医療施設は数少なく、患者さんの認知度も低いままという現状にあります。
しかし、電動式PCAポンプは患者さん1人ひとりの痛みへの「個別性」対応と、病院側の「効率性」や「安全性」を両立できる有効な鎮痛法といえます。
「電動式PCAポンプを用いた疼痛管理が行われている施設が『痛みの少ない病院』であり、今後も『世界で1番痛みの少ない病院』を目指していきたいと考えています」と飯嶋さんは言います(図7)。
患者さんの痛みを緩和する1つの方法として、電動式PCAポンプを使用できる医療体制の整備が求められています。
同じカテゴリーの最新記事
- こころのケアが効果的ながん治療につながる 緩和ケアは早い時期から
- 緩和ケアでも取れないがん終末期の痛みや恐怖には…… セデーションという選択肢を知って欲しい
- 悪性脳腫瘍に対する緩和ケアの現状とACP 国内での変化と海外比較から考える
- 痛みを上手に取って、痛みのない時間を! 医療用麻薬はがん闘病の強い味方
- 不安や心配事は自分が作り出したもの いつでも自分に戻れるルーティンを見つけて落ち着くことから始めよう
- 他のがん種よりも早期介入が必要 目を逸らさずに知っておきたい悪性脳腫瘍の緩和・終末期ケア
- これからの緩和治療 エビデンスに基づいた緩和ケアの重要性 医師も患者も正しい認識を
- がんによる急変には、患者は何を心得ておくべきなのか オンコロジック・エマージェンシー対策
- がん患者の呼吸器症状緩和対策 息苦しさを適切に伝えることが大切


