オピオイドの使用で実績をあげている新潟市民病院のチーム医療を紹介「緩和ケアチーム」で取り組むがんの疼痛治療
新潟市民病院におけるがん疼痛治療の実態
| 0 | なし |
|---|---|
| 1 | 時折の、または断続的な単一の痛みで、患者が今以上の治療を必要としない痛みである |
| 2 | 中程度の痛み。時に調子の悪い日もある。痛みのため、病状からみると可能なはずの日常生活動作に支障をきたす |
| 3 | しばしばひどい痛みがある。痛みによって日常生活動作や物事への集中力に著しく支障をきたす |
| 4 | 持続的な耐えられない激しい痛み。他のことを考えることができない |
緩和医療に熱心に取り組んできた同病院で、がんの痛みがどの程度解消されているか、痛みの治療にどのような鎮痛薬が使われているか、といったことを調べた研究がある。
調査対象は、08年1月の1カ月間に入院していたがんの患者さんで、2週間未満の短期入院患者、手術を受けた患者、早期がん患者を除いた。痛みの評価はSTAS(*)日本語版で行った。表のような基準に基づき、医療者が0~4の5段階で判定する。STAS0~1が、痛みが良好にコントロールされた状態だ。
入院時および入院14日目に、STASと使用されていた鎮痛薬を調べた。その結果をまとめたのが図1~6である。
痛みがないか、あっても現在の治療に満足している良好コントロール群(STAS0~1)の割合は、入院時は75.9パーセント。14日目には83.1パーセントに増えていた(図1)
入院時に何らかの痛みがあった人(STAS1~4)に限ると、良好コントロール群の割合は、入院時の36.7パーセントから、14日目の70.0パーセントに増えていた(図2)。
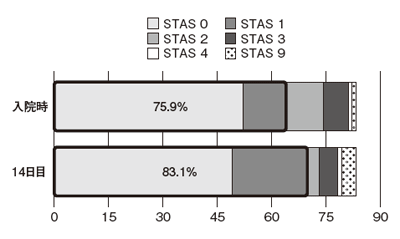
変化(STAS1~4)]
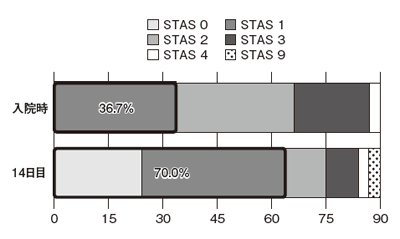
*STAS= Support Team Assessment Schedule
患者さんの7割以上の痛みを軽減
入院時に痛みを何とかしてほしいと感じていた人(STAS2~4)に限ると、14日目には、そのうちの73.7パーセントが、良好コントロール群になっていた(図3)。
疼痛治療に使われる代表的な薬には、NSAID(非ステロイド性抗炎症薬)とオピオイドがある。NSAIDはアスピリンの仲間。オピオイドはより強力な鎮痛作用を発揮する。
全対象者で見ると、オピオイド使用者の割合は、入院時には18.1パーセント。14日目には、33.7パーセントに増えていた(図4)。
入院時に何らかの痛みがあった人(STAS1~4)に限ると、オピオイド使用者の割合は、43.3パーセントから73.3パーセントに増えていた(図5)。
入院時に痛みを何とかしてほしいと感じていた人(STAS2~4)では、オピオイド使用者の割合は、52.6パーセントから73.7パーセントに増えていた(図6)。
「治療を望むような痛みがある患者さんの7割以上が、入院から2週間目には、かなり痛みが軽減しています。化学療法や放射線療法の効果もあるでしょうが、オピオイドを中心とした疼痛治療が、かなり貢献していると考えられます」(野本さん)
がんの痛みに対し、新潟市民病院でどのような治療が行われているのかを、次に紹介しよう。
感じた患者さんの変化(STAS2~4)]
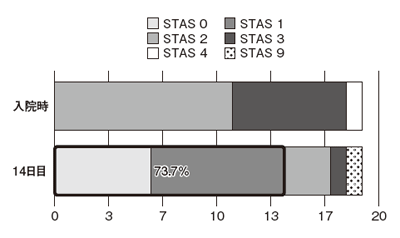
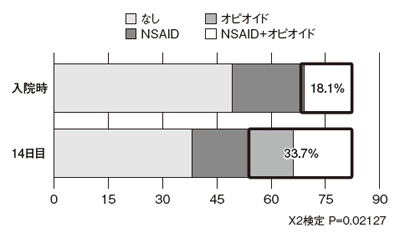
鎮痛薬使用の変化( STAS1~4)]
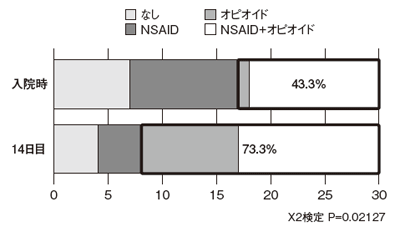
鎮痛薬使用の変化(STAS2~4)]
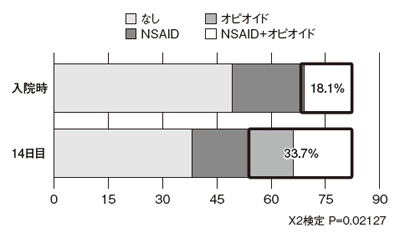
痛みは第5のバイタルサイン
バイタルサインといえば、心拍、呼吸、血圧、体温の4つを指すことが多い。医療現場では、患者さんの状態を把握するために、常にチェックされている。それに加え、疼痛治療を行う患者さんでは、痛みをチェックすることも必要だという。
使われている指標はNRS(数値的評価スケール)である。痛みなしを0、考えられる最も強い痛みを10として、現在の痛みを11段階で患者自身が評価するというもの。これを" 第5のバイタルサイン" として治療に生かしている。
「鎮痛薬の量を調節するのに欠かせない情報で、看護師が1日に3回聞いています。もっと短い間隔で聞いたこともあるのですが、回数が増えると患者さんにとってストレスになるので、現在は3回に落ち着いています。ただ、ひどい痛みがあるときには、何か手を打つたびにチェックします」(野本さん)
痛みの治療では、痛みを完全に取り除くのが理想だが、どこまで治療するかは患者さん自身が決定する。
「何を目指すかはまちまちです。痛みがなくなることを望む人もいれば、普通に生活が送れるなら少し痛みがあってもいいという人もいます。あなたの痛みをゼロにする方法があるということは伝えますが、そうしなさいとは言いません」(片柳さん)
どこまで治療するかを決めるのは、あくまで患者さんなのだ。
痛みの治療はWHO方式で
痛みの治療では、WHO(世界保健機関)方式が採用されている。3段階の痛みのレベルに応じて、NSAIDやオピオイドなどの鎮痛薬を、適切に使用していく治療法だ。
「WHO方式の疼痛治療法は、基本であると同時に最低ラインで、特殊な知識や技術がなくても、普通に処方箋を書ける医師なら、誰でもできる治療なのです」(野本さん)
WHO方式に従えば、第1段階の痛みはNSAIDで抑えるが、それでは不十分な第2段階、第3段階の痛みには、オピオイドを加えて治療する。適切にオピオイドを使用できるかどうかが、治療効果を決定する。
「オピオイドは経口投与が原則です。もちろん、食事ができない患者さんは別ですが、薬を飲めるなら、経口のオピオイドを使用します」(野本さん)
よく使われるオピオイドには、モルヒネとオキシコドンがある。
「オキシコドンは腎臓の悪い人でも使うことができ、副作用も若干少ないようです。最近の日本では、まずオキシコドンが使われるケースが増えているようです。5ミリグラム錠があるので、微調節できるというメリットもあります」(野本さん)
オピオイドの使用に当たっては、さまざまな誤解が妨げになることもある。たとえば、麻薬なので使用すると廃人になってしまうとか、終末期に使う薬で早い段階から使うものではない、といった根強い誤解がある。
「オピオイドに吐き気・便秘などの副作用があることは確かですが、副作用を予防する方法はあります。NSAIDで痛みがとれなければ、なるべく早くオピオイドを使用したほうがいい。痛い状態を放置していると、かえってオピオイドの必要量が増え、副作用対策も大変です」(野本さん)
オピオイドは終末期だけに使う薬ではない。早い段階から使用することで、患者さんのQOL改善に役立っている。
「野球の好きな人が、痛みのことなど忘れてテレビ中継を楽しむ。オピオイドはそれを可能にしてくれます。麻薬だからと抵抗感を持つ人には、よくそういう話をしますね」(片柳さん)
がんの疼痛治療は、患者さんの人間性を回復させる治療でもある。それが、終末期に関わらず必要なのは当然だろう。
同じカテゴリーの最新記事
- こころのケアが効果的ながん治療につながる 緩和ケアは早い時期から
- 緩和ケアでも取れないがん終末期の痛みや恐怖には…… セデーションという選択肢を知って欲しい
- 悪性脳腫瘍に対する緩和ケアの現状とACP 国内での変化と海外比較から考える
- 痛みを上手に取って、痛みのない時間を! 医療用麻薬はがん闘病の強い味方
- 不安や心配事は自分が作り出したもの いつでも自分に戻れるルーティンを見つけて落ち着くことから始めよう
- 他のがん種よりも早期介入が必要 目を逸らさずに知っておきたい悪性脳腫瘍の緩和・終末期ケア
- これからの緩和治療 エビデンスに基づいた緩和ケアの重要性 医師も患者も正しい認識を
- がんによる急変には、患者は何を心得ておくべきなのか オンコロジック・エマージェンシー対策
- がん患者の呼吸器症状緩和対策 息苦しさを適切に伝えることが大切


