「腕を温める」「希釈液を増やす」……さまざまな工夫で大腸がん患者さんの苦痛を和らげる XELOX療法の副作用「血管痛」はこうして乗り切ろう!!
腕を温めることで痛みを軽減する
仁科 血管痛が発現した場合、血流をよくするため、カイロを握らせたり、ソフトアンカを腕の下に敷いたりして、投与する側の腕を温めています(写真)。

兵頭 温める部位はどこがいいでしょう?
森 針を刺す部位から中枢側に血管に沿った痛みがある場合には、痛みのある部位を温めています。針を刺す部位より末梢側が冷たくなったり、ピリピリ痛んだりするような患者さんもいましたが、この方に対しては、腕全体を温めることも行いました。
仁科 点滴が痛いので、途中でやめてくれと言っていた患者さんがいました。しかし、ソフトアンカを用いて、腕全体をぐるぐる巻きにして温めたところ、最後にしびれが出ましたが、痛みはなく、「これなら治療を続けられる」というのが患者さんの感想でした。
ただ、これでは労力がかかりますし、薬剤が漏れ出たときに気づきにくいので注意が必要です。また、急性の末梢神経症状が主な訴えと考えられる患者さんには、カルシウム・マグネシウムの投与を考えています。
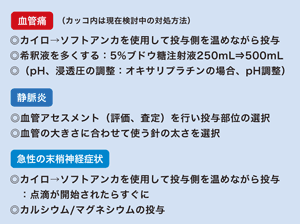
兵頭 エルプラットの末梢神経症状に、カルシウム・マグネシウムが有効という報告はありますね。
仁科 違和感や筋肉の痙攣に関しては、有効というデータがあります。
���院では、原則としてポートの留置を勧めますが、留置する患者さんは3分の1くらいで、他の患者さんは末梢血管からの投与になります。対応としてまず、看護師が針を刺すのに適している血管かどうか、きちんと確認してから針を刺します。これによって、痛みなどの症状はだいぶ軽減されます。さらに、温めることと、必要に応じてカルシウム・マグネシウムを投与します。それでもだめならポートを留置する、ということにしています(図2、3)。
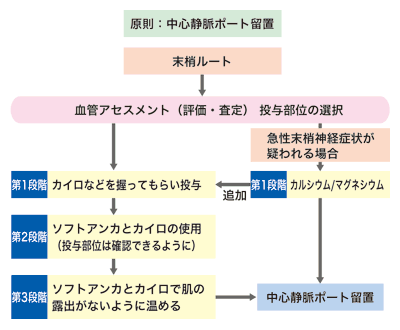
低すぎるpHが血管痛の原因?
兵頭 大阪医療センターではどうですか。
三嶋 XELOX療法が使えるようになって、多くをFOLFOX療法からXELOX療法に変えたところ、血管痛で治療継続が困難になる患者さんがいることがわかりました。一般的に血管痛には、薬剤によるもの、pHによるもの、浸透圧によるものがあるようです。XELOX療法による血管痛の原因はエルプラットによるものだけか、薬剤師に調べてもらいました。
松山 血管痛の原因となる滴定酸度(製剤に添加されている酸の量)、浸透圧、pHについて調べてみました。エルプラットに5パーセントブドウ糖注射液を加えた場合、滴定酸度と浸透圧はとくに問題ないのですが、pHが4.8と低く、これが血管痛の原因ではないかと考えられました。
デキサメタゾンを加えた場合のpH(大阪医療センター)]
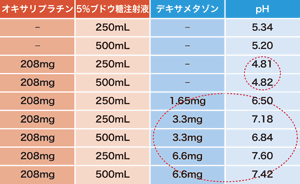
[図5 pHによる投与方法(大阪医療センター)]
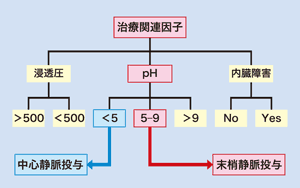
RCN IV Therapy Forum 2003.: Royal College of Nursing 2004.
三嶋 エルプラットをブドウ糖注射液で溶解すると、pHは低くなります。ブドウ糖注射液がこんなに酸性寄りだとは知りませんでした。生理食塩液を点滴しても痛くないのに、ブドウ糖注射液を2時間点滴すると痛いのは、これが原因だと気づきました。
松山 抗がん剤のファルモルビシン(一般名エピルビシン)の血管痛対策として、ステロイド薬のデカドロン(一般名デキサメタゾン)を少量加えることの有効性が報告されています。そこで、エルプラットと5パーセントブドウ糖注射液に、デカドロンを加えた場合の浸透圧とpHについて検討してみました。
その結果、浸透圧に関しては問題ないことがわかりました。pHに関しては、デカドロンを加えることで、中性の7に近い値に調整されます(図4)。ただ、デカドロンを6.6ミリグラム加えると、pHがアルカリ性に傾いてしまいます。薬の安定性ということから考えて、3.3ミリグラムまではいいが、6.6ミリグラムは添加してはいけないと思います。
三嶋 結局、pHが5~9の範囲に入り、末梢静脈投与に適していたことからエルプラットを5パーセントブドウ糖注射液250ミリリットルに溶解し、デカドロンを1.65ミリグラム加えることにしました(図5)。
松山 以前、FOLFOX療法を末梢血管から投与したことがありますが、そのときには血管痛は起きませんでした。エルプラットの量が少ないこともありますが、レボホリナート(一般名)と並列で投与していたためではないかと思います。レボホリナートのpHは6.5程度なので、並列投与したことでエルプラットのpHが中性の7に近い値に調整され、血管痛が起きなかったのだと思います。
患者さんのリスクや医療従事者の負担軽減のために
三嶋 エルプラットにデカドロンを配合して、問題ないのかという疑問があると思います。これについて、エルプラットの配合変化試験(*)の成績が報告されています。エルプラットにデカドロンを3.3ミリグラム混ぜるとpHが6.5になるのですが、24時間後のエルプラット含有率は98.28パーセントときわめて安定です。
ただ、エルプラットの添付文書には、「本剤は塩基性溶液により分解するため、塩基性溶液との混和あるいは同じ点滴ラインを用いた同時投与は行わないこと」と書いてあり、デカドロンは塩基性溶液ですから、ここが問題になります。また、デカドロンを配合して投与した場合のエルプラットの治療効果が担保されていないことも問題だと思います。
兵頭 実際にこれらの対策を行った症例があるということですね。
血管痛が起きた患者さんへの対応例(大阪医療センター)]

[図7 オキサリプラチンの血管痛対策(大阪医療センター)]
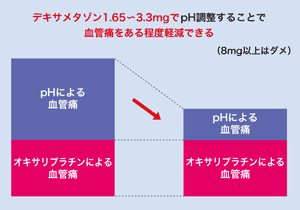
三嶋 エルプラットの点滴で血管痛が起きた患者さんの例です(図6)。1回目の投与では、痛みが出てから温めましたが、症状が消えず、75分で腕を変えました。痛みが出てからは点滴を遅くしたので、トータルで3時間かかっています。
2回目は希釈液を増やし、最初から温めました。痛みはありましたが、腕を変えるほどではなく、2時間で終了。3回目はデカドロンを加え、希釈液は元の250ミリリットルに戻しました。そうすると、痛みはかなり軽くなり、治療が継続できそうでしたので、それ以降はデカドロンを加えています。私は効果に関して、配合変化試験の結果を信じるという立場です。
XELOX療法の血管痛には、エルプラットという薬による痛みと、5パーセントブドウ糖注射液に由来するpHによる痛みがあると考えられます(図7)。希釈液の増量によって、薬による痛みを軽減できるのだと思います。そして、デカドロンを配合し、pH調整をすることによって、痛みの一部を減らせるのではないかと考えています。
石倉 当院では、添付文書に従ってデカドロンを最初からエルプラットと混ぜず、別の点滴ラインで投与するようにしています。そういった点は、考慮しませんでしたか?
三嶋 対策はなるべくシンプルにしたいので、別の点滴ラインから投与するのではなく、エルプラット希釈液に混和しました。デカドロンを入れて痛みが軽減すれば、腕を被って温めることで薬剤の漏出に気づきにくいという患者さんのリスクや医療従事者の負担を軽減できますからね。
デカドロンに関しては臨床試験を開始する予定です。
兵頭 どういった試験で、何が明らかになるのでしょうか。
三嶋 pH調整のためのデカドロンを混和する群と混和しない群に分け、血管痛の頻度などの差を調べる試験です。治療効果も見ますが、例数が少ないので、それに関しては何とも言えません。
兵頭 実際の治療における臨床試験ということですので、結果を楽しみにしたいですね。
*配合変化試験=ある薬に他の薬を加えたときの安定性などを調べる試験
同じカテゴリーの最新記事
- こころのケアが効果的ながん治療につながる 緩和ケアは早い時期から
- 緩和ケアでも取れないがん終末期の痛みや恐怖には…… セデーションという選択肢を知って欲しい
- 悪性脳腫瘍に対する緩和ケアの現状とACP 国内での変化と海外比較から考える
- 痛みを上手に取って、痛みのない時間を! 医療用麻薬はがん闘病の強い味方
- 不安や心配事は自分が作り出したもの いつでも自分に戻れるルーティンを見つけて落ち着くことから始めよう
- 他のがん種よりも早期介入が必要 目を逸らさずに知っておきたい悪性脳腫瘍の緩和・終末期ケア
- これからの緩和治療 エビデンスに基づいた緩和ケアの重要性 医師も患者も正しい認識を
- がんによる急変には、患者は何を心得ておくべきなのか オンコロジック・エマージェンシー対策
- がん患者の呼吸器症状緩和対策 息苦しさを適切に伝えることが大切


