「腕を温める」「希釈液を増やす」……さまざまな工夫で大腸がん患者さんの苦痛を和らげる XELOX療法の副作用「血管痛」はこうして乗り切ろう!!
症状と範囲をスコア化し対応の効果を判定した
範囲のスコア化(徳島赤十字病院)]
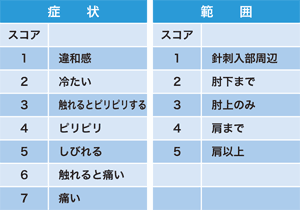
兵頭 徳島赤十字病院の対策はどうでしょうか。
組橋 エルプラット投与時に現れている症状について確認し、どのような症状があり、それがどのような範囲に現れているのかを調べました。そして患者さんが表現する多くの言葉から症状を分類することにしました。
さらに、内容に応じて点数をつけ、いろいろな対応で患者さんの症状がどのように変化したかを、スコアとして把握できるようにしました(図8)。
兵頭 対応としてはどのようなことが行われたのですか。
組橋 腕を温める、エルプラットの希釈液を増量する、デカドロンを制吐目的とは別に追加する、といったことです。デカドロンは、3.3ミリグラムを250ミリリットルの5パーセントブドウ糖注射液に加え、最初からエルプラットと混和せずに、別の点滴ラインで投与しました。
ホットパックで腕を温めたところ、症状が改善された人もいましたが、効果のない人、症状が強くなった人もいました。希釈液の増量でも、一部の人にはよく効いていますが、あまり変わらない人や、悪くなった人もいました。腕を温め、かつ希釈液の増量も行った場合、かなり効果が期待できるという結果が出ています。腕を温め、かつ希釈液を増やすことが効果的だったので、これにデカドロンを追加すると、さらによい結果が得られました(図9)。症例数が少なく十分なデータではありませんが、当院ではこのような対応策をとっています。
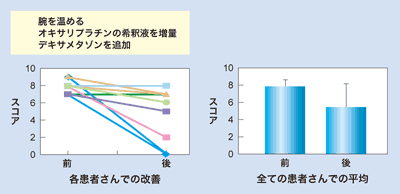
デカドロンの使用は効果がありそう
兵頭 デカドロンに関しては、250ミリリットルの5パーセントブドウ糖注射液に3.3ミリグラム入れ、やはり250ミリリットルの5パーセントブドウ糖注射液で希釈したエルプラットと、混和せずに同時に滴下するわけですね。
石倉 添付文書に、塩基性溶液との混和は行わないこと、と書かれていましたので……。最初から混ぜて、エルプラットの治療効果がなくなってしまったら困るという不安がありました。
兵頭 添付文書では、塩基性溶液との混和や同じ点滴ラインでの同時投与はしないこととなっています。ただ、実際に患者さんに血管痛が起きているわけですし、それを軽減する対策として、デカドロンの混和は非常に有効なオプションとなる可能性がありそうです。この点について、きちんと検討すべきである、という認識でよいのではないかと思います。
コース毎に対策を工夫
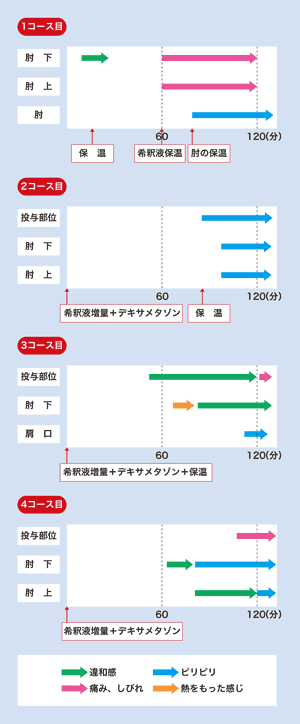
兵頭 組橋先生、具体的な症例を紹介していただけますか。
組橋 大腸がんの手術を受けた後、リンパ節転移が見つかり、アバスチン(一般名ベバシズマブ)+XELOX療法が行われることになった、65歳の男性患者さんがいます。血管痛などの症状に対して、図のような対策をとりました(図10)。
この方の場合、1コース目、通常通りに投与するとすぐに違和感が生じました。温めることで改善しましたが、60分ころから腕に痛みが発現しました。希釈液バッグを温め、肘が冷たくピリピリするというので肘も温めましたが、症状はあまり改善しませんでした。
2コース目は、前回たくさんの症状が出たので、希釈液を増量し、デカドロンを追加してスタートしました。80分ころから針を刺した部位周辺がピリピリし始め、腕全体にも広がりました。途中で腕を温めましたが、症状はほとんど変わらず、そのまま終了しました。
3コース目は、最初から腕を温めました。60分の少し前に針を刺した部位に違和感が出ましたが、これは最後まで違和感程度のままでした。最後に肩口にピリピリする症状が出ましたが、全体ではうまく症状をコントロールできたと思います。
熱を持った感じや違和感は温めた影響かもしれないということで、4コース目は希釈液の増量とデカドロンの投与だけにしました。針を刺した部位にしびれなどが出ましたが、患者さんはほぼ苦痛を感じることなく治療を終えました。
兵頭 コース毎に対策を工夫してみたところ、かなり改善されたということですね。
血管痛に対してどのような対策がいいか?
兵頭 それでは、血管痛に対してどのような対応策がいいのか、まとめに入りたいと思います。
三嶋 温める、希釈液の増量、デカドロン、これが3本柱になると思います。私は、デカドロンが1番目で、2番目に温める、3番目に希釈液の増量としています。
兵頭 仁科先生は、デカドロンを使っていないのですね。
仁科 薬剤として安定しているとは聞いていますが、やはりエルプラットの治療効果に影響がないかが気になります。混和しても効果に問題がないというエビデンス(科学的根拠)が出てからにしようと思っています。
三嶋 デカドロンを採用しないのであれば、2本柱でやればいいと思いますが。
仁科 希釈液の増量は、組橋先生のデータでは有効だということですね。希釈液が増えると血管外に漏れ出てしまうリスクが高まるので、これまでやっていなかったのですが、今後、希釈液を増やすことも試みたいと思います。
腕を温め、希釈液を増やしデカドロンを加える
兵頭 最後に、対策をまとめてみましょう(図11)。まず、痛みの起こった部位を温めたり、エルプラットの希釈液を増やしたりし、痛みが出てきたら投与速度を遅くします。投与部位は、中枢側(心臓に近い側)の太めの血管を選び、肘下なら親指側より小指側の血管がいいようです。
痛みが起きてしまった場合の対策としては、まず、痛みのある部位や希釈液を温めます。そのままでは治療継続が困難な場合には、デカドロンを混和するか、あるいは別の点滴ラインで同時投与する方法が有効だと考えられます。しびれなどがあり、急性末梢神経症状が考えられる場合は、カルシウム・マグネシウムの投与を検討します。
これらの対策を講じても末梢血管からの投与が困難な場合は、ポートからの中心静脈投与を検討します。――このような内容でよろしいでしょうか。
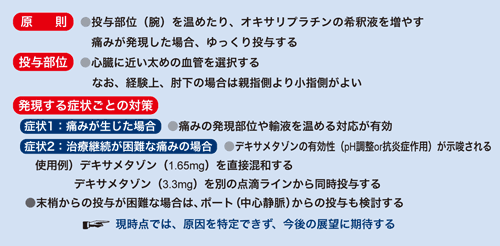
全員 そうですね。
兵頭 では、本日のお話が少しでも多く、患者さんのためになるように期待しまして、この座談会を終了したいと思います。ありがとうございました。
(構成/柄川昭彦)

各施設からXELOX療法の血管痛対策について、先進的な取り組みが紹介された
同じカテゴリーの最新記事
- こころのケアが効果的ながん治療につながる 緩和ケアは早い時期から
- 緩和ケアでも取れないがん終末期の痛みや恐怖には…… セデーションという選択肢を知って欲しい
- 悪性脳腫瘍に対する緩和ケアの現状とACP 国内での変化と海外比較から考える
- 痛みを上手に取って、痛みのない時間を! 医療用麻薬はがん闘病の強い味方
- 不安や心配事は自分が作り出したもの いつでも自分に戻れるルーティンを見つけて落ち着くことから始めよう
- 他のがん種よりも早期介入が必要 目を逸らさずに知っておきたい悪性脳腫瘍の緩和・終末期ケア
- これからの緩和治療 エビデンスに基づいた緩和ケアの重要性 医師も患者も正しい認識を
- がんによる急変には、患者は何を心得ておくべきなのか オンコロジック・エマージェンシー対策
- がん患者の呼吸器症状緩和対策 息苦しさを適切に伝えることが大切


