すべては患者さんのために 精神(こころ)にも身体(からだ)にも優しい緩和ケア
栄養サポートで食事を摂れるようになる
飢餓状態の患者さんは、適切な栄養サポートを行うことで、多くが食事を摂れるようになる。同病院の緩和ケア病棟では、入院期間中に口から栄養が全く摂れなかった人(経口摂取不能患者)は、余命が日単位となった患者さんを含めても、わずか8.3パーセントだったという。
食べられない患者さんにはまず、点滴による栄養補給で体力を回復させ、食べられるようになったら、各種の栄養剤を利用して必要な栄養を補給する。
また、患者さんの好物を採り入れて、嗜好の面からも食べたくなるような工夫をする。1回の食事量を普通食の4分の1、あるいは2分の1に減らすことで完食できるように配慮して、満足感を与えるといった工夫もする。
「栄養はできる限り口から食事として摂るのが基本です。単に栄養を摂取するだけでなく、見た目を楽しみ、香りや味を感じ、食べるという動作を行うことは、患者さんの癒しにつながります。また、免疫反応に重要な役割を果たすリンパ球の半分は腸の粘膜に存在するので、食べることが免疫力を高めることに役立つのです」
口から食事を摂ることは、このようにさまざまな効果をもたらすことになるのだ。
痛みの治療も“口から”が基本
栄養サポートと並んで重要なのが痛みの治療である。がんの痛みは全人的なもので、それらを構成しているのは、身体的苦痛(身体の痛み、日常生活動作の支障)・精神的苦痛(不安、いらだち、恐れ、怒りなど)、社会的苦痛(仕事・経済・家庭の問題、人間関係、遺産相続など)、霊的苦痛(人生への問い、死生観の悩みなど、スピリチュアルペインとも呼ばれる)だと言われている。
それら全てに対応する必要があるのだが、まず身体的な痛みを抑えなければ話にならない、と東口さんは言う。
「まず身体的な痛みを完全に抑えます。痛かったら食欲もなくなりますからね。食べられないのは当然だとあきらめることはありません。実は痛みの治療が不完全で、痛みのために食べ��れないケースもあるのです」
がんの痛みを抑えるためには、医療用麻薬を適切に使っていくことになる。こうした薬も、栄養と同じように“口から”服用するのが基本だという。
「飲み薬だと、薬の成分が腸から比較的安定して吸収されるので、確実な鎮痛効果が期待できますし、薬の量も調節しやすいのです」
医療用麻薬には飲み薬(経口剤)の他に、注射薬や坐薬や貼り薬(貼付剤)もあるが、基本となるのは飲み薬である。WHO(世界保健機関)は、鎮痛薬の使い方の原則を提唱しているが、その第1原則が「バイ・マウス(by mouth:経口的に)」となっているほどだ。
「飲み薬だと、自分で薬を飲んで痛みを抑えるので、患者さんにセルフ・コントロールの意識を根付かせるのに役立ちます。セルフ・コントロールの意識が高まれば、薬の量が不十分で痛みが取れていないのに痛みを我慢してしまうことや、必要以上に薬を飲みすぎたりする危険性が減りますし、在宅治療への移行も可能になります」
医療用麻薬の適正な使い方が大切
医療用麻薬にはいくつかの種類がある。最もよく知られているのは古くから使用されているモルヒネだが、その他にオキシコドン(一般名)とフェンタニル(一般名)という種類も日本で使われるようになった。このうちモルヒネとオキシコドンには飲み薬があるが、東口さんがまず用いるのはオキシコドンだという。
「最初に使う医療用麻薬はオキシコドンです。モルヒネも効果の点では申し分ないのですが、その患者さんにとって十分な量を投与しないと、吐き気などの副作用だけが出て、鎮痛効果が現れないことがあります。この段階で、もう飲みたくないと思ってしまう患者さんがいるのです。腎機能の悪い患者さんや高齢の患者さんでは、強い眠気や幻覚などの副作用が出てしまうこともあります。その点、オキシコドンはモルヒネに比べて副作用が少ないので、吐き気止め(制吐剤)や便秘薬(緩下剤)を上手に組み合わせて飲み始めることで、多くの患者さんにおいてスムーズな導入が可能なのです」
オキシコドンには、すぐに効く粉薬のオキノーム散(商品名)と、効果が長く続く錠剤のオキシコンチン錠(商品名)がある。東口さんは、まずオキノーム散の投与で開始して、痛みを抑えるために必要な量が決まったら、それをオキシコンチン錠に切り替えて投与することを基本パターンとしている。
痛みを抑えるために必要な量のオキシコンチン錠が投与されていれば、患者さんは1日2回決まった時間に服用することで痛みを感じることなく生活ができる。しかし、オキシコンチン錠をきちんと飲んでいても、突然痛みが出ることがあるので、そのときにはオキノーム散を飲んで痛みを抑える。

「オキノーム散を飲む回数が増えたときには、オキシコンチン錠の量を多くしますが、痛みの強さに応じて量の調整を適切に行っていれば、心配することはありません。オキシコンチン錠の量を調節することで、1日に何度もオキノーム散を飲まなくても、痛みのない生活を送っていただくことができます。そして、食べられなくなったり、飲み薬を飲むことができなくなったりした患者さんには、坐薬や注射薬を使います。医療用麻薬はできるだけ“口から”を基本にしながら、患者さんの状態に合わせて種類や投与方法を適切に選んで、適正に使用することが大切です」
飲み薬をできるだけ長く使うためにも、口からの食事摂取を大切にすべきと言えそうだ。
緩和ケアはあきらめの医療ではない

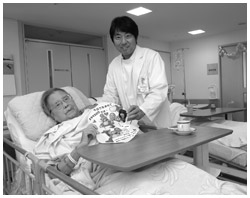
藤田保健衛生大学における緩和ケアの歴史は古く、1987年には前述の七栗サナトリウムに緩和ケア病棟が設置され、1997年には大学病院としては全国で初めて緩和ケア病棟として厚生労働省の認可を受けた。2003年には全国初の外科・緩和医療学講座が開設され、そして今年2010年3月には、本院である藤田保健衛生大学付属病院に今回取材をした緩和ケアセンターが開設された。
「緩和ケアは決してあきらめの医療ではありません。緩和ケア病棟で元気を取り戻して家に帰ることができる患者さんや社会復帰を果たす患者さん、がん治療に耐えられる体力を回復してから一般病棟に戻って抗がん剤治療を再開する患者さんもいます。たとえ、がんが治らなくても、がんと共に生きる体づくりをすれば、本来の寿命をまっとうすることができるのです」
患者さんやご家族の望みと提供される医療が同じところを目指している。だからこそ、患者さんたちは安心してこの緩和センターに入院することができる。
コミュニティ・ルームで開かれていたお茶会が終わると、患者さんたちはたくさんの絵画がかかった廊下を通り、それぞれの病室に戻っていく。これらの絵画は、車いすに乗っている患者さんの目線に合わせて少し低い位置にかけられている。
「先生もスタッフの方々もよくお話してくれますし、私の話も聞いてくれます。いつもやさしくしてくださるので、感謝の気持ちでいっぱいです」
この日82歳の誕生日を迎えた患者さんは、可動式ベッドの上で笑顔を見せていた。
同じカテゴリーの最新記事
- こころのケアが効果的ながん治療につながる 緩和ケアは早い時期から
- 緩和ケアでも取れないがん終末期の痛みや恐怖には…… セデーションという選択肢を知って欲しい
- 悪性脳腫瘍に対する緩和ケアの現状とACP 国内での変化と海外比較から考える
- 痛みを上手に取って、痛みのない時間を! 医療用麻薬はがん闘病の強い味方
- 不安や心配事は自分が作り出したもの いつでも自分に戻れるルーティンを見つけて落ち着くことから始めよう
- 他のがん種よりも早期介入が必要 目を逸らさずに知っておきたい悪性脳腫瘍の緩和・終末期ケア
- これからの緩和治療 エビデンスに基づいた緩和ケアの重要性 医師も患者も正しい認識を
- がんによる急変には、患者は何を心得ておくべきなのか オンコロジック・エマージェンシー対策
- がん患者の呼吸器症状緩和対策 息苦しさを適切に伝えることが大切


