渡辺亨チームが医療サポートする:緩和ケア編
渡辺亨チームが医療サポートする:緩和ケア編(1)
がんの発見が遅れる理由
橋爪隆弘さんのお話
*1 スキルスがん
- 胃がん全体の10%ぐらい
- 30代~50代の女性に多い
- 胃全体に横に広がる
- 転移は腹膜に転移するケースが圧倒的に多い
- 固い繊維組織を作りながら広がる
- 胃全体が縮む
- あまり予後がよくない
スキルスは「硬い」という意味です。スキルスがんはがん細胞がばらけて広がり、深く浸潤すると繊維化といって硬くなったものです。がん細胞の分裂がさかんで悪性度が高く「低分化型」と呼ばれます。スキルスがんは一般的な「高分化型」の胃がんのように胃壁が盛り上がり腫瘍が突起するものではなく、胃壁の中を這うように横に進行します。そのため早期発見が難しく、見つかったときにはかなり進行している状態で見つかることが少なくありません。スキルス胃がんに関しては内視鏡よりむしろ胃全体の動きが目視できるバリウム検査(二重造影法検査)のほうが発見しやすいところがあります。胃がん患者の10~20人に1人がスキルス胃がんといわれます。手術できた例でも5年生存率が10~15パーセントという厳しいがんです。
*2 ウィルヒョウリンパ節
左鎖骨上部にあるリンパ節で、この部分の腫れは胃がんの徴候として知られています。
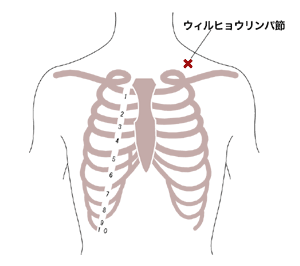
*3 がんの病状説明
がんの患者さん本人に、病状を説明することを以前は「告知」と言いましたが、現在ではそういう言い方はしなくなりつつあります。「告知」という呼び方はいかにも医師が患者さんの上に立って、教え授けるというイメージがありました。これに対して、もともと病気の情報は患者さん自身のものであり、医療者は治療のためにその情報を共有するのだという考え方に変わってきたのです。基本的にはご家族よりも、まず患者さん本人に説明することが求められるようになりました。
がん治療を進めるうえで、患者さん自身が正確な病名や病状を熟知していることが不可欠です。重い病気を抱えた患者さんにとって一番大切なのは、真実に基づいた医療者と患者さんの間のコミュニケーションです。本人が病名を知っているから治療や治療についての説明を受け入れることができます。ところが、日本ではいまだに自分の病気を知らされないままがん治療を受けているという患者さんが少なくありませ���。
具体策、解決策を提案することが大切
橋爪隆弘さんのお話
*4 悪い知らせの伝え方
医療者が患者さんにとって悪い情報を伝えるとき、「もう治療法はありません。ホスピスに移ってください」という話し方をして、患者さんや家族が途方に暮れてしまうケースがあります。患者さんに病状を知らせるには、がんをどうするか、いかにしてQOL(生活の質)を保障するかという具体策、解決策を提案することが大切です。患者さんのタイプに応じて、少しずつ状況を説明しながら、具体的に患者さんは今日からどうすればいいかを伝えることが必要となります。さらに、伝えたらご家族の説明に対する理解度を確認したり、気持ちの落ち込みがひどい場合の精神的なケアを行うなど、フォローアップすることも大切です。
2000年のASCO(米国臨床腫瘍学会)で、ロバート・バックマンというがん治療医がSPIKESというものを提案しています。医療者が患者に悪い知らせを伝えるときに心得るべき6つの要素を頭文字で並べた造語です。
- * S:Setting=話を伝えるための適切な場所を用意する
- * P:understand patients’ Perception=患者と家族がどのように自分の病気を理解しているかを把握する
- * I:obtain patients’ Invitation=患者と家族がどの程度知りたがっているかを把握する
- * K:provide Knowledge=目指すゴールを相談しあう
- * E:have and show Empathy=患者の感情との共感を示す
- * S:suggest Strategy=具体的なプランを示す
*5 全身状態
がんの患者さんの全身状態が、どのくらい活動能力があるかによって判断されます。この活動能力は、万国共通のパフォーマンス・ステータス(Performance Status=PS)という指標で示されます。下の表のように0~4の5段階で評価します。このうち、抗がん剤治療の対象となるのはPS1~PS2で、PS3~PS4は対象にはなりません。しかし、抗がん剤が少しでも症状の緩和や寿命を延ばすことに結びつくならPS3~PS4でも治療することがあります。これを「緩和化学療法」と呼びます。
| 0 | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく発病前と同等にふるまえる |
|---|---|
| 1 | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行や軽労働、(軽い家事など)、座業(事務など)はできる |
| 2 | 歩行や身の回りのことはできるが、ときに少し介助がいることもある。軽労働はできないが、日中の50%は起居している |
| 3 | 身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床している |
| 4 | 身の回りのこともできず、つねに介助が必要で、終日就床を必要としている |
*6 緩和ケア
治癒を目的とした医療ではなく、がんやがんに伴うつらい症状を和らげることを目標とした医療のことです。かつては、主に末期がんの患者さんなどに対して、痛みを中心とした身体的、精神的な苦痛の除去を目的とした医療を指していました。
これに対して1990年にWHO(世界保健機関)は、緩和ケアについて「治癒を目標とした治療に反応しなくなった患者に対する積極的な全人的ケアである」と定義しました。身体的痛みばかりでなく、社会的、精神的、霊的な痛み(スピリチュアルペイン)もコントロールされるべきであるとされたのです。そして緩和ケアの目的は、患者とその家族のQOLをできるだけ高い位置に持っていくことであり、それは病気の初期段階から適応されるべきものとされています。
さらにWHOは2002年に緩和ケアは、早期の診断、早期の治療によって苦しみを予防し、苦しみからの解放を実現すべきものであることを強調しました。緩和ケアは末期がんだけを対象にしたものではなく、がん診断初期から手術、放射線、抗がん剤というがんを直接攻撃する治療と並行して行うべきであるとされるようになっています。
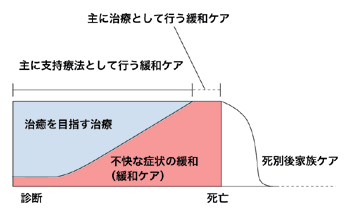
同じカテゴリーの最新記事
- こころのケアが効果的ながん治療につながる 緩和ケアは早い時期から
- 緩和ケアでも取れないがん終末期の痛みや恐怖には…… セデーションという選択肢を知って欲しい
- 悪性脳腫瘍に対する緩和ケアの現状とACP 国内での変化と海外比較から考える
- 痛みを上手に取って、痛みのない時間を! 医療用麻薬はがん闘病の強い味方
- 不安や心配事は自分が作り出したもの いつでも自分に戻れるルーティンを見つけて落ち着くことから始めよう
- 他のがん種よりも早期介入が必要 目を逸らさずに知っておきたい悪性脳腫瘍の緩和・終末期ケア
- これからの緩和治療 エビデンスに基づいた緩和ケアの重要性 医師も患者も正しい認識を
- がんによる急変には、患者は何を心得ておくべきなのか オンコロジック・エマージェンシー対策
- がん患者の呼吸器症状緩和対策 息苦しさを適切に伝えることが大切


