渡辺亨チームが医療サポートする:緩和ケア編
渡辺亨チームが医療サポートする:緩和ケア編(2)
橋爪隆弘さんのお話
*1 緩和ケア病棟
緩和ケア病棟はこれまで「ホスピス病棟」とも呼ばれ、がん治療に反応しなくなった終末期の患者さんが、痛みのケアを専門的に行う病棟と考えられてきました。しかし、現在の緩和ケアとは、がんの診断時から患者さんやご家族のQOL(生活の質)を支えることが主な目的で、ケアや治療が提供されます。緩和ケア病棟は緩和ケアの中でも主に終末期ケアを行っております。2007年9月現在、ホスピス・緩和ケア病棟として届出受理された施設数は、175施設3362床となっています。
*2 TS-1
日本で開発された経口の抗がん剤です。体内で5-FU(フルオロウラシル)という抗がん剤に変わって効果を発揮します。胃がん、大腸がん、頭頸部がん、非小細胞肺がん、膵臓がん、乳がんに対して保険適用されています。
胃がんについては単剤で奏効率が5割近くあり、進行胃がんでは平均2カ月の延命をもたらすとされています。比較的副作用が小さい抗がん剤でもあり、日本では急速に普及しています。
用量は平均的な日本人男性の体表面積1.5平方メートルで、1回50ミリグラム、1日2回服用します。用法は一般に4週間28日連続服用して2週間14日の休薬で1サイクルとして、これを繰り返します。
*3 がんの身体的疼痛の種類
がんの身体的痛みにもさまざまな種類の痛みがあります。がんの増殖に伴う痛み、骨転移の痛み、神経が浸潤される痛み、炎症に伴う痛み、抗がん剤の副作用により神経が障害される痛みなどです。疼痛治療はこれら痛みの原因や種類、強さに応じた対策がなされます。
*4 痛みスケール
同じ程度の痛みでも、その感じ方は人によって大きな差があります。しかし、痛み治療で大切なのはその人がどう感じているかであって、それに対応することです。0~5の6段階の顔の表情の絵を使ったり、10段階のスケールを使って痛みの強さと薬の効果を評価しています。
*5 がんの痛み治療に用いる鎮痛薬の種類
がんの痛みの治療は、痛みの強さに応じて痛み止めを3段階に分け、患者さんが感じる痛みの強さや痛みの種類に応じて薬を追加したり、組み合わせを変えたりします。よく用いる薬剤は、弱い痛みには消炎鎮痛薬やアセトアミノフェン、強い痛みにはモルヒネなどの強オピオイドといわれる鎮痛薬、さらにこれらの鎮痛薬に対応できない種類の痛みに対応する鎮痛補助薬の4種類です。
| ・消炎鎮痛薬 | アスピリン、イブプロフェン、セレコキシブ |
| ・アセトアミノフェン | |
| ・強オピオイド鎮痛薬 | モルヒネ、オキシコドン、フェンタニル |
| ・鎮痛補助薬 | 抗けいれん剤、抗うつ剤、ステロイドなど |
*6 WHO方式疼痛管理
WHO(世界保健機関)は、がんの疼痛管理について、「患者には痛みを除去するために痛み止めを要求する権利がある。医師はそれを投与する義務がある」「有効な治療法が存在するのに、それを実施しない医師には弁明の余地がなく、倫理的に許されないことである」とうたっています。そして、次の5つの原則を掲げています。
1.原則的に経口投与で行う
なるべく簡便な経路で投与するのが望ましい。経口投与ができない場合は、直腸内投与(坐薬)、または注射、貼り薬で行う。
2.時刻を決める
痛みが出てからではなく、薬の特徴に合わせて時刻を決めて内服する。
3.段階的に
患者の疼痛について的確に診断して、痛みや種類に応じてそれに合う鎮痛剤を使う。十分な効果があげられない場合は、増量したり、薬の種類の組み合わせを変える。
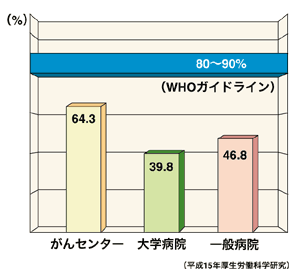
4.個々の患者にあわせる
疼痛治療に必要な量は患者によって異なるので、効果に応じて漸次増量し痛みの緩和に必要な量に到達するようにする。患者と疼痛治療の目標を共有することがポイントである。
5.きめ細かい対応を
モルヒネやオキシコンチン(一般名オキシコドン)は便秘や悪心・嘔吐などの副作用を予測できるので、予め下剤や制吐剤を使用する。効果の見通しと予想される副作用に関しては予め説明しておく。
がんの痛みはWHO方式に従えば80~90パーセントは取り除けるとしています。
しかし、たとえば日本の大学病院の場合、その数字は40パーセントを下回っています。言い換えれば日本では6割以上の患者さんが、痛みに苦しめられながらがん治療を進めているのが現状なのです。

石川千夏さんのお話
*7 緩和ケアチーム
がん治療の過程では身体的苦痛ばかりでなく、精神的・社会的・スピリチュアルな問題も発生します。これらの全人的苦痛を解決するために医師と看護師だけでなく、薬剤師、理学療法士、栄養士、臨床心理士、ソーシャルワーカー、医療事務(医事課)などの医療職が力を合わせるチーム医療が不可欠です。
2002年4月には厚生労働省が「緩和ケア診療加算」を医療保険で認可するようになりました。現在では一定の条件を満たした全国で60数カ所の施設が緩和ケア診療加算を算定して緩和ケア活動を展開しています。がん診療連携拠点病院などでは緩和ケアを提供する体制を有することが義務付けられています。それ以外にも緩和ケアチームが活動している病院は数多くあります。
*8 緩和ケア認定看護師
日本看護協会は高度化・専門分化が進む医療現場において、看護ケアの広がりと看護の質向上を目的にした専門看護師や認定看護師などの資格認定制度を設けています。緩和ケア認定看護師の制度は、がんの緩和ケアを必要としている人々に、トータルなケア(身体的・精神的・社会的・スピリチュアルなケア)を実践し、その人らしく生きることを支援できるエキスパートナースとして1998年に設けられました。以前は「ホスピスケア認定看護師」といいましたが、2007年7月から現在の名称になっています。同8月現在全国で420名が認定されています。
ただし、緩和ケアチームには必ず緩和ケア認定看護師がいるとは限らず、また緩和ケア認定看護師が緩和ケアチームに属しているとは限りません。
橋爪隆弘さんのお話
*9 モルヒネ
モルヒネは強い痛みに対する医療用麻薬の1つで、適正に使用している限り、非常に有用な薬です。日本のがんの疼痛治療で最もよく使われています。がんの強い痛みには、モルヒネなどの強オピオイドと呼ばれる鎮痛薬を十分な量使う必要があります。現在、強オピオイドには他にオキシコンチン(オキシコドン)、デュロテップ(フェンタニル)が使用されています。これらオピオイドには、痛くなったとき飲むレスキュー剤と、痛くなくても決まった時刻に飲む徐放剤があります。

同じカテゴリーの最新記事
- こころのケアが効果的ながん治療につながる 緩和ケアは早い時期から
- 緩和ケアでも取れないがん終末期の痛みや恐怖には…… セデーションという選択肢を知って欲しい
- 悪性脳腫瘍に対する緩和ケアの現状とACP 国内での変化と海外比較から考える
- 痛みを上手に取って、痛みのない時間を! 医療用麻薬はがん闘病の強い味方
- 不安や心配事は自分が作り出したもの いつでも自分に戻れるルーティンを見つけて落ち着くことから始めよう
- 他のがん種よりも早期介入が必要 目を逸らさずに知っておきたい悪性脳腫瘍の緩和・終末期ケア
- これからの緩和治療 エビデンスに基づいた緩和ケアの重要性 医師も患者も正しい認識を
- がんによる急変には、患者は何を心得ておくべきなのか オンコロジック・エマージェンシー対策
- がん患者の呼吸器症状緩和対策 息苦しさを適切に伝えることが大切


