がん治療医の痛み治療に関する知識不足、経験不足が患者を苦しめる 痛みに苦しむがん患者は、なぜこんなに多いのか
半数の医師が痛みについての基本的な知識がない
- 患者にとって簡単で維持・管理がしやすい経口投与を優先的に選択。漫然と坐薬を使用したり、嘔吐の可能性が高い患者には経口投与を選択しない。
- 薬剤の作用時間が途切れないように投与間隔を決める。特にオピオイドでは毎食後という指示はすべきではない。均等な時間間隔で指示することが重要。
- 患者にとって鎮痛が不十分な場合には、3段階のラダーにしたがって段階的に治療薬のレベルを上げて行く。オピオイドを避けて第1段階を引き伸ばさない。
- オピオイドによる鎮痛では、患者ごとに必要量が大きく異なる。痛いまま何日待っても効果は変わってくれない。
- 副作用が新たな苦痛とならないよう注意し予防に努める。治療への不安や疑問、病状の変化による投与経路の変更の必要性などに常に配慮する。
2006年6月、非営利団体「ジャパン・パートナーズ・アゲインスト・ペイン(JPAP)」がインターネット上で実施した調査(1000人の病院医師らの回答)がある。それによれば、疼痛治療に関して医師たちは表面的には知っている。たとえば、がんそのものに対する治療と痛みをとる治療では、まず後者を優先させるとか、「モルヒネなどの医療用麻薬を早期から積極的に使うべきだ」と答えた人が78パーセント。医療用麻薬の有効性や副作用を「説明できる」「多少は説明できる」とした人も92パーセントにも上っている。
しかし、がんの疼痛治療の世界的指針であるWHOの鎮痛薬の基本5原則というように、ちょっと踏み込んで聞くと、「聞いたことがない」「聞いたことはあるが知らない」という人が47パーセントもいるというのが実態だった。
また、薬の適正使用に不可欠な用語を知らない医師も多く、痛みを抑える薬について医師たちに基本的な知識が不足していることが明らかになった。
疼痛緩和に関する教育の不十分さ
このような医師たちの知識不足、無知の背景には、疼痛治療に関する教育の不十分さがあると考えられる。たとえばかつては��学医学部のなかでは、がんの痛みについて教育が行われているのは麻酔科の講義だけだった。しかもそれが30数時間だとしたら、そのうちの1時間くらいが痛みの治療について割かれ、さらにそのうちのわずか3分の2ががんの痛みにあてられるという貧しい状況だった。現在でも、医学部で疼痛緩和に関する講義を行っているのはわずか16パーセントしかない。
また、これまで、一般医師はおろか、緩和ケア専門医に対しても疼痛治療についての系統的な教育プログラムもなかった。昨年、ようやく日本緩和医療学会でそうした教育カリキュラムが作成され、それをもとに教育セミナーなどが実施され始めたところである。
「ようやくがん性疼痛に関する医学教育が本格的に始動しました。現在は、体系的な講義や実習を行うところも増えてきています。指導医からがん性疼痛治療の手ほどきを受けた若い研修医が医療現場で活躍し始めているので、これからは大きく変わっていくのではないでしょうか。今はちょうどがん疼痛治療の黎明期といえるでしょう」(小川さん)
治療をするには実践的教育や訓練が不可欠
先に挙げた患者QOL向上を目指したがん性疼痛治療に関する調査研究によれば、この疼痛治療に関する学習経験について、9割近くの医師は「経験がある」と回答している。しかし、これまたその内容を突っ込んで聞いてみると、「緩和ケアチームまたは緩和ケアの専門医のサポート」のもとで学習したという医師はわずか30パーセント弱。約半数の医師は学習経験がないか、あっても「学会やセミナー、専門誌」など、独学に近い学習形態であった。
痛みの治療は、知識があればできるというわけではない。知識に加えて、実地のトレーニング、実際の経験がなければ痛みについての適切な評価もできなければ、医療用麻薬も適切な量も使えない。
「少し前までは医師の間でも、モルヒネは『最後に使う手段』『死期を早める』『廃人になる』といった誤解から抜け出せない人がたくさんいました。1回10ミリグラムというわずかな量をおそるおそる投与していた医師の考え方、体質は、そう簡単には変わりません。学会やセミナーで医療用麻薬の使用法について講師の説明を聞いたり、専門誌で読んだりしたからといって、1日に80~90ミリグラムといった、それまでの経験からは考えられない量のモルヒネを患者さんに対し積極的に投与することは難しいでしょう。抗がん剤の投与同様、ベテランの医師から実地に教えてもらい、投与上の安全性や治療効果を実感してこそ初めて、がん疼痛治療において、モルヒネなどの医療用麻薬を駆使できるようになるのです」(小川さん)
医療用麻薬を使いこなす難しさ
ただ、先の「患者QOL向上……調査」によるがん治療医の調査では、「オピオイド(医療用麻薬)の導入をためらうことがある」と答えた医師は少なく(15パーセント)、「ためらわない」とした医師は8割以上に上っている。
しかし、実際の使い方を見てみると、患者が痛みを訴える前に兆候を把握し、治療を始めるとした医師はわずか12パーセント。半数以上は「患者による痛みの訴えがあってから」始め、さらに「患者からの訴えがあってもすぐには始めない」医師も26パーセントもいた。こうした点を考慮すると、実際には医療用麻薬を使えていないというのが実情のようだ。
また、医師がオピオイドの導入をためらう理由の第1は、「オピオイドローテーションが難しい」(45パーセント)点が挙げられている。オピオイドローテーションとは、オピオイド鎮痛薬による疼痛コントロールがその副作用などのために不良となった場合、他のオピオイドへ速やかに切り替えることをいう。たとえば、現在、日本ではモルヒネのほかに、オキシコドンやフェンタニルなどのオピオイドが使用可能である。便秘や吐き気などの副作用でモルヒネが投与できなくなったら、オキシコドンに切り替えることなどをオピオイドローテーションという。
その他の理由としては「オピオイドの処方量の加減が難しい」(21パーセント)、「麻薬使用への心理的な抵抗」(12パーセント)が挙げられている。
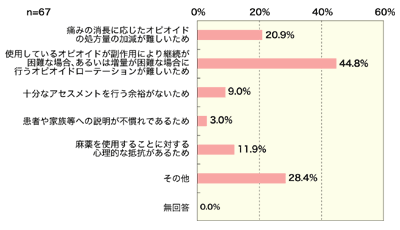
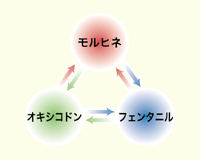
取り扱いの煩雑さがネック
医療用麻薬の使用に関しては、法律上の規制があり、取り扱いが煩雑なので、使用するのが難しいという側面もある。たとえば、モルヒネの処方は資格のある医師しか書けず、必要なときにすぐに処方してもらえないことが多い。
病院でも使用するたびに、管理簿へ細かく記入することが厳格に決められている。使用したモルヒネのアンプルやフェンタニルの貼付薬は、捨てずに保管し麻薬検査に備えねばならない。アンプルを破損した場合は、事故報告書を書かされる。オピオイドの使用については、もっと使い勝手をよくすることが求められている。
また、モルヒネの添付文書には「1日30~120ミリグラム、1日6回に分割し経口投与する」「1日20~120ミリグラムを2回に分割経口投与する」などといった記載があるが、もちろん、モルヒネは痛みが治まるまで投与量を増やせる有効限界のない鎮痛薬で、投与量に上限はない。とはいえ、医療用麻薬を使えるのは医師だけ。このような煩雑さを理由に使わないのは、医師の怠慢ではないのだろうか。
我慢しないで、痛みを訴えよう
もっとも、痛みで苦しむ患者が多いのは、医師だけに責任があるわけではない。患者側にも責任がある。
2004年6月にヤンセンファーマという製薬会社が行った「がん疼痛治療に関する一般意識調査」(400人の男女を対象)によると、痛みがあれば、「どんな薬でも使ってもらいたい」が66パーセント、「モルヒネを使ってもらいたい」が20パーセントとしながら、その一方で、「痛みは限界まで我慢すると思う」と答えた人が21パーセントもいた。つまり、痛みがあっても、医師に訴えないのだ。
別の調査でも、鎮痛薬を服用している患者の3分の1が「医師に遠慮」して、痛みを訴えていないことが明らかになっている。医師への遠慮だけでなく、多くの患者が「緩和ケアの開始=がん治療の中止」と考え、がんの治療にストップがかけられるのが嫌で、痛みを隠す傾向もあるようだ。
米国臨床腫瘍学会では「治療医はがん患者の大多数が訴える痛みを完全にコントロールすべきである。すべてのがん患者は痛みのない生活を送り、そして痛みのない死を迎える権利がある」とされている。
患者さんや家族の方はこのことを今1度思い起こし、「痛みを取ってほしい」と医師に訴えていくことが大切だ。痛みからの解放はそこから始まる。
同じカテゴリーの最新記事
- こころのケアが効果的ながん治療につながる 緩和ケアは早い時期から
- 緩和ケアでも取れないがん終末期の痛みや恐怖には…… セデーションという選択肢を知って欲しい
- 悪性脳腫瘍に対する緩和ケアの現状とACP 国内での変化と海外比較から考える
- 痛みを上手に取って、痛みのない時間を! 医療用麻薬はがん闘病の強い味方
- 不安や心配事は自分が作り出したもの いつでも自分に戻れるルーティンを見つけて落ち着くことから始めよう
- 他のがん種よりも早期介入が必要 目を逸らさずに知っておきたい悪性脳腫瘍の緩和・終末期ケア
- これからの緩和治療 エビデンスに基づいた緩和ケアの重要性 医師も患者も正しい認識を
- がんによる急変には、患者は何を心得ておくべきなのか オンコロジック・エマージェンシー対策
- がん患者の呼吸器症状緩和対策 息苦しさを適切に伝えることが大切


