痛みをなくすレポート(3)痛み治療で免疫力が高まる
痛みをなくすレポート(3)痛み治療で免疫力が高まる
池垣淳一さんのコメント
*1 がんの痛み
初診時のがん患者の3分の1に痛みがあり、亡くなるまでに痛みを経験する人は7~8割にのぼると言われています。痛みの原因としては、がんが組織に浸潤したり神経を圧迫したりする際の痛みや治療に伴う痛みなどがあります。 「痛くて眠れない」「痛みにじっとしていられない」という状況は地獄です。何としてでも、とにかく早く痛みをとる必要があります。
また、患者さんが亡くなる2カ月前の身体的な症状のうち、いちばん多いのが「痛み」(50パーセント)です。「全身倦怠」や「食欲不振」などはせいぜい10パーセントぐらい。つまり、痛みさえ取れれば、この時期、自宅に帰れます。これは社会的に復帰できるということで、患者さんにとって、疼痛治療は大きな意味を持つと考えます。
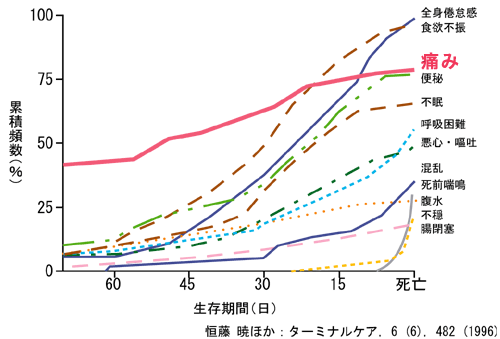
*2 WHO方式がん疼痛治療法
WHOでは、痛みの強さによって、使う薬の種類を変えていく方法を提唱しています。これは3段階に分かれていて、第1段階では、ロキソニンなどの鎮痛薬が用いられます。第2段階では、一般の鎮痛薬に加え、医療用麻薬(オピオイド)のうち「弱オピオイド」が追加されます。第3段階は、オピオイドが「強オピオイド」のモルヒネなどに変わります。
*3 オキシコンチン錠
日本では一昨年に発売されました。小腸でゆっくりと溶け出し効果が12時間持続する「徐放剤」ですが、即効性があります。モルヒネよりも副作用が少なく、安価なのでオピオイドの開始薬として最適です。オキシコンチン錠はWHO方式では第3段階の薬ですが、低用量のもの(5ミリグラム)は、第2段階から使えます。
*4 医療用麻薬に対する偏見
医療用麻薬を使うのは「最後」というイメージを持っておられる方は少なくありません。しかし、それは誤解です。がんの疼痛治療のために医療用麻薬を定期的に使っても、麻薬中毒にはなりません。体がぼろぼろになるとか死期を早めるということもありません。
ただ、医療用麻薬の副作用に対しては別の薬で抑える必要があります。副作用の出方には個人差がありますので、そのことを十分に理解して頂く必要があります。副作用がうまくコントロールできないと毎回処方が変わるので、不安に思われるかもしれませんが、患者さんとともに、粘り強く、その人に合った処方を探していくことになります。
*5 オキシコンチン開始指示書
当病院オリジナルのマニュ���ルです。半年前に導入しました。がんの疼痛治療に不慣れな医師でも、この書類にサインさえすれば、標準化された処方が自動的に行われます。短期間で患者さんごとに最適な薬の量を決定する仕組みで、反応するタイプではほとんどの人は2日以内に、8錠(40ミリグラム)までで痛みが止まります。痛みの程度に合わせて1種類の内服の鎮痛薬を増量していくだけなので、煩雑な計算や手続きが要りません。
これまでは、医師によって薬の処方がまちまちで、看護師は毎回違う指示を受けて混乱していました。また、従来の方法だと、医師によって必要な薬の量を決定するまでに要する時間がまちまちで遅れがちでしたが、新方式では、それが極めて迅速に、鎮痛に必要な量のオキシコンチン錠を決定することができます。
これで6割の人の痛みが止まります。止まらない場合は、麻酔科に連絡があります。治療を標準化していると、痛みがとれない場合のパターンが一定で対応しやすい。鎮痛補助薬を使ったり、神経ブロックなどの処置をしたりします。副作用の対応が困難な場合は薬を変えます。シンプルな疼痛治療なので、在宅ケアに移行する場合にも使えます。
ちなみに、最初から非常に激しい痛みのある患者さんには、飲み薬より効果が速い注射剤を使用して痛みをとります。その後、痛みがとれた注射剤の量を目安にして内服薬に切り替えます。緩和チームは標準化した治療で痛みがとれない場合は、24時間態勢で相談を受けています。がんの痛みをがまんしても何の得もありません。あなたの周りの医療スタッフにまず相談して下さい。
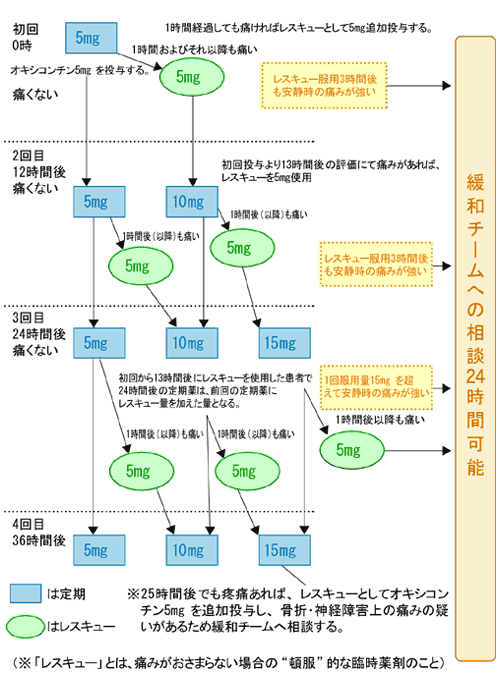
同じカテゴリーの最新記事
- こころのケアが効果的ながん治療につながる 緩和ケアは早い時期から
- 緩和ケアでも取れないがん終末期の痛みや恐怖には…… セデーションという選択肢を知って欲しい
- 悪性脳腫瘍に対する緩和ケアの現状とACP 国内での変化と海外比較から考える
- 痛みを上手に取って、痛みのない時間を! 医療用麻薬はがん闘病の強い味方
- 不安や心配事は自分が作り出したもの いつでも自分に戻れるルーティンを見つけて落ち着くことから始めよう
- 他のがん種よりも早期介入が必要 目を逸らさずに知っておきたい悪性脳腫瘍の緩和・終末期ケア
- これからの緩和治療 エビデンスに基づいた緩和ケアの重要性 医師も患者も正しい認識を
- がんによる急変には、患者は何を心得ておくべきなのか オンコロジック・エマージェンシー対策
- がん患者の呼吸器症状緩和対策 息苦しさを適切に伝えることが大切


