痛みをなくすレポート(5)痛みにすぐ対応する
痛みをなくすレポート(5)痛みにすぐ対応する
安部睦美さんのコメント
*1 緩和ケア病床
| ●1998年~ 緩和ケア研究会 |
|---|
| …「これからは緩和ケアが患者さんにとって大事」という思いを共有する有志が集まり、勉強会を開始。各科の医師にどんどん参加してもらい、WHO方式の薬の使い方で疼痛コントロールをしてくれるよう、アピールした。 |
| ●2001年~ 緩和ケア検討委員会 |
| …病院内の組織として、緩和ケア病棟の立ち上げに向けて活動。勉強会とともに、一般市民を巻き込んだシンポジウムを開いたり、安部医師らが公民館などで講演を行ったりしてきた。「緩和ケア病棟は死ぬところではなく、痛みを取って、これからの生き方を考えるところ」と利用者に伝えてきた。 |
| ●2003年4月~ 緩和ケア病床(3床) |
| …一般病棟(産科・婦人科・内科・放射線科・小児科の混合病棟)の中で、緩和ケアを開始。スタッフは「仕事は大変、だけど患者さんには必要」というジレンマを抱えながらも、1歩ずつ前進していく。 |
| ●2005年8月~ 緩和ケア病棟(22床) |
| …島根県初の緩和ケア病棟。この病棟の患者の7割は、院内の医師から紹介されてくる。院内の医師たちに「緩和ケアの必要性」が理解されている結果と言える。また、院内の一般病棟で積極的な抗がん剤治療をしている患者の緩和ケアも、安部医師らが“往診”する形で行っている。 |
松江市立病院では、2003年4月から、一般病棟(産科・婦人科・内科・放射線科・小児科の混合病棟)の中に、緩和ケア病床を3床もうけました。
一般病棟で緩和ケアをやることに、スタッフから心配の声もありました。それでも2年後に立ち上げが決まっていた「緩和ケア病棟」の準備段階として、導入しました。
始めてみると、看護師が患者さんのお話をじっくり聞いたり、必要なことに素早く対応したり、かなり満足のゆくケアができました。
この試みがうまくいった理由は、緩和ケア病棟への配属を希望していた看護師がその病棟に3~4人いたこと、また緩和ケアを熱心に学び、知識のある看護師が多かったためです。そもそも、7年前に発足した緩和ケア研究会の時代から、スタッフが地道に取り組んできた草の根活動の積み重ねが大きいと考えています。
医師だけでなく、患者さんを支えるあらゆる職種、看護師、理学療法士、栄養士、ソーシャルワーカー、薬剤師、事務、音楽療法士らが協力して作り上げてきたのが、この病院の緩和ケアの特徴です。
*2 一般的な鎮痛薬
WHO(世界保健機関)方式がん疼痛治療法はWHOが推奨するがんの痛みの治療法で、効果的で安全な治療法です。痛みに応じ、3段階の薬の使い方をします(除痛ラダーという)。
第1段階では、一般的な鎮痛薬(NSAIDs)を使います。第2段階では、第1段階の鎮痛薬に加えて、医療用麻薬(オピオイド)の弱いものか、それに相当する鎮痛薬を使います。第3段階では第1段階の鎮痛薬に医療用麻薬の強いものを加えます。実際には、第1段階から、第2段階をとばして第3段階に移行することがほとんどです。
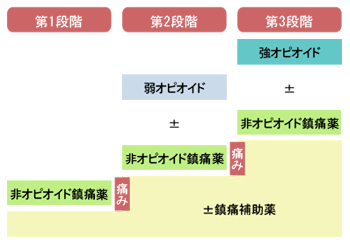
●オピオイド使用の時期は痛みの強さによる
●非オピオイドは必ず使う
*3 きめ細かな対応
患者さんがご自分の望むことを言える雰囲気を大事にしています。苦痛を取り除き、今後どう生きていくかを考えていただけるように、スタッフが支えます。また、患者さんによっては、「来年のこの日」がないかもしれません。できるだけその方の日常生活を大切にする工夫をしています。たとえば先日、栄養士が、あまり食べられない患者さんのお誕生日に、ハートの形の水ようかんを作ってくれました。
*4 カンファレンス
一緒にカンファレンスをすることによって、その患者さんに関する情報をご家族・各スタッフは共有することができます。食事の内容、排泄などすべてのことにおいて、重要な点を確認しておきます。すると、1つのことに関して、みんなが同じ言葉で説明することができるので、患者さんは混乱しなくて済みます。たとえば、「ここが痛いんだけど?」とたずねられた時、「それはこういう痛みですよ」と誰でも同じ説明ができます。
ちなみに、患者さんに大事な話をする時、私は必ず看護師に同席してもらいます。それによって、医師と患者の間だけの話で終わらせず、看護師に同じ情報を持ってもらうことができます。会話の雰囲気は言葉では伝えにくいので、同席することに意味があります。

カンファレンスでは、患者さんに関わるスタッフ一同が同じ認識を持つように心がけた
*5 医療用麻薬(オピオイド)
「医療用麻薬」を使う場合、タイミングが重要です。
痛みが強くなった時、早めに医療用麻薬を使うと、低用量でコントロールできます。
ただ「麻薬」に抵抗感のある方は少なくありません。ご高齢の方の中には、戦後、麻薬中毒者を見た経験のある人もいます。そこで、「医療用麻薬」が決して怖い薬ではないことを丁寧に説明します。
医師が適量を的確に使えば、絶対に中毒になったり、廃人になったりはしません。また、人間の身体は痛みを感じた時に、脳からモルヒネ様物質を出して、痛みを和らげます。頭痛や腹痛なら、ふつうの痛み止めを足せば治まりますが、がんの痛みは、それでは足りないので、「医療用麻薬」を補います。そう説明すると、たいていの方が安心されます。
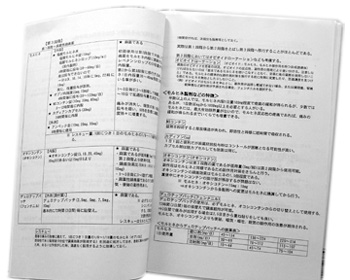
同じカテゴリーの最新記事
- こころのケアが効果的ながん治療につながる 緩和ケアは早い時期から
- 緩和ケアでも取れないがん終末期の痛みや恐怖には…… セデーションという選択肢を知って欲しい
- 悪性脳腫瘍に対する緩和ケアの現状とACP 国内での変化と海外比較から考える
- 痛みを上手に取って、痛みのない時間を! 医療用麻薬はがん闘病の強い味方
- 不安や心配事は自分が作り出したもの いつでも自分に戻れるルーティンを見つけて落ち着くことから始めよう
- 他のがん種よりも早期介入が必要 目を逸らさずに知っておきたい悪性脳腫瘍の緩和・終末期ケア
- これからの緩和治療 エビデンスに基づいた緩和ケアの重要性 医師も患者も正しい認識を
- がんによる急変には、患者は何を心得ておくべきなのか オンコロジック・エマージェンシー対策
- がん患者の呼吸器症状緩和対策 息苦しさを適切に伝えることが大切


