痛みをなくすレポート(6)患者と医師の信頼関係
痛みをなくすレポート(6)患者と医師の信頼関係
目黒則男さんのコメント
*1 緩和ケアチーム
大阪府立成人病センターで緩和ケアチームが発足したのは、2003年3月ですが、当院の緩和ケアの歴史は古く、85年の「ターミナルケアを考える委員会」設立に遡ります。5年ごとにテーマを設け、活動を継続してきました。緩和ケアチームの診療加算の施設基準を取得した病院は、全国に約50、大阪に4つありますが、大阪で一番早く取得したのがわれわれの病院です。現在チームの構成員は、精神科、泌尿器科などの医師6人のほか、看護師(がん専門看護師1人、がん性疼痛専門看護師2人)、理学療法士、ソーシャルワーカー2人、薬剤師、事務の合計14人です。
*2 痛みの強さ
痛みを治療するには、痛みの強さを正しく把握する必要があります。痛みを測るものさしとしては、「痛みなし」から「最高の痛み」までを横線で表し、痛みがどのあたりかを示してもらうVAS(ビジュアル・アナログ・スケール)、痛みの度合いをゼロから10までの数字に置きかえて口頭で答えてもらう方法などがありますが、数字で表現するのに慣れておらず、戸惑う患者さんには顔の表情で痛みの強さを6段階で表すフェイス・ペイン・スケールを用いることもあります。
*3 オピオイド鎮痛薬
患者さんがオピオイド鎮痛薬の使用を嫌がる理由として最も多いのは、「中毒や依存症になる」「痛みをとる最後の手段」で、次に「寿命を縮める」「薬が増える」「副作用が強い」などがあります。これらは、かつての「麻薬=モルヒネ」のイメージから抱く誤解や偏見に根ざしたもので、患者さんばかりか、医療関係者でも間違った認識をしていることが今なおあります。では、どうすれば患者さんはオピオイド鎮痛薬を受け入れやすくなるのでしょうか。単に「優れた鎮痛効果をもつ良い薬」と説明しても不十分で、「WHO(世界保健機関)で推奨されている」「世界で広く使われている」とさらに説明されると受け入れやすくなるようです。
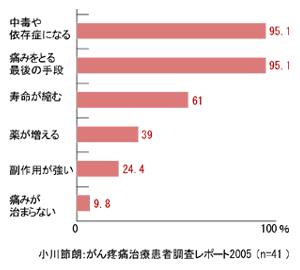
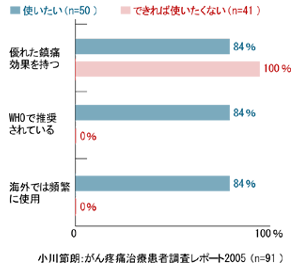
*4 チームワーク
緩和医療は救急医療と同じです。今、患者さんはどんな問題を抱えていて、何をどのように解決していくのかを決める必要があります。週1回の回診時に情報を得るのでは遅く、われわれは院内メールでチーム全員に同じメールを送って日々の情報��共有しています。メーリングを開始してからは、情報交換が迅速になり、連携が良くなりました。
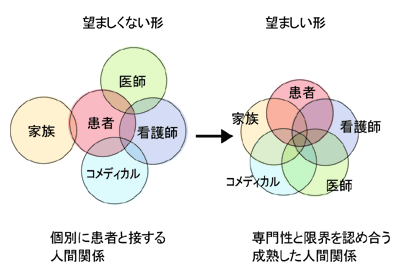
*5 オキシコンチン錠
「われわれがオキシコンチンを使い出したのは2003年からです。現在では使用するオピオイド鎮痛薬ではオキシコンチンが最も多くなっています。その理由は、個々の患者さんの痛みの強さに応じた最適な量を調節しやすいこと。またこの薬が腎機能に影響なく使えるので、病状の進行や化学療法などによって腎機能が低下した患者さんでも安心して使うことができ、また薬価も安く、副作用の吐き気や眠気も若干ですが少ない印象があるからです。さらに難治性の神経因性疼痛にも比較的有効とされるのもメリットのひとつです。
*6 神経因性疼痛
神経因性疼痛はがんによる末梢神経や中枢神経の損傷や障害によっておこり、その関連領域の痛みを感じます。米国疼痛学会ガイドラインによれば、がん患者の30~40パーセントに出現します。一般に、モルヒネが効きにくいとされています。オキシコンチンは近年、この神経因性疼痛にも比較的有効との報告があります。
同じカテゴリーの最新記事
- こころのケアが効果的ながん治療につながる 緩和ケアは早い時期から
- 緩和ケアでも取れないがん終末期の痛みや恐怖には…… セデーションという選択肢を知って欲しい
- 悪性脳腫瘍に対する緩和ケアの現状とACP 国内での変化と海外比較から考える
- 痛みを上手に取って、痛みのない時間を! 医療用麻薬はがん闘病の強い味方
- 不安や心配事は自分が作り出したもの いつでも自分に戻れるルーティンを見つけて落ち着くことから始めよう
- 他のがん種よりも早期介入が必要 目を逸らさずに知っておきたい悪性脳腫瘍の緩和・終末期ケア
- これからの緩和治療 エビデンスに基づいた緩和ケアの重要性 医師も患者も正しい認識を
- がんによる急変には、患者は何を心得ておくべきなのか オンコロジック・エマージェンシー対策
- がん患者の呼吸器症状緩和対策 息苦しさを適切に伝えることが大切


