これだけは知っておきたい。在宅医療の基礎知識 緩和ケアは在宅でも受けられる
病院、開業医、訪問看護、それに地域福祉が連携する

福島労災病院(福島県いわき市)
たとえば、私が福島労災病院で最初に在宅がん治療を始めたのは87年でしたが、いわき市は94年、「地域で看取る」をテーマに2つの取り組みを始めています。
ひとつは、市の保健所がコーディネートして、介護支援や福祉サービスなど、地域社会福祉と病院との連携である「いわき地域在宅ターミナルケア・システム」が作られたこと。もうひとつは、いわゆる病診連携です。
病診連携とは総合病院と開業医(診療所)の医師が連携を取り、がん患者の在宅医療を支えるシステムですが、その一環として、各開業医にどんな「在宅治療」が可能かをリスト化した「いわき安心医療マップ」を、97年にいわき市医師会がまとめています。患者さんは保健所に尋ねたりマップを利用すれば、少なくとも在宅がん治療に熱心な医師や病院は探せるということになります。
そうした病診連携の中で、訪問看護ステーションの果たす役割も小さくありません。患者さんや家族と直接向き合うのは看護師さんたちです。実際の医療行為を行うのも看護師さんです。福島労災病院にも96年、訪問看護室が作られ、看護師さんたちは驚くべき努力で技術を習得されました。その姿を見て、私は「在宅がん治療の中でも特に緩和ケアは、看護師さんが中心になって行なうべきだ」と思いました。事実、今後の病診連携の要になるのは、訪問看護ステーションと思います。
訪問看護師のレベルが一定レベルに達するためには、研修も必要ですし、医師でなく看護師によるケアに保険点数がつくなどの医療保険改正も必要でしょう。が、現時点でも在宅がん治療に習熟した看護ステーションは、各地に確実に増えています。そこからたぐって、納得のいく在宅がん治療を探し当てる道筋もあるかと思います。
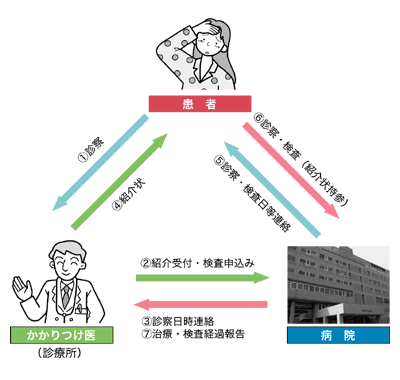
全国各地に相談窓口も動き出した各地の在宅医療構想
では、具体的にどこでどんな試みが始まっているのでしょうか。いわき市の例はお話ししたとおりですが、宮城県でも行政と病院と開業医が連携した独特の病診連携が確立されつつあります。広島では、一般相談窓口(コール・センター)をふくむケアセンター構想が、県の主導で今年始まりました。千葉県でも、全県の医療マップが作られたと聞いています。
相談窓口は福岡県や山口県にも作られたようですし、愛媛県松山市では松山市医師会が国立がん研究センターとインターネットを通じたネットワークを作っているとか。そのほか、各地で在宅医師リストなどを提供するNPOも増えていますし、緩和ケア関連の学会が看護師な���の教育システムを見直すという動きも出ています。
さらに、各地の活動を集約し、意見を統一して、厚生労働省にシステム作りや法的な整備を働きかけようという試みも、この秋、行なわれます。在宅がん治療を巡る動きは、ここに来てたいへん活発になっています。患者さんや家族の皆さんにも、ぜひ動きを注視していただきたいと思います。
看取りを取り戻すことで、地域文化を再生しよう
在宅がん治療は、さまざまな症状のコントロールが必要な点がほかの在宅医療と違っているとお話ししましたが、最期に到達するのが看取りであるところと、期間が短いというところも、ほかの在宅医療と違います。
もちろん、緩和ケアの最期に容態が急変し、病院に緊急入院するケースのほうが一般的でしょう。けれども私は、できるならご家族が患者さんを看取っていただきたいなあと思います。そして、いかに上手に自宅で看取りまでもっていくかというのが、実は在宅がん治療の最終目標ではないかと思うのです。
自宅での看取りはかつて、当たり前でした。その当たり前が当たり前でなくなり、社会から身近な死がなくなった結果、さまざまなゆがみが起きてきた気がします。
現実を見ても、在宅ケアをいいものにするためには、病院だけでなく地域全体がそれを支える必要があります。そもそも、人の生き死には地域社会のあり方そのもの。人間が人間の生まれ育つ場に、みんなが暮らしやすい環境を作り上げるということは、実はその地域に文化があるということなんですね。
その意味で、在宅がん治療は地域社会、地域文化と密接につながっています。当然、地域住民や地域社会を巻き込んだ形で展開しなくては、うまく普及するはずがないのです。
「地域文化の再生」などと言われても、患者さんにとってはピンと来ないかもしれません。最期の話なども聞きたくないかもしれません。しかし逆に言えば、患者さんは「家族に負担をかける」などと遠慮せず、在宅がん治療を最大限に生かして、自宅での生活を楽しんで過ごしていいのだと思います。
どうぞあらゆる知恵を駆使して、充実した在宅ケアライフを過ごしてください。
同じカテゴリーの最新記事
- こころのケアが効果的ながん治療につながる 緩和ケアは早い時期から
- 緩和ケアでも取れないがん終末期の痛みや恐怖には…… セデーションという選択肢を知って欲しい
- 悪性脳腫瘍に対する緩和ケアの現状とACP 国内での変化と海外比較から考える
- 痛みを上手に取って、痛みのない時間を! 医療用麻薬はがん闘病の強い味方
- 不安や心配事は自分が作り出したもの いつでも自分に戻れるルーティンを見つけて落ち着くことから始めよう
- 他のがん種よりも早期介入が必要 目を逸らさずに知っておきたい悪性脳腫瘍の緩和・終末期ケア
- これからの緩和治療 エビデンスに基づいた緩和ケアの重要性 医師も患者も正しい認識を
- がんによる急変には、患者は何を心得ておくべきなのか オンコロジック・エマージェンシー対策
- がん患者の呼吸器症状緩和対策 息苦しさを適切に伝えることが大切


