ネックは治療費。しかし、早ければ来年にも保険適用の可能性あり 難治がんに有効で、副作用が少ない重粒子線治療の威力
重粒子線治療の特徴の1つ、治療期間が短くてすむ
治療期間が短くてすむのも、重粒子線治療の特徴の1つだ。
「治療は平均12~13回、3週間ほどで終わります。一般の放射線や陽子線の治療はその倍ぐらいかかりますから、かなりの短さです。小さな肺がんだと1日1回の治療で終わり、肝がんでも1~2回。比較的長期の治療が必要とされるのが前立腺がんや骨軟部腫瘍ですが、それでも約16回、4週間ぐらいで終わります」
X線などの場合、正常組織への障害を考えて、期間を長くとって治療するのが常識だが、ピンポイントの集中性があり、同じ線量でも生物効果が高い重粒子線治療は、短期治療に向いている治療法といえよう。
気になるのは副作用だが、「一般の放射線照射につきものの骨髄機能が落ちたり、周辺の組織にダメージを与えたり、などはほとんどゼロに近い。臨床応用を始めた当初はどれだけの線量がよいかわからず、かなりの副作用が出たりもしましたが、技術が成熟した今では、ほかの治療法と比べても、もっとも低い率の副作用におさまっていると思っていただいて差し支えありません」
と辻井さんは語る。
患者にとってのネックは、高額の治療費
ここまでは患者にとってうれしいことばかりの治療法といえるが、現在、患者にとってネックとなっているのが治療費の高さだ。
先進医療の対象ならば混合診療が認められるため、重粒子線照射は患者の自己負担となる。一方、治療に必要な診察、検査、投薬、入院など、一般の治療と共通する部分は保険診療となる。
それでも、重粒子線照射そのものの患者自己負担額は314万円にのぼり、「高額療養費制度」の対象外のため、全額を患者が支払わなければならない。
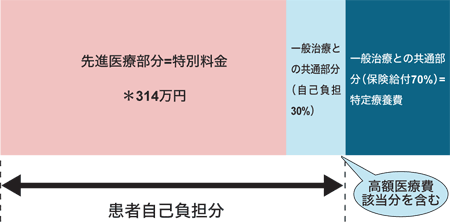
幸いなことに、民間のがん保険や医療保険には「先進医療特約」が付加されているものがあるので、上手に利用すればかなりの負担軽減が可能だろう。
そのような中で、近い将来、重粒子線治療が保険適用になる可能性も高い、という。そもそも先進医療の承認を受けていることは「将来的な保険導入のための評価を行うもの」という位置づけがされていて、重粒子線治療はすでにその条件を満たしている。
「ただし、いきなりすべての部位について保険適用ということではなくて、ほかに代替する治療がないようなものが優先されるでしょう。手術が難しいような場所の肉腫、骨盤や脊髄の近くにできたようながんなど、手術ができない、抗がん剤も効かないとなると非常に予後が厳しいので、こういったがん種から保険適用が実現できたらと思っています」
普及のため、小型化を実現

治療施設の拡大も、課題の1つだ。重粒子線の治療施設は、広大な敷地と高額な設置費用を要する。放医研が開発・建設したHIMACは、面積がサッカー場ほどにもなる巨大マシーンだ。
治療に使う重粒子はシンクロトロンと呼ばれる加速器で光速の近さまで加速させ、ビームとなって治療室まで送られ、腫瘍を狙い撃って照射されるが、シンクロトロンは1周130メートルもある。
しかし、最近、最新の技術により機器の改良が進み、面積を3分の1まで小さくすることに成功。製作コスト、運転コストも大幅に下げることができるようになってきた。
現在のところ、重粒子線治療ができるのは千葉県にある放医研と、兵庫県にある兵庫県立粒子線医療センターの2カ所だが、今年度中に、群馬県の群馬大学重粒子線照射施設でコンパクト化した装置による臨床応用が開始される予定だ。
また、さらに高精度の照射を実現するための3次元ビームスキャニング照射法や、360度から照射方向を自由に決めることのできる回転型照射装置の開発など、次世代照射システムの研究開発も進んでおり、これまで適用外だった症例への治療の拡大や、成績のいっそうの向上が期待されている。
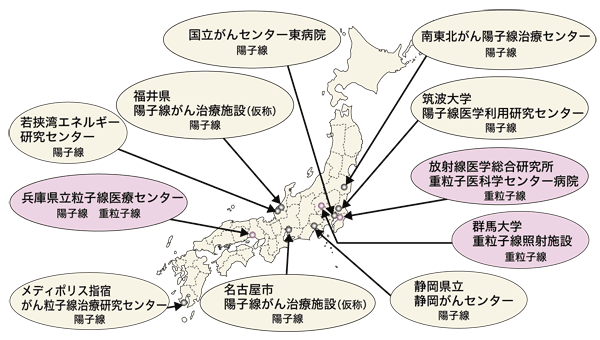
同じカテゴリーの最新記事
- 化学・重粒子線治療でコンバージョン手術の可能性高まる 大きく変わった膵がん治療
- 低侵襲で繰り返し治療ができ、予後を延長 切除不能膵がんに対するHIFU(強力集束超音波)療法
- 〝切らない乳がん治療〟がついに現実! 早期乳がんのラジオ波焼灼療法が来春、保険適用へ
- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術
- 大規模追跡調査で10年生存率90%の好成績 前立腺がんの小線源療法の現在
- 心臓を避ける照射DIBH、体表を光でスキャンし正確に照射SGRT 乳がんの放射線治療の最新技術!
- 2年後には食道がん、肺がんの保険適用を目指して 粒子線治療5つのがんが保険で治療可能!
- 高齢の肝細胞がん患者さんに朗報! 陽子線治療の有効性が示された
- 腺がんで威力を発揮、局所進行がんの根治をめざす 子宮頸がんの重粒子線治療
- とくに小児や高齢者に適した粒子線治療 保険適用の拡大が期待される陽子線治療と重粒子線治療


