「がん」を確定するには細胞診と組織診の2つの診断が不可欠 細胞の顔つきや組織のかたちで病変を鑑別する病理検査
病理医によるセカンドオピニオンを受診する
「組織診を受けても、病理の専門ではない医師が病理診断をすると、誤診が生じることがあります。1番問題なのはがんなのにがんではないと診断する例です。また、よその病院でがんと言われた患者さんの標本を私たちが見ると、がんではなかったという例もしばしばあります。ですから、病理の専門医のいない病院で診断を受けた場合はセカンドオピニオンが絶対必要です」
がんの診断に対するセカンドオピニオンは、がんを専門にしている病院で受けることが勧められる。その際はカルテのコピー、画像診断や腫瘍マーカーなどの検査資料などとともに、病理標本(細胞診あるいは組織診の検体)を持って受診する。
病理診断のセカンドオピニオンの受け方
「セカンドオピニオン」という言葉は一般的になりつつありますが、病理診断のセカンドオピニオンを求める患者さんはあまり多くありません。ですが病理診断は治療や予後に大きく影響してきます。がんかどうか、どのような性質のがんであるか、またどのように進行しているのか、病理診断によって治療法が変わるなど影響を及ぼすこともあり、予後にも関ってきます。がんと診断されたら、治療前に病理診断のセカンドオピニオンを受けましょう。
Q.病理のセカンドオピニオンはどこで受けたらいいの?
A.がんを専門としている病院や「病理科」がある病院を選びましょう。予約制をとっている場合が多いので、病院に問い合わせてから受けるようにしましょう。
Q.何を持っていけばいいの?
A.必ず必要なものは(1)診療情報提供書(主治医の先生にもらう)(2)血液検査結果(3)レントゲン画像(4)相談同意書・健康保険証など続柄を示す書類(相談者が患者以外の場合)。症例に応じて、(1)超音波検査画像(2)CT、MRI画像(3)病理標本(4)病理組織検査報告書―などが必要。
Q.相談料金はどのくらいかかるの?
A.保険外診療として全額患者さんの実費となります。病院によって違いがありますが、30分で1~2万円くらいという病院が多いようです。
迅速病理診断の態勢がない病院も
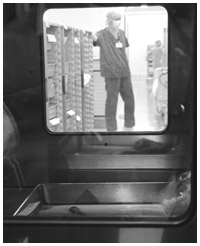
がんの迅速病理診断では、手術中に摘出した臓器の固まりの端っこ(断端)部分や手術した臓器に近いリンパ節の組織を顕微鏡で見て、がんが取りきれたかどうかを判断する。あるいは、腹膜に播種のようなものが認められれば、それを採取して細胞診でそれががん性かどうかを見極めたりする。その結果を執刀医に伝えることで、臓器をもっと大きく切除したり、リンパ節を郭清(切除)したり、手術をあきらめたりするケースが出てくる。
「執刀医の見た目だけではどこまでがんが広がっているかはわかりません。『まあ、このあたりまでだろう』という判断で手術を進めているのですが、迅速病理診断で思いのほかがんが広がっているといったことがわかる場合があるわけです。その場合は手術範囲を拡大したり、あるいはむしろ抗がん剤に切り替えたほうがいいと判断しなければならない場合も出てきます」
もっともすべての手術症例で迅速病理診断が行われるわけはない。癌研有明病院ではさまざまながんの手術を1日平均20例くらい、年間5000例近く行うが、そのうちの3分の2ほどが迅速病理診断の適用となる。「術中迅速病理診断は執刀医が必要だと思ったものだけ行います。たとえば『これ以上切ると動脈を傷つける』と判断するような場合は、そこで切除はやめなければなりません。このような例では迅速病理診断は必要がないと判断するわけです」



また、がんの手術が行われるすべての病院で、術中迅速病理診断が行われるわけではない。加藤さんは全国の300床以上を抱える大病院のうち、半分は迅速病理診断を行う態勢がないと見ている。
「当然がんの手術では迅速病理診断は行われるべきだと思いますが、がん専門病院などを除くと、病理のスタッフや迅速病理診断ができる態勢はあまり整っていないのが現状です。その結果、がんの手術を受けたけれど、がんを完全に切除しきれていないものが混じってくる恐れもあるでしょう」
病理医は手術が終わると摘出された臓器の組織を詳しく調べ、完全に病変部が摘出されているか、摘出前に予想していなかった病変は存在していないか、今後の治療はどうすべきか、などについて詳しくチェックする。癌研有明病院ではこうした結果は全て文書化されていて、電子カルテの情報として主治医と共有している。
次に病理標本の作り方だが、生検や手術で切除された組織は、血流が遮断されることにより自家融解、変性が生じるため、病理医は組織の形態を保存する固定(病理標本の作成)という作業を行う。病理標本の作り方はまず組織をホルマリン液に2~3日つけておく。この処理が終わると細胞中の脂肪を抜き、その部分にパラフィン(ろう)を浸透させてパラフィンブロックというものを作る。このブロックを3~4ミクロン(1000分の1ミリ)という厚さにスライスしてスライドガラスに貼り、プレパラート(顕微鏡観察用の標本)の形にして保存する。
「癌研では1945年の創立以来全部の患者さんの標本を残してあります。たとえばがんがだんだん治るようになって、第2のがん、第3のがんにかかる人も出てきましたが、それが再発なのかどうかといったことが過去の標本で確認できます。原発か再発かによって治療法が違ってくるので、昔のものを残しておくという意味があるわけです。
また、ずっと癌研を受診する家族や親族があるとすれば、その標本を調べて、昔からいわれてきた『がん家系』というものが本当にあるのかどうかといったことを調査するのに役立つかもしれません」
更に日進月歩のがん化学療法をより生かすうえでも標本が役立つ可能性がある。たとえば抗がん剤が効くがん、効かないがんがわかったり、新薬が登場した場合、過去に治療を受けた人の標本から、その人に合った薬かどうかを探ることもできる。
「進行がんの患者さんは『何か効く薬があるのでは』と探しています。
たとえば肺がんのイレッサ(一般名ゲフィチニブ)はEGFレセプターという増殖因子を標的にした分子標的薬ですが、『この増殖因子を持った人には、この薬が効く』という情報が増えているので、病理の情報が非常に役立つ可能性があるわけです。今後は病理診断の情報はDNAチップを用いた遺伝子情報の利用と並行してがんの治療法、予防に役に立つ場面がもっと増えるでしょう」
病理標本ができるまで


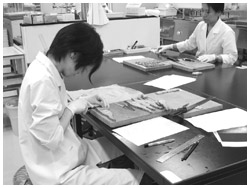

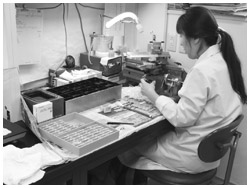

同じカテゴリーの最新記事
- 正確な診断には遺伝子パネル検査が必須! 遺伝子情報による分類・診断で大きく変わった脳腫瘍
- 高濃度乳房の多い日本人女性には マンモグラフィとエコーの「公正」な乳がん検診を!
- がんゲノム医療をじょうずに受けるために 知っておきたいがん遺伝子パネル検査のこと
- AI支援のコルポスコピ―検査が登場! 子宮頸がん2次検診の精度向上を目指す
- 「尾道方式」でアプローチ! 病診連携と超音波内視鏡を駆使して膵がん早期発見をめざす横浜
- 重要な認定遺伝カウンセラーの役割 がんゲノム医療がますます重要に
- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に
- 「遺伝子パネル検査」をいつ行うかも重要 NTRK融合遺伝子陽性の固形がんに2剤目ヴァイトラックビ
- 血液検査で「前がん状態」のチェックが可能に<img draggable="false" class="emoji" alt="⁉" src="https://s.w.org/images/core/emoji/11/svg/2049.svg"> ――KK-LC-1ワクチン開発も視野に


