早期発見にはあまり役立たない。腫瘍マーカーを賢く使おう がんのリスクを知る! 腫瘍マーカー早わかり
スクリーニング検査(がん検診)に使われる腫瘍マーカー
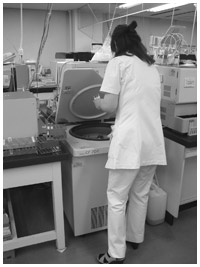
検体を遠心分離器から取り出している様子
腫瘍マーカーというと、血液を1滴とるだけでがんが診断できるというイメージがありますが、がん検診に使われている腫瘍マーカーとしてはPSAやペプシノーゲンなどがあります。
これらの腫瘍マーカーはがんを直接診断するわけではありませんが、特定の臓器に異常があるかどうかをチェックする目印になるという特徴があります。例えばPSAは体の中で前立腺だけ、ペプシノーゲンは胃だけで作られる物質です。
PSAは前立腺がんだけでなく、前立腺の炎症や前立腺肥大などの状態でも増えてきます。通常の検診では、PSAの値が4以上の場合、前立腺に針を刺してがん細胞があるかどうかを調べる生検検査が行われます。ところが、生検を行うと、70歳以上の男性では20パーセント以上の方に前立腺がんが見つかりますが、この内の多くは一生前立腺にとどまるおとなしいがんと考えられています。PSAは前立腺がんのスクリーニング検査として使われますが、がんの悪性度を診断することはできません。このような事情から、最近、アメリカでは75歳以上の高齢者ではPSAによる前立腺がん検診は行わないことになりました。
胃がん検診というとバリウム検査を思い浮かべる方が多いと思いますが、血液検査で胃がんをスクリーニングする方法があるのをご存知でしょうか? 胃がんの多くは慢性萎縮性胃炎(胃の粘膜が炎症によって委縮した状態)を背景として発生します。ペプシノーゲンは胃で作られる消化酵素ですが、血液中のペプシノーゲンの量を測定することで、慢性萎縮性胃炎の進み方を知ることができます。ペプシノーゲンには1と2という2種類があるのですが、1の値が低いなどの方に対して内視鏡検査を行うという方法があります。
一般の腫瘍マーカーは色々ながんで陽性になることが多いので、がんが疑われても存在する場所を決めることができない場合があるのですが、PSAやペプシノーゲンの検査は、特定の臓器に異常があるかどうかを知ることができるという特徴があり、検診に利用されています。
「将来、がんになるか」を診断する、研究の腫瘍マーカー
がん検診に使われる腫瘍マーカーの話をしましたが、今後出てくる可能性が高いマーカーは、「将来、がんになるかどうかを調べる」遺伝子のマーカーです。その1つが、BRCA遺伝子というものです。
BRCAとは乳がん(BReast CAncer)の略で、BRCA-1とBRCA-2という2つの遺伝子が、遺伝性乳がんと卵巣がんの発症に関わることが、最近わかってきました。米国で行われた結果では、この2つの遺伝子に変異がある人は、約60パーセントの方が70歳までに乳がんを発症すると報告されています。最近の研究で、日本人でもBRCA1/2の遺伝子検査で異常が見つかる人は、米国人以上に多いことがわかってきました。
この遺伝子の異常は卵巣がんの原因にもなります。米国では、BRCAの遺伝子検査で陽性だった人の約6割が、予防的な手術、つまり、がんになる前に卵巣や乳腺を予防的に切除する手術を受けたということです。予防的な手術については賛否両論あると思いますが、こうしたものが一種、究極の腫瘍マーカーであることは間違いなく、今後日本でも利用されるようになるでしょう。
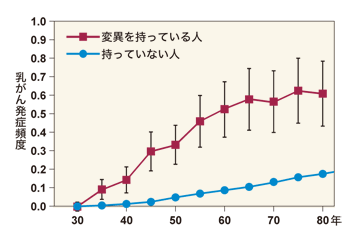
遺伝子研究が進んでいるのに、なかなか保険適用されない理由
がんが発生する過程で起きている遺伝子の異常によって生じてくる物質を利用して「腫瘍マーカーを開発する」というのが、最近の大きな動きです。そもそも、がんの原因は遺伝子の異常ですから、遺伝子を調べることで究極の腫瘍マーカーを開発できる可能性があります。
最近、日本で保険適用になったのが、抗p53抗体です。これはがん発症を抑制する「p53がん抑制遺伝子」が作り出すタンパク質で、ストレスがかかると正常な細胞でも作られますが、非常に寿命が短く、すぐに分解されてしまいます。しかし、がん細胞ではp53遺伝子に突然変異が起きるため、p53タンパク質が分解されず、蓄積されていきます。
すると生体はこれを異物とみなして、免疫反応がおきる結果、このタンパク質に対する抗体が血液中に検出されるようになります。抗p53抗体は早期の肺がんや食道がんなどの約30パーセントの症例で検出できるようになりました。
また、DNAチップを使うと、1度に数千個以上の遺伝子の変化を調べられるので、がんに特徴的な遺伝子の変化を網羅的に調べることができるようになっています。
このように、基礎研究はさかんになりましたが、実際に保険の適用になる腫瘍マーカーは滅多にありません。腫瘍マーカーが最終的に保険適用されるためには、きちんと品質管理されて製造された試薬を使った臨床試験を行う必要がありますが、抗がん剤に比べると検査用試薬の保険点数は非常に低いので、企業は新しい腫瘍マーカーの開発にあまり積極的ではありません。
血液を調べるだけでがんをスクリーニングしたり、病気の進み方を診断する、あるいは治療方針を決めたり、治療効果を判定できるということは、個々の患者さんに最適な治療を提供すること、さらに医療費の無駄を省くことにつながっていきます。
以上、腫瘍マーカーの概要と現状をお話しましたが、大事なのは、そのメリットとデメリットをよく理解し、目的に合った腫瘍マーカーを使うことです。
腫瘍マーカーは、早期発見という点では決して精度の高い検査ではありません。ただその一方で、いったんがんと診断された場合、腫瘍マーカーにできることはたくさんあります。多くの皆さんが正しい認識をもち、上手に利用していただければと思います。
同じカテゴリーの最新記事
- 正確な診断には遺伝子パネル検査が必須! 遺伝子情報による分類・診断で大きく変わった脳腫瘍
- 高濃度乳房の多い日本人女性には マンモグラフィとエコーの「公正」な乳がん検診を!
- がんゲノム医療をじょうずに受けるために 知っておきたいがん遺伝子パネル検査のこと
- AI支援のコルポスコピ―検査が登場! 子宮頸がん2次検診の精度向上を目指す
- 「尾道方式」でアプローチ! 病診連携と超音波内視鏡を駆使して膵がん早期発見をめざす横浜
- 重要な認定遺伝カウンセラーの役割 がんゲノム医療がますます重要に
- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に
- 「遺伝子パネル検査」をいつ行うかも重要 NTRK融合遺伝子陽性の固形がんに2剤目ヴァイトラックビ
- 血液検査で「前がん状態」のチェックが可能に<img draggable="false" class="emoji" alt="⁉" src="https://s.w.org/images/core/emoji/11/svg/2049.svg"> ――KK-LC-1ワクチン開発も視野に


