従来の検診と組み合わせ効率的な治療方針を立てる 将来の危険性を予測する試みの子宮頸がんの新しい診断
真の危険型HPVは16型、33型、52型
ここで子宮頸部異形成とHPVとの関連について、荷見さんはじめ同病院婦人科のスタッフが行った研究結果を紹介します。
研究に先立ち、荷見さんたちは異形成と診断された183例のHPVの型を検出しました(表3)。子宮頸がんでは16型、18型、31型、33型、52型、58型が多く検出されますが、異形成ではさまざまな型が検出されました。これらの結果から、「子宮頸部の上皮にHPVが感染することにより異形成が発生し、異形成のうち高~中危険型のHPVに感染していくケースが高い率でがん化していく」との仮説を立てました。
| HPVの型 | 例数(%) | |
|---|---|---|
| 中~高危険型 | 16 | 29(15.8) |
| 18 | 9(5.9) | |
| 31 | 1(0.5) | |
| 32 | 0(0) | |
| 33 | 4(2.7) | |
| 52 | 14(7.7) | |
| 58 | 22(12.0) | |
| 低危険型 | 35 | 0(0) |
| 61 | 2(1.0) | |
| 56 | 8(5.4) | |
| その他 | 94(50.4) | |
| 計 | 183 |
次に、この仮説を検証するため、軽度・中等度異形成を215例について、5年以上の期間、生検や治療は行わず、細胞診のみで自然観察を行いました。
| 消失(Regression) | 149(69.3%) |
|---|---|
| 不変存続(Persistence) | 52(24.2%) |
| 増悪(Progression)* | 14(6.5%) |
[表5 HPV型別の増悪化の危険度]
| 型 | 16型 | 33型 | 52型 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 倍率 | 7.95倍 | 15.48倍 | 17.44倍 | 1倍 |
結果は、「病変消失」が149例、「不変存続(軽度・中等度異形成のまま存続)」が52例、「増悪(高度異形成以上に進行)」が14例でした(表4参照)。なお、増悪例のうち浸潤がんに進行したものはありませんでした。
このうち増悪した14例中のHPVの型を調べると、16型が4例、33型が2例、52型が5例、52型が5例、58型が1例、その他2例でした。18型では12例中増悪したものはありませんでした。
これらの結果から、増悪化の危険度について示したのが表5です。危険度の低い「その他」に比較して、16型では7.95倍、33型では15.48倍、52型では17.44倍となっています。これらの研究結果から、荷見さんらは「子宮頸がんに対して真に高い危険性を持つHPVは16型、33型、52型」との結論を出しました。
研究結果について、荷見さんは次のように語ります。
「これらの型は『真の高危険型』とも言うべきもので、がん組織から検出される頻度の高さから見た危険型と違っていることがわかります。注目すべきは52型です。欧米ではほとんど見られないため、欧米では低危険型とされていますが、日本では感染頻度が高いので中危険型とされています。しかし、今回の研究結果から見れば、増悪する可能性は16型より高いので、危険性は高いのです。ほかにも、欧米では高危険型に分類できる18型は腺がんでは約50パーセントに見つかりますが、扁平上皮がんに限ると話が違ってきます。当院で調べた結果、異形成で18型が検出されたケースでがん化したものは1例もなく、すべて治療せずに自然消失しました」
このように調査、研究が行われた地域、国によって高危険型に分類されるHPVの型が異なる可能性があります。日本人にとっての高危険型HPVを見極めるためには、さらなる日本独自の研究が必要です。
HPV-DNA診断導入の2つの目的
現在、子宮がんの検診で軽度・中等度異形成と診断されると、数カ月ごとに細胞診や組織診を行いながら経過観察していくのが一般的です。これらは細胞や組織の形の異常から病気を診断しようとする方法で、形が異常であれば、その性格にも異常があるという考えに基づいています。
「しかし、細胞診や組織診で同じ程度の異形成と診断されても、がんになっていくものもあれば、自然消滅してしまうものもあります。この違いは形のうえからだけでは判別できません。しかし、現状では、軽度・中度異形成と診断されると、同様の割合、回数で診断に行き、同様のやり方、条件で経過観察を続けることになるのです」と荷見さん。
そこで、荷見さんたちは、従来と同じような検診が必要な患者さんと、病変消失の可能性が高く検診を間引いてもかまわない患者さんとに分けることができないかと考えました。
ここで役立つのがHPVの情報です。
「HPV–DNA診断を導入した目的の1つは、将来への危険性によって患者さんを分類すること。本来なら必要のないかもしれない検診を受ける必要がなくなり、患者さんの負担が減るだろうと考えています。2つ目は、病気の潜伏的な進行の見過ごしを防ぐこと。従来の方法で病変が消失しても、相変わらず高危険型のHPVが続けて見つかる場合、念入りに経過観察していく必要があると判断できるかもしれません」
HPVの型による経過観察期間の違い
現在、同病院では、軽度・中等度異形成と診断され、HPV–DNA診断で「真の高危険型」である16型、33型、52型が見つかった場合、3カ月ごとの検診を行っています。31型、32型、58型の場合は4~5カ月ごと、その他の型のものは6カ月ごとの検診です。18型の場合、扁平上皮がんが発生する頻度は低いのですが、腺がんが発生する可能性が高いため3カ月ごとの検診となります。腺がんの場合、細胞診でも見逃しやすく、コルポスコープ(腟拡大鏡)でも所見に乏しいので、念入りに行う必要があるそうです。
従来の検診と組み合わせることで有用性を発揮
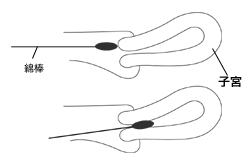
[子宮頸部の試験切除鉗子]
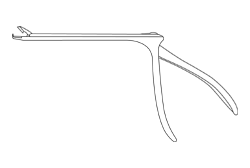
ただし、注意したいのは、高危険型のHPVが見つかったとしても、確実にがん化するわけではないということです。最もがん化する率が高いと考えられている16型でも、約20パーセントにしかがん化は起こりません。また、「真の高危険型」と分類した16型、33型、52型が見つかった場合でも、がん化するのは、6~7人に1人という割合です。そのため、高危険型のHPVが見つかった場合でも、経過観察のみで、治療を行うことはありません(*注3)。
「高危険型HPVが見つかったという理由だけで手術を行ったとしたら、それは行き過ぎた治療です」と荷見さん。
現在、同病院では、同じ型のHPVを持っているのにがん化する病変と自然治癒する病変があるのはなぜか、その違いを明らかにする研究に取り組んでいるところです。
最後にHPV–DNA診断の意義について、荷見さんは次のように語りました。
「HPV–DNA診断は、現在のところ、その結果だけで治療方針が決定される検査ではありません。細胞診、組織診と組み合わせ、HPV–DNA診断の結果を参考にしながら、経過観察のための検診を効率的に行い、適正な検診間隔を考えていくのが最良の治療方針と考えています。また、このように効率的に検診を行えば、医療費の節約に大きく役立ちます。大学病院や地域の基幹病院など、病理診断を行っているところであれば実施できる検査です。ぜひ保険診療へ移行することを望みます」
*注3 高度異形成の場合、子宮部円錐切除術や、病巣にレーザーを照射して消滅させるレーザー療法が行われます
*現在、がん研有明病院では外来にてHPV–DNA診断を実施中(費用1万2,200円)。
お問い合わせはこちらまで
電話03(3520)0111 ホームページ
同じカテゴリーの最新記事
- 正確な診断には遺伝子パネル検査が必須! 遺伝子情報による分類・診断で大きく変わった脳腫瘍
- 高濃度乳房の多い日本人女性には マンモグラフィとエコーの「公正」な乳がん検診を!
- がんゲノム医療をじょうずに受けるために 知っておきたいがん遺伝子パネル検査のこと
- AI支援のコルポスコピ―検査が登場! 子宮頸がん2次検診の精度向上を目指す
- 「尾道方式」でアプローチ! 病診連携と超音波内視鏡を駆使して膵がん早期発見をめざす横浜
- 重要な認定遺伝カウンセラーの役割 がんゲノム医療がますます重要に
- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に
- 「遺伝子パネル検査」をいつ行うかも重要 NTRK融合遺伝子陽性の固形がんに2剤目ヴァイトラックビ
- 血液検査で「前がん状態」のチェックが可能に<img draggable="false" class="emoji" alt="⁉" src="https://s.w.org/images/core/emoji/11/svg/2049.svg"> ――KK-LC-1ワクチン開発も視野に


