ROS1融合遺伝子陽性肺癌に対する治療戦略
[2024.12.1] 取材・文●「がんサポート」編集部
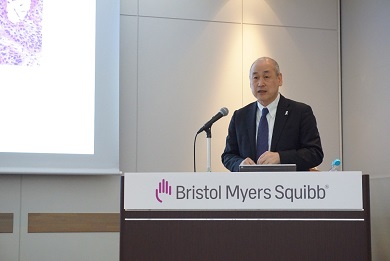
2024年11月14日、ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社主催で、「ROS1融合遺伝子陽性非小細胞肺癌についてのメディアセミナー」が開催。国立がん研究センター東病院の副院長・呼吸器内科長の後藤功一さんによる「ROS1融合遺伝子陽性肺癌に対する治療戦略」と題したご講演がなされた。また、患者の立場から、吉野振一郎さんが、病歴から現在の治療への取り組みの姿勢をご講演された。
「ROS1融合遺伝子陽性肺癌に対する治療戦略」

肺がんは、厚生労働省「人口動態統計」2021年では、がん関連死亡原因の1位であり、全がん関連死の約38万人のうち、約20%にあたる76,212人(男性 53,278人、女性 22,934人)が肺がんによる死亡です。さらに、非小細胞肺がんは、肺がん全体の約85%を占めています。
後藤さんは、肺がんの罹患数と死亡数について、依然として増加傾向を示していますが、死亡数は、2000年過ぎあたりからプラトーになっているとし、その理由について、喫煙率の低下の影響もあるかもしれないかが、主なものは、治療薬の開発にあるという。
さらに、がんは遺伝子の変異で発症し、肺がんで代表的なドライバー遺伝子は、EGFRであり、それはがんの発生から増殖、生存に直接関わっている遺伝子であるという。
EGFR遺伝子変異からEGFRタンパクの活性化→過剰な細胞増殖シグナルを出し、がん化にアクセルに影響を及ぼし、がんの病巣を増殖させるシステムであるとした。
現在、進行肺がんの対しての薬物療法として抗がん薬、分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬の3つがあり、なかでも分子標的薬のメリットとして、身体への負担が比較的少ない、特定のがん細胞の遺伝子変化に効果ありとし、デメリットについて、特定の遺伝子変化がなければ使用できない点をあげました。
日本肺癌学会の診療ガイドライン2024年版の中でも、Ⅳ期非小細胞肺がんのドライバー遺伝子変異/転座陽性の治療方針でも、各*ドライバー遺伝子(+細胞障害性抗がん薬)に対する標的療法が記されております。2023年版の診療ガイドラインでもROS1融合遺伝子陽性にROS1-TKIは勧められるか?に対して、推奨としてROS1-TKI単剤療法(クリゾチニブ(商品名:ザーコリ)、エヌトレクチニブ(商品名:ロズリートレク)のいずれかを行うよう推奨。と記載されています。
2024年版のガイドラインには、今年9月承認を受けましたレポトレクチニブ(商品名:オータイロ)が追記されています。同薬の効能または効果は、ROS1融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺がんです。
非小細胞肺がんの中で、ROS1融合遺伝子の肺がんは、1~2%に存在する希少ながんです。
最も多いのが、EGFR遺伝子です。しかし、後藤さんは、患者さんは少なくても、その患者さんによりよい治療薬を開発し、新しい治療薬として使用していくことが我々医師の役目とあると強調されました。
オータイロのTRIDENT-1試験では、他のROS1-TKIの治療歴のない患者さんの奏効率は77.8%、1種類のROS1-TKIおよび、1種類の白金系抗がん薬による治療歴のある患者さんの奏効率は、43.5%、2種類のROS1-TKIの治療歴のある患者さんでは、29.4%という結果であった。主な副作用は、めまい、味覚障害、肝機能障害などでありますが、休薬、減量でコントロール可能であり、副作用のマネジメントが必要であるとした。
まとめとして、後藤さんは、非小細胞肺がんにおけるROS1融合遺伝子の頻度は約1%と希少であり、マルチ遺伝子解析を用いて陽性の患者さんを同定する必要があるとし、ROS1融合遺伝子陽性肺がんの既承認薬のクリゾチニブやエヌトレクチニブは、有効な治療薬でありますが、PFS(無増悪期間)が15~16か月で耐性化の克服が必要。
さらに、肺がんの治療を受けることになったら、「肺がんについて勉強する」、「病状をしっかり把握する」、「病状に合う標準的治療を尋ねる」、「医師の説明を聞きながら、納得のいく治療を選択する(治療方針の決定に参加する)」、「遺伝子変化の有無を確認する」をあげて結んだ。
*ドライバー遺伝子:EGFR遺伝子、ALK融合遺伝子、RET融合遺伝子、ROS1融合遺伝子、BRAF遺伝子、MET遺伝子、KRAS遺伝子、HER2遺伝子、NTRK融合遺伝子


