患者の特性に合った乳がんの個別化治療 過剰な治療をなくし、治療の精度を高める方向へ加速
個別化と低侵襲の大きな流れ

温存療法の普及で乳房全摘が少なくなってきた

このようにみていくと、乳がん治療の大きな流れは、術前の薬物療法でがんを小さくして乳房を温存し、センチネルリンパ節生検によって不必要なリンパ節郭清を行わない「個別化と低侵襲」といえるだろう。
それなら、今後、乳がんの治療はすべて乳房温存となるかというと、そう簡単には切除手術はなくならないようだ。乳房温存療法にしても切除手術には変わりはない。
そこで、手術に変わる低侵襲の治療として注目されているのがラジオ波など「アブレーション(ablation)」と呼ばれる治療法だ。「アブレーション」とは「取り除く、切除する」という意味だが、医学的には一般に「焼灼(焼くこと)」を指す。
ラジオ波を用いた治療は「ラジオ波焼灼(熱凝固)療法」と呼ばれ、全身麻酔下で、医師がエコーでモニターしながらラジオ波による熱を腫瘍に伝えるニードルを刺入し、ラジオ波を流すことでニードルの周囲を90℃まで上昇させ、がん細胞を死滅させる。乳がんを切らずに治す、より低侵襲の治療法として、この治療を積極的に臨床に取り入れている施設もある。国立がん研究センター東病院では現在、臨床試験を行っているところだが、井本さんはいう。
「温存手術といっても切除しているわけですが、しこりがかなり小さくてそこに限局しているという場合、そのままにしておく方法もありますが、もう1つ、ラジオ波で焼灼する方法があるわけです。ですから、ラジオ波は腫瘍の範囲が限局している人が対象となります。ただ、単に切らなくてよくなっただけではなく、切除する今の治療法と比べて、同等の治療法であると証明されなければいけません。そこで現在、臨床試験を行っている段階です」
ただし、まったく切除しないわけではなく、同病院では、ラジオ波で焼灼したあと、ちゃんと焼けているかどうかを確認するため、患者の同意を得て切除を行い、治療効果を確かめている。一部の施設では、これを省いて切除を行わないところもあるという。
臨床試験の中間解析では、評価ができた16例のうち、14例ではがんの消失が確認されているという。最終結果が待たれるところだ。
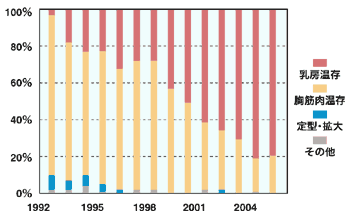
[リンパ節郭清が減少]
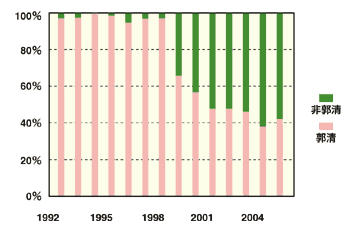
難点がある集束超音波療法

また、ラジオ波のほかにも、超音波を用いた「集束超音波療法」という治療法もある。これは、別の記事で取り上げているのでそちらを参照してほしいが、国立がん研究センター東病院では行われていない。
この治療法の難点は、装置が高価であるため、自由診療でかなり高額の治療費を払わなければならないこと。また、この治療の原理は太陽の光を1点に集中させて熱を集める虫めがねと同じで、ズレることなく超音波を1点に集めなくてはいけないので、患者は一定時間じっと動かずにいる必要がある。
ラジオ波や超音波以外にも、海外ではマイクロ波や超低温(凍結療法)を使った治療法が行われているが、日本ではまだ実施されていない。
東病院では、ラジオ波による治療は2センチ以内のがんが対象。乳房温存手術を行って、きれいにがんを取り除いたと思っても、断端といって、がん細胞を完全に取りきれていないケースが10パーセント以上あるという。そこで、乳腺の管の中に残っているような小さなしこりを、ラジオ波で焼灼すれば、あとは放射線などの治療を患者に提案することができるという。
やがて手術も生検もいらなくなる日が…
いずれにしろ、乳がんの手術は、より患者の負担の少ない低侵襲の方向にあるといえる。乳房温存にセンチネルリンパ節生検に加え、温存の次にくるのが焼灼であり、これはまさに切除をやめて、乳房にメスを入れないという治療法だ。さらに、センチネルリンパ節生検も、将来的にはやらなくてもいい時代がくるかもしれない。
「もともとのしこりが非浸潤がんであれば転移しないわけです。ところが、非浸潤がんがすべて非浸潤がんかどうか分からず、一部が浸潤がんだったりします。実際、非浸潤がんと思ってセンチネルリンパ節生検をしてみると、4パーセントとか、場合によっては10パーセントぐらいの確率で転移があります。何らかの方法で非浸潤がんだという確証が得られれば、センチネルリンパ節生検も行わずに、組織診とか、画像をみて判断できるようになるでしょう」
今後、個別化治療の流れはどのような方向にいくのだろうか。井本さんにまとめていただいた。
「乳がんの患者さんに対して、手術だけではなく、補助療法としての薬物療法がかなり進歩してきました。とくに乳がんは薬剤や放射線の感受性が高いので、以前のように乳腺を一律に大きくとることをしてなくても、がんの範囲が分かれば必要十分の範囲を切除するだけでいいというので、温存へと向かっています。
それと相まって、薬物療法にしても、たとえばがんの性質とか、転移の有無とか、ホルモンの感受性とか、最近はHER2の感受性などによって、用いる薬剤の違いも明らかになってきています。さらに、手術前に薬物療法を行うことで、がんが消えてしまえば、やがては手術もいらなくなるかもしれません。
手術にしても、これに代わるものとしてラジオ波や集束超音波なども出てきています。ただし、小さなしこりであれば小さな切除で済むかもしれない。だから、ラジオ波や集束超音波でなければダメということではなく、切除を選択することもあり得るでしょう。
センチネルリンパ節生検に関しては、今ようやく一般医療になったところで、今後少なくとも5年から10年はこれが行われ、郭清するかどうかを決めることになると思います。
その次としては、画像診断が進歩してミクロのレベルまで分かるようになれば、何もしないとか、あるいは、ここに2ミリぐらいの転移があるが、郭清しなくても放射線だけでいい、となるかもしれません。ヨーロッパの研究グループが、センチネルリンパ節生検をして小さな転移があった場合、郭清と放射線との有効性を比較する試験を行っていて、数年後には結果が出ます。ただし、個別化といっても、効く確率が高くなければいけません。その点をどうクリアするかも今後の課題と思います」
同じカテゴリーの最新記事
- 高濃度乳房の多い日本人女性には マンモグラフィとエコーの「公正」な乳がん検診を!
- がん情報を理解できるパートナーを見つけて最良の治療選択を! がん・薬剤情報を得るためのリテラシー
- 〝切らない乳がん治療〟がついに現実! 早期乳がんのラジオ波焼灼療法が来春、保険適用へ
- 新規薬剤の登場でこれまでのサブタイプ別治療が劇的変化! 乳がん薬物療法の最新基礎知識
- 心臓を避ける照射DIBH、体表を光でスキャンし正確に照射SGRT 乳がんの放射線治療の最新技術!
- 術前、術後治療も転移・再発治療も新薬の登場で激変中! 新薬が起こす乳がん治療のパラダイムシフト
- 主な改訂ポイントを押さえておこう! 「乳癌診療ガイドライン」4年ぶりの改訂
- ステージⅣ乳がん原発巣を手術したほうがいい人としないほうがいい人 日本の臨床試験「JCOG1017試験」に世界が注目!
- 乳がん手術の最新情報 乳房温存手術、乳房再建手術から予防的切除手術まで
- もっとガイドラインを上手に使いこなそう! 『患者さんのための乳がん診療ガイドライン』はより患者目線に


