- ホーム >
- 連載 >
- 中医師・今中健二のがんを生きる知恵
第10回 なぜ乳がんになるの? 再発予防法
「足のむくみ&冷えのぼせ」が重なったとき
とはいえ、足のむくみが続いたら乳がんになる、というわけでは決してありません。では、どういうときに乳がんになるのか?
それは、足のむくみに加えて、冷えのぼせの状態が続いたとき。ホットフラッシュや熱っぽいといった状況が、足のむくみとともに長く続いているときは、乳がんができやすい体質になっていると考えられます。
このときに現れやすい他の症状としては、顔に大量の汗をかく、前頭葉とくに眉間やこめかみ辺りの頭痛、口内炎がよくできる、突発性難聴、高音の耳鳴り、動悸、ヘルペス、扁桃腺・甲状腺が腫れる、痰が絡むような咳が続く、胸がつかえる、吐き気がするなど。こうした症状に覚えがあるならば、足のむくみから冷えのぼせを起こしつつある状態と思って、対策をとることをお勧めします。
ちなみに、これらの症状を並べると、更年期障害を思い浮かべるかもしれませんが、そもそも更年期障害なんていう病はないのです。「更年期障害は女性ホルモン不足が原因」などとも言われますが、これだけ栄養満点の時代に女性ホルモン不足もそうそうありません。単に下半身がむくんで、気血が上半身だけを巡っていることが原因の場合がほとんどです。
少し話が逸れましたが、足のむくみが続き、冷えのぼせから熱っぽい状態が続いたとき、症状がどこにどう出てくるかは人それぞれ。その人の弱い部分に出てきます。その1つに乳がんがある、と考えてください。
乳がんの自己診断法
ここで、乳がんの自己診断法に触れておきましょう。
右手で左乳房を、左手で右乳房を、それぞれ親指とその他の指で挟み込むようにマッサージ。しこり、ツッパリ感、痛みがないかをチェックします。肌に触ったときの感覚が部分的にカサカサしていたり、ツブツブ感がないかといった皮膚の異変も見落とさないように。その際、乳房の真ん中から外側の、とくに上側を中心に行いましょう。
乳房にしこりなどの異変を見つけたときは、迷わず乳腺外科へ行ってください。早期ならば、そこだけ切除すれば終わることも多いです。
繰り返しになりますが、栄養過多が原因で胃の経絡上で気血が溢れたとき、最初に溜まりやすい場所が乳房です。胃の経絡上で発生するがんは、胃の経絡が通る近辺すべてで起こり得ます。脳、喉、食道、肺、胃はもちろん、さらに下に流れたら腎臓や膀胱でも発生します。その中で乳房は、母乳を溜めるという本来の役割上、いちばん最初に気血を濃縮して塊にしやすい、つまり、がんができやすい場所ということです。
となると、早期の乳がんならば、胃の経絡上で起きるがんのいちばん最初の小さいうちに見つけることができたということ。もちろん早期でも、「がん」と言われたらショックです。でも、そこは気持ちを切り替えて、早い段階で見つけることができて、小さな切除ですんでよかった! と思ってほしい。
乳がん治療後に考えたいこと
さらに言えば、切除して治療を終えたら、あなたはもうがん患者ではありません。それ以降は、「食べ過ぎていた」とか「足がむくみがちだった」といった乳がんを招いたかもれしない生活習慣や体質についての知識を持ち、その後の生活を考えていきましょう。
血液検査の値が高い方、食べ過ぎは今すぐやめましょう。とくに肉や糖質(ご飯やパン)、菓子類の摂り過ぎはNGです。また、体のためと栄養価の高い食品ばかり偏って食べるのもよくありません(食べ過ぎについては、第1回 病は「胃」から始まるを参照)。
足のむくみは、なぜ起きたのでしょうか? 水分を摂り過ぎていませんでしたか? 世間的には水分摂取は大いに推奨されますが、飲み過ぎはむくみのもとです。日頃から自分の舌を観察して、水分の摂り過ぎに気をつけてください(舌診については、第1回 病は「胃」から始まるを参照)。
また、「足のむくみ」タイプは、「栄養過多」タイプとは対照的に、肉や糖質を避け過ぎて、野菜や果物ばかり選んできたことで、水分を多量に摂取する食事になっていることも考えられます。肉や糖質の粘性も、気血を循環させるためには、適度に必要ということです。
さらに、どちらのタイプにも言えることですが、運動不足になっていませんか? 長時間、座り仕事の方はとくに注意が必要。ウォーキング、スクワット、ダンス、何でもいいので、日々の生活に運動を取り入れましょう。
とくに、足のむくみには、ヨガや太極拳など、足を挙げるポーズがおすすめです。運動が難しかったら、仰向けに寝て膝を曲げてカエル足にし、股関節を片方ずつゆっくり回したり、足のむくみがとれるまで足を挙げて壁に預け、振ってみるだけでも良いでしょう。ご自身の方法で、足のむくみを取りましょう。
乳がんの転移をどう考える?
最後に、転移についても触れておきます。
乳がんは、肺、脳、骨への転移が多いですね。骨転移は腰椎や大腿骨が多く、10年以上経っての転移もあります。実は、これらもすべて経絡で説明がつきます。
肺も、脳(前頭葉)も、腰椎や大腿骨もすべて、胃の経絡が通る近辺にあります。乳がん治療を終えて治癒しても、もし、それ以前の生活習慣を変えずに過ごしていたら、胃の経絡内は、いつしか乳がんが発生したころと同じような状態になり、やはり、どこかに気血が溜まり、蓄積されていくことになります。それがまた乳房ならば再発、乳房以外の場所ならば転移と呼ばれるわけです。
乳がんになったということは、当時は胃の経絡のどこにがんが発生してもおかしくない状態だったということです。乳がんをきっかけにそのことを理解し、今後は食事内容を考えたり、運動を取り入れたりして生活習慣を見直すことができれば、体内環境が少しずつ変わっていくでしょう。それは、乳がんはもちろん、がん自体が発生しにくい体になることに繋がるのではないでしょうか。
次回は、「胃がん」について、その発生メカニズムと養生法をお伝えしたいと思います。(次号へ続く)
著書紹介
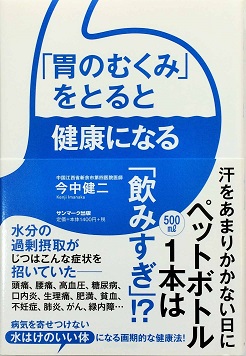
「胃のむくみ」をとると健康になる
今中健二著 サンマーク出版 1,400円(本体)
「水は飲むほど体にいい」に警鐘を鳴らす1冊。過剰な水分摂取が胃をむくませ、そのむくみが体中に伝わって不調が現われるのだという。その症状は、頭痛、腰痛、高血圧、糖尿病、生理痛、肥満、貧血、不妊症、肺炎、がん、緑内障など多岐に渡る。中国伝統医学のプロフェッショナルが教える究極の健康法
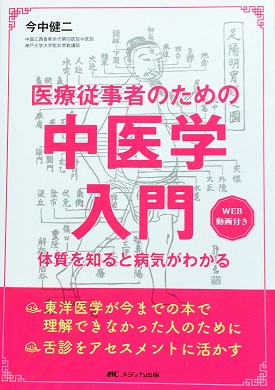
医療従事者のための中医学入門
今中健二著 メディカ出版 3,000円(本体)
整体観、陰陽五行学説、弁証理論など、複雑に思える中医学の概念を分かりやすく明快に解説。医療従事者はもちろん、家族の健康を気遣うお母さんたちにも知ってほしい中医学の知識を伝える。舌や顔色でわかる体質や対処法、それに合わせた食事や温度調整など、実際のケアに役立つ知識をまとめた1冊


