抗がん剤ごとの副作用を理解し、対策を講じながら治療を続ける 肺がん化学療法の副作用対策
エビデンスに基づく吐き気、骨髄抑制、しびれ対策
抗がん剤治療の副作用とその出現時期
また、最近は副作用への対処が進んできているので、安心して治療を受けましょう
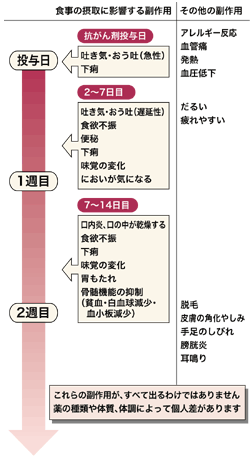
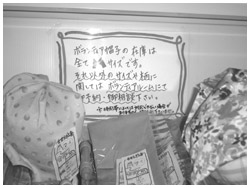
抗がん剤の副作用が出る時期は、大体決まっています。
「抗がん剤の投与直後にはごく稀にアレルギー症状、初日から3、4日間は吐き気や食欲低下、10日から2週間ほどで、白血球や血小板の低下、脱毛、しびれなどが起こります。抗がん剤をやめると副作用もおさまるのが普通ですが、しびれなどは長く続くこともあります。副作用の出方は非常に個人差が大きいものですが、大体1コース目で抗がん剤の効果とともに副作用の出方もわかってきます」(右図参照)
吐き気
現在、日本で使える吐き気止めは、5-HT3受容体拮抗剤(注1)とステロイドの併用療法で、抗がん剤投与前に予防的に点滴で投与するのが普通です。
「抗セロトニン剤の5-HT3受容体拮抗剤が1990年前半に登場し、シスプラチンなどによる初日の強い吐き気は驚くほど軽減されました」。これは、吐き気を脳に伝えるしくみを遮断する薬ですが、抗がん剤投与後2日目以降の「遅発性」の吐き気にはあまり効果がないといわれています。アレルギーと吐き気予防を兼ねるステロイドも十分ではないとか。
「欧米では一昨年から、遅発性の吐き気にも効果があるNK-1阻害剤のアプレピタント(商品名エメンド)という新薬がガイドラインで推奨され、使われています。日本でも臨床試験が終了したので、数年後には使えるようになるでしょう」
現在、遅発性の吐き気に対しては、中枢神経に作用する薬剤(注2)やドーパミン受容体拮抗剤(注3)などが、症状に合わせて補助的に使われています。経口剤は、抗がん剤投与の30分から1時間前、または吐き気が起こる前から早めに飲むのがおすすめです。
注1 グラニセトロン(商品名カイトリル)、オンダンセトロン(同ゾフラン)、アザセトロン(同セロトーン)など
注2 ハロベリトール(商品名セレネース)など
注3 メトクロプラミド(商品名プリンペラン)など
骨髄抑制
抗がん剤は、がん細胞と同時に分裂速度の速い正常細胞にもダメージを与えます。血液の成分を作っている骨髄もその1つで、白血球や血小板の減少、貧血などが起こります。
●白血球・好中球減少 白血球の5~7割を占める好中球は、細菌等から体を防御しています。極端に減ってくると感染症にかかりやすくなりますから、人ごみを避けるなどの注意が必要です。「貧血と違って症状はなく、感染さえしなければそれ自体が体に影響するわけではありません。好中球減少には、日本のガイドラインに沿ってG-CSF製剤(顆粒球コロニー刺激因子)を使用するのがよいでしょう。G-CSFは薬剤性の肺炎を起こすこともあるので、必要なときにだけ使います」。
発熱があったら細菌感染が懸念されますから、医療者に伝えましょう。細菌感染には、抗生剤で対処します。 「現在日本で使われているG-CSFは1日1回数日間皮下注射する短期型ですが、米国では1レジメンに1回の注射ですむ長期作用型製剤が承認され、日本でも臨床試験中です」
●血小板減少 「血小板は通常1マイクロリットルあたり15万ほどですが、2万以下になった場合は血小板輸血が必要です」出血しやすくなるため、ひげは電気かみそりで剃るなど刃物の扱いややけどなどに気をつけましょう。
●貧血 赤血球の減少により体内に酸素を運びにくくなり、疲れやめまいが起こるほか、心臓への負担がかかります。自覚症状があったときも検査で確認し、高度な貧血がみられたら輸血を検討します。
「欧米では、腎不全等に用いられるエリスロポエチン製剤(商品名エポジン)が貧血にも効果があると確認され、使われています。日本でも承認が期待されます」
腎機能障害・肝機能障害
「腎臓機能はクレアチニンという値で判断します。むくみが現れたときはかなり腎臓機能が悪化している可能性があります。腎臓機能が低下してきたら、水分を点滴で追加して尿として排泄させるのが基本です。家庭でもお茶などで水分を補給しましょう。「沈黙の臓器」といわれる肝臓は、自覚症状なしに徐々に悪化しやすいので、肝機能を示すGOT、GTPなどの数値の変化にも注意が必要です。肝臓機能障害には、肝臓庇護剤を使います」
しびれ
手足の先がジンジンする、ピリピリするなど、パクリタキセル使用時に起こりやすいしびれの症状は、医療者にとっても課題の1つだそうです。
「私たちは、関節炎などに使われる鎮痛薬のCOX-2阻害剤(商品名モービック、セレブレックス等)でパクリタキセルによるしびれが軽減できる可能性があると発表し、臨床で使用しています。また、各種の鎮痛薬やグルタミン、漢方薬などで効果が得られたとの報告もありますが、どの方法も比較試験が行われているわけではなく、決定打ではないのが実情です」
しびれでお悩みの方は、担当医と相談して、これらの方法やクルミを転がすなどの方法を試してみるのも1案です。
「私たちはピアニストや大工さんなど、手足がしびれると困る方には他のレジメンを検討しています。現在、世界中でしびれをとる薬剤の治験中です」
イレッサの副作用
●皮疹 イレッサを服用中は、ニキビ状の皮疹や全身の発疹、手の指先が真っ赤に腫れるなど、高頻度に皮疹(イレッサ疹)が起こります。
「皮疹が出たほうが治療効果も高いといわれているので、簡単に薬をやめるのは避けてください。症状によってステロイド軟こうや抗生剤入りの軟膏を使うなど対処法が異なるため、皮膚科に紹介してもらいましょう。現在、皮膚科のドクターらがイレッサや今後出てくるタルセバ(一般名エルロチニブ)の皮疹対策を執筆中です」
刺激の少ないローションなどで保湿してもよいでしょう。
●肺炎 イレッサでもっとも注意しなければいけないのは薬剤性の肺炎です。2週間から2カ月以内に起こりやすく、いったん発症すると重症化し、約半数は命に関わります。静岡がんセンターでは、最初の2週間は入院で経過観察し、その後週1回から2週に1回のレントゲン検査でチェックしています。 「喫煙者やもともと間質性肺炎などのある人は、イレッサによる肺炎になりやすいので、利益と不利益を考えて薬剤選択をすることが重要です」
早期発見もポイント。発熱や呼吸困難感があったらすぐに医師に連絡を。薬剤性肺炎に抗生物質は効果がないので、ステロイドで対処します。
「今後、日本での承認が予想されるタルセバや、肺がんに対する治験が進んでいるアバスチン(一般名ベバシズマブ)などの新しい分子標的薬は、従来の副作用は起こらない代わりに、皮疹や喀血、甲状腺障害、蛋白尿など、想定外の副作用が出てくる可能性もあり、薬剤に応じた副作用対策が求められるようになるでしょう」
治療をやめたいとき
肺がんの標準的な化学療法では、4~6コースを目標にしています。1コース目で腫瘍が増大したときや副作用が強い場合は、抗がん剤を切り替えることもあり、実際は3コース程度が平均的。「途中でやめたくなっても、肺がんの場合は抗がん剤治療を長く続けるわけではないので、効果があるときはがんばって続けたほうがよいと思います。腫瘍が縮小していなくても、増大していなければ、がんの進行を止めていると考えられます。担当医とよく相談しましょう」
*抗がん剤の副作用対策 PART-1、抗がん剤の副作用対策 PART-2もご参照ください。
同じカテゴリーの最新記事
- 免疫チェックポイント阻害薬で治療中、命に関わることもある副作用の心筋炎に注意を!
- 心不全などの心血管の副作用に気をつけよう! 乳がんによく使われる抗がん薬
- 手術や術後化学療法を受ける前に知っておきたいこと 大腸がん術後の副作用を軽減する
- 免疫チェックポイント阻害薬は、発現しやすい副作用を知っておくことが大事
- 免疫チェックポイント阻害薬の副作用対策 早期発見・早期対応のために必要なチーム医療
- 外来がん化学療法副作用対策 薬剤師外来の活用で安心のできる化学療法を
- 本邦初となる『がん薬物療法時の腎障害診療ガイドライン2016』の内容をひも解く
- 制吐療法の新しい展開 薬剤師主導の臨床試験で第2世代制吐薬の優位性を証明
- 進行肝がんに対するネクサバールのマネジメント


