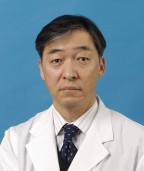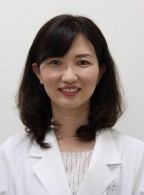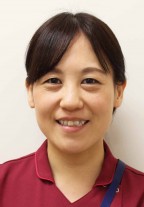2018年9月
「子宮体がんに関しては、ダヴィンチ手術は出血が少なく開腹手術と比較しても予後も差がなくて患者さんにとってメリットが大きい」と話す佐々木寛さん 手術支援ロボット、通称ダヴィンチ手術は日本では2012年4月前立腺がんに、2016年4月腎臓がんに保険適用されていた。今年2018年4月からその対象が大幅に拡大され、肺がん、食道がんなど12件に対して新規保険適用された。婦人科がんでは子宮体がんに対して適用。...


2018年8月
「肝細胞がんの治療がやっと次の時代に突入したかなという感じです」と語る池田公史さん 今年(2018年)3月、マルチキナーゼ阻害薬レンビマが、「切除不能な肝細胞がん」に日本で承認された。これは、切除不能な肝細胞がんに対する世界で最初の承認であり、肝細胞がん全身化学療法の1次治療薬としては実に約9年ぶりの新薬になるという。肝細胞がんの治療において、この新薬の位置づけはどのようなものだろうか。また、今後...

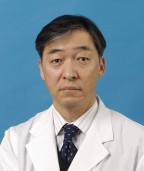
2018年8月
「アバスチンは、シグナル分子VEGFを捕獲することで、血管新生阻害だけでなく、免疫機能アップに関与していると考えられます」と語る高橋俊二さん 現在、化学療法との併用で使われることがほとんどのアバスチンは、分子標的薬の中では少々、特殊な存在かもしれない。がん細胞に直接作用するのではなく、がん細胞を巡る環境に働きかけるアバスチンのメカニズム(作用機序)と今後の可能性に焦点を当ててみた。 アバスチンとは...

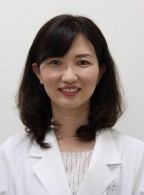
2018年7月
「将来的には子宮頸がんなど他のがんにも応用が期待できるかもしれません」と語る扇田真美さん 治療の選択肢が豊富で、適切に治療を行えば予後も良好な前立腺がん。その放射線治療において、直腸の副作の軽減に大きく貢献することが期待できるハイドロゲルスペーサー(SpaceOARシステム)が新たに保険収載となった。ハイドロゲルスペーサーをアメリカから導入し、自ら臨床試験に取り組みながら、今後の普及に期待をかける...


2018年7月
「子宮頸がんは、Ⅱb期までなら、手術と放射線治療は同等の効果です。Ⅲa~Ⅳa期は放射線治療でないと治せません」と語る村上直也さん 小線源治療が、なぜ子宮頸がんで効果的なのか。前立腺がんで多く活用されるのか。それには確たる理由があった。体の内側からピンポイントで放射線を照射する小線源治療について考えてみた。 放射線治療の歴史は小線源治療から始まった 放射線治療をひと言でいうと、直接的あるいは間接的に...


2018年7月
「最新式ガンマナイフ導入で、より患者さんに負担が少ない治療ができます」と語る赤羽敦也さん がんの遠隔転移によって起こる転移性脳腫瘍。腫瘍によって手足の麻痺や、痙攣など様々な神経症状が出る。そうした中で治療件数を伸ばしているのがピンポイントの放射線治療装置ガンマナイフだ。通常は1回の照射で退院できる。開頭手術に比べて身体的な負担が軽く、高齢者や体力を消耗した患者にも治療可能などのメリットがある。その...


2018年6月
「今回のガイドラインは医者と患者さんが話し合う共有意思決定のツールとして使って欲しい」と話す岩田広治さん これまでは2年ごとに改訂されてきた「乳癌診療ガイドライン」だが、今回は3年を要して改訂された。今回の改訂は、これまでのガイドラインと大きく変わったという。どこがどのように変わったのか。ガイドライン作成委員長の愛知県がんセンター中央病院乳腺科部長の岩田広治さんに伺った。 世界のガイドライン作成の...

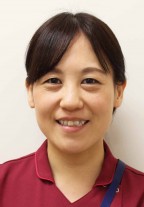
2018年6月
「臭いに困っている患者さんに対してケアの方法に悩むことがあります」と語る名取由貴さん 乳がんは進行・転移すると皮膚表面に露出し、潰瘍になることがある。がん性皮膚潰瘍だ。強い痛みが起こり、出血や滲出液に細菌が感染すると臭いを放つようになり、潰瘍が広がると滲出液も増え、1日に何度もガーゼやパッドを交換しなければならない。「臭いで周囲も自分もつらい……」という精神的苦痛も含めて、患者のQOLを著しく損な...


2018年6月
「我々は100を目指して治療しますが、患者さんにはそれが幸せなのかは別です。我々の価値感がベストとは思っていません。もう十分だからと、強い治療を望まないという人もいます。家族会議の中で個人の有事の際の身の振り方を決めておくことが大事です。意思表示がはっきりしていると治療方針も決めやすくなります」と語る西村誠一郎さん 超高齢社会となった日本では、当然のように高齢になってからがんに罹患する患者数も増え...


2018年6月
「背骨や腰など体のどこかに痛みが出たときは、まず乳腺外科を受診しましょう」と語る中村さん 術後10年以上経っても、再発の不安から逃れられない乳がん。しかし、ホルモン療法のメカニズムを知り、その理由と傾向がわかれば、何に注意して日々を過ごしたらよいかが見えてくる。過剰な心配は必要ない。万が一、再発したとしても、新薬も年々増え、治療法の選択肢も広がっている。大切なのは、知ること。そして、不安を捨てて楽...