抗がん剤の副作用対策 PART2 その軽減法と乗り切り方
骨髄抑制で、白血球や血小板が減るとどうなる?
感染や出血を起こしやすくなる。感染や傷の予防を第1に
多くの抗がん剤で程度の差はあれ、骨髄抑制が起こるといわれています。
「骨髄は、白血球、赤血球、血小板などの血液の成分を休むことなくつくっています。細胞分裂が盛んな骨髄細胞は、抗がん剤のダメージを受けやすいため、これらの血液成分が減少し、細菌やウイルス感染、出血、貧血などの症状が起こりやすくなります」
白血球は、抗がん剤投与後7~10日目から減り始め、4~5日間下がった後、自然に増え始めるのが普通です。治療の2、3回目になると、骨髄が早くダメージを受けて4、5日目で減少し始めたり、減少期間が長く続いたりする人もいます。
「白血球は、通常1マイクロリットルあたり4000から9000程度ですが、1000以下になると抵抗力が弱まり、風邪などの感染症にかかりやすくなります。
白血球のなかでも細菌を防御している好中球が500以下になった場合は、とくに注意が必要です。また、血小板が3万以下(通常は15万/マイクロリットル)になると血液凝固作用が弱くなり出血しやすくなります」
対策1 白血球減少時は感染予防
感染対策は予防が第1。食事の前やトイレの後、外から帰ってきたときには、手洗いとうがいを習慣づけて、細菌やウイルスを持ち込まないようにしましょう。毎日入浴をして、陰部も清潔に保ちます。抗がん剤投与日でも、シャワーや一番風呂なら大丈夫。毎食後と寝る前には歯磨きを。軟らかい歯ブラシやスポンジブラシを使うと口の中が傷つきません。虫歯がある方は、抗がん剤投与前に治療しておきましょう。
対策2 ピーク時には外出を控えて
白血球が1000以下、好中球が500以下になった場合は、人ごみを避け、生ものには火を通して食べましょう。 発熱が見られたら感染が疑われるので、受診してください。
「抗がん剤治療中でも、骨髄抑制がない時期には、マスクをしたり、生ものを避けたりする必要はありません」
対策3 好中球低下にはG-CSFで対処
血液検査の結果や、発熱、口内炎などの症状によっては、白血球を増やすG-CSF製剤を数日間皮下注射することがあります。好中球数が500以下の場合に保険が適用されます。
対策4 ひげそりは電気かみそりで
「白血球と血小板の減少が重なっているときにケガをすると、傷口から細菌が入りやすく、治りにくいもの。ひげやむだ毛の処理には、電気かみ���りを使い、調理中は包丁による傷にも注意しましょう。血小板が3万以下になった場合は、輸血が考慮されます」
中島さんより一言
その他の副作用対策
実際の治療メニューでは、どんな副作用がいつ、どのような順序で現れるのか、例を挙げてみました。
●口内炎
治療開始から2、3日ごろから口の中や、のどがひりひりし、1週間目くらいの白血球の減少時にピークとなりますが、10日目過ぎには徐々に改善してきます。痛みがあって食べられないときは、医師に鎮痛剤か、局所麻酔剤入りのうがい薬を処方してもらうと楽。感染予防のために、虫歯は治療しておき、食後の歯磨きと塩水でのうがいを励行。炎症にしみるときは、塩水をつけたスポンジブラシで磨き、口の中を常に清潔にしておきましょう。口の中が乾燥して唾液が出ないときは、保湿剤(オーラルバランス)や人工唾液(サリベート)を使うことをお勧めします。粘膜保護・修復作用のあるハチアズレを溶かした水でうがいをしたり、粘膜再生を促すエレース液を丸く凍らせた「エレースアイスボール」をなめて、症状を和らげる方法などもあります。
●脱毛
治療を始めて10日~14日前後から抜け始め、治療終了後3カ月くらいで、スポーツ刈り程度にはえそろってきます。あらかじめ髪を短めにカットしておくほうが、抜けたときのショックが少なく、ヘアケアも楽なようです。長い髪に抜けた毛がからまって困る、という患者さんもいます。治療期間と生活スタイルを考慮して、かつらやバンダナなどを用意するといいでしょう。市販の安価なかつらや、つけ毛つきの帽子などを利用する患者さんも増えています。インターネットで検索できる方は探してみてください。
●倦怠感
治療開始後、3、4日目ごろからだるくなり始め、徐々に回復してくることが多いものです。だるいときでも、歯磨きや着替えだけはするなどの目標を決め、それ以外は休み、ONとOFFを切り替えると、精神的に落ち込まずにいられるようです。
※それぞれの副作用対策については以下のコンテンツをご参照ください。
「下痢」 抗がん剤の副作用「下痢」のセルフケア
「口内炎」 お口の副作用トラブルを改善するオーラルケア
「味覚障害」味覚障害はなぜ起こる?
治りにくいしびれへの対処法は?
ビタミンB6・B12、タキサン系由来ならCOX2阻害剤が有効
手足の指先や足の裏がピリピリ、ジンジンするような痛みやしびれ、皮膚が1枚張り付いているような違和感、ほてり、知覚が低下し、力が入りにくくなるなどの症状は、抗がん剤が末梢の神経細胞を障害するために起こるといわれています。
「タキソールやオンコビンなどのタキサン系抗がん剤や、新しい抗がん剤のエルプラット(一般名オキサリプラチン)などで起こりやすく、個人差も大きいものです。初回投与後から起こることもあれば、数回の投与を経て起こることもあり、1度症状が出ると治りにくい傾向があります」
対策1 クルミなどで、手指を刺激
手を握ったり開いたり、クルミを握るなどの手指の運動や、手足の筋肉の曲げ伸ばしを積極的に行って、神経を刺激しましょう。また、温湿布で温めると症状が改善することがあります。
対策2 ビタミンB6やB12を補給
ビタミンB6やビタミンB12(メチコバール)は、神経の軸索に作用して、神経障害の回復を助ける作用があります。
対策3 COX2阻害剤が有効
「タキソールによるしびれの改善には、リウマチなどの関節痛や筋肉痛に使われるCOX2阻害剤(商品名モービック)が効果的、と当センターの呼吸器内科の臨床で確認され、実際に使われています。筋肉痛や関節痛の治療薬として保険が適用されるので、主治医に相談してみてください」
対策4 エルプラットの場合
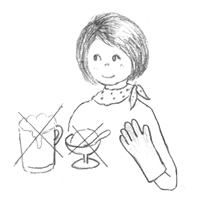
エルプラットを含むFOLFOXなどの治療では、手、足、のどの周りのしびれや麻痺、痛み、のどがしめつけられるような感覚が、投与直後または数時間後に起こることがあります。
「カルシウムやマグネシウム製剤を投与すると、これらの神経症状を45パーセントから20パーセントに減らせると報告され、当院ではエルプラットの投与前後に点滴で予防的に入れています。症状は2、3日で改善することが多いのですが、治療期間が長期にわたる場合は数カ月続くこともあり、しびれて歩きにくい、ボタンがはずしにくい、細かい作業がしにくいなどと訴える方もあります。このような場合でも、一時休薬すると、ほとんどの方は症状が回復するといわれています」
エルプラットによる神経症状は、冷気や冷たいものに触れることで誘発され、悪化することがあります。投与後3日間はアイスクリーム、冷やしたビールなどを口にしたり、素手で触れたりしないように注意してください。スカーフや靴下で首や手足の保温に努め、水仕事のときや、金属製のドアノブやはさみに触れるときは、裏地つきのゴム手袋などを着用するとよいでしょう。
| 薬品名 | 使用目的 | スケジュール |
|---|---|---|
| カイトリル1A デカドロン1V 生理食塩液100ml | 吐き気止め | 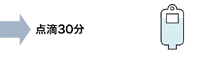 |
| カルチコール12ml コンクライトMg8ml 5%ブドウ糖液100ml | 神経障害軽減 | 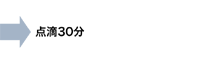 |
| アイソボリン200mg/m2 5%ブドウ糖250ml | 作用増強剤 | |
| エルプラット85mg/m2 5%ブドウ糖液250ml | 化学療法剤 | |
| カルチコール12ml コンクライトMg8ml 5%ブドウ糖液100ml | 神経障害軽減 |  |
| 5-FU 400mg/m2 5%ブドウ糖液50ml | 化学療法剤 | |
| 5-FU 2400mg/m2 生理食塩液を加え 全量225mlとする | 化学療法剤 | 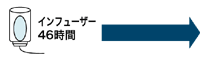 |
インフューザーは開始約46時間後に薬液の注入が終了。終了後ポート(抗がん剤を持続的に注入する装置)にヘパリン3mlを注入して抜針
対策5 やけどや転倒に注意
神経症状があるときは、感覚が鈍り、力が入らなかったりするので、熱い湯のみや刃物を持つときは、やけどや切り傷に注意します。足に合わない靴、すべりやすい履物は避け、浴室や階段では、転倒に気をつけましょう。
中島さんより一言
新しい抗がん剤の副作用は
最近話題の新しい抗がん剤は、副作用がまだよくわかっていないものが多いものです。
肺がんに使われるイレッサは皮疹、下痢、肺臓炎、血管新生阻害剤のアバスチンは高血圧、出血、下血、TS-1は骨髄抑制が起こりやすいといわれています。
同じカテゴリーの最新記事
- 免疫チェックポイント阻害薬で治療中、命に関わることもある副作用の心筋炎に注意を!
- 心不全などの心血管の副作用に気をつけよう! 乳がんによく使われる抗がん薬
- 手術や術後化学療法を受ける前に知っておきたいこと 大腸がん術後の副作用を軽減する
- 免疫チェックポイント阻害薬は、発現しやすい副作用を知っておくことが大事
- 免疫チェックポイント阻害薬の副作用対策 早期発見・早期対応のために必要なチーム医療
- 外来がん化学療法副作用対策 薬剤師外来の活用で安心のできる化学療法を
- 本邦初となる『がん薬物療法時の腎障害診療ガイドライン2016』の内容をひも解く
- 制吐療法の新しい展開 薬剤師主導の臨床試験で第2世代制吐薬の優位性を証明
- 進行肝がんに対するネクサバールのマネジメント


