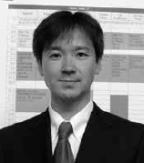
病型ごとに治療の開発が進む B細胞性リンパ腫
2016年2月
「B細胞性リンパ腫では、病型によって新たな治療法の開発が進んでいます」と語る丸山 大さん 悪性リンパ腫は種類が多く、治療選択もそれぞれで異なる。近年は新薬の開発が進むとともに、薬剤の組み合わせ、さらに投薬スケジュールの工夫など様々な取り組みが行われている。今回はB細胞性リンパ腫の中のびまん性大細胞型B細胞性リンパ腫(DLBCL)、濾胞性リンパ腫(FL)、マントル細胞リンパ腫(MCL)の最新治療につ...
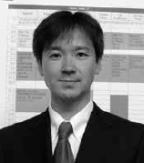
2016年2月
「B細胞性リンパ腫では、病型によって新たな治療法の開発が進んでいます」と語る丸山 大さん 悪性リンパ腫は種類が多く、治療選択もそれぞれで異なる。近年は新薬の開発が進むとともに、薬剤の組み合わせ、さらに投薬スケジュールの工夫など様々な取り組みが行われている。今回はB細胞性リンパ腫の中のびまん性大細胞型B細胞性リンパ腫(DLBCL)、濾胞性リンパ腫(FL)、マントル細胞リンパ腫(MCL)の最新治療につ...

2016年2月
がん患者の約7割でみられる「再発・転移」。この再発・転移が最終的な予後を決定すると言われる。「再発・転移」の基礎知識について、各種の資料をもとにまとめた。 再発・転移とは 縮小したがんが再び大きくなったり、別の場所に同じがんが出現「再発」とは、手術で取り切れていなかった小さながんが残存していて、再び現れたり、薬物療法や放射線治療で一旦縮小したがんが再び大きくなったり、別の場所に同じがんが出現するこ...

2016年2月
「例え大腸がんが肝臓に転移したとしても、決して諦める必要はありません」と語る吉留博之さん 大腸がんは肝臓に転移しやすい。ただ転移したとしても、決して諦める必要はない時代になってきた。手術で切除できれば、長期生存が可能になってきており、例え手術ができないと判断されても、手術のアプローチ法を変えたり、近年登場した新規薬剤を組み合わせることで、手術に持ち込めるケースも増えてきている。 治癒の可能性のある...

2016年2月
「乳がんの骨転移治療では、患者さんのQOLを保つことが重要です」と語る公平 誠さん 乳がんは骨に転移しやすい。痛みや骨折、脊髄の麻痺などを起こすことがあり、そうなると日常生活に悪影響を及ぼすことになってしまう。また、加齢によって骨が脆くなった上に骨転移が重なれば、より症状が悪化することにもなりかねず、十分な骨転移対策が必須となっている。 高率で発生する乳がんの骨転移 表1 固形がんにおける骨転移...

2016年2月
西脇市立西脇病院乳腺外科部長/昭和大学病院乳腺外科の三輪教子さん 治療法の進歩によって、進行・再発乳がん(以下mBC)の予後は大きく改善されてきました。例えば、再発後の5年生存率は、1970年代の約10%から2000年には50%近くとなっています 1)。しかし、現在でも早期乳がん(以下eBC)の20~30%が再発し、mBCの10年以上の長期生存はいまだに5%程度に留まっています。mBC患者は今後も...

2016年2月
「肺がんの脳転移症例に対する治療には大きな進歩が見られます」と語る岡本浩明さん 肺がんは脳転移しやすい。すべての脳転移のうち、半分以上を肺がんが占める。以前は予後がとても厳しかったが、近年は分子標的薬の登場や放射線療法の進化で治療できるようになった。肺がんの脳転移にどう対処するのか、最新の学会報告を交えてレポートする。 肺がんが脳に転移しやすい理由 図1 がん種別の脳転移発症頻度 杏林大学・永根...

2016年1月
人口の高齢化とともに、前立腺がんの罹患数が増加している。国立がん研究センターがん対策情報センターの2015年のがん統計予測では、部位別の罹患数で前立腺が女性乳房を抜いて第4位となっている(2014年のがん統計予測では第5位)。また男性においては、胃および肺を抜いて首位になると予測されている。早期の段階で治療を行えば治癒が期待できる前立腺がん、最低限知っておきたい基礎知識をまとめた。 前立腺がんの特...

2016年1月
「正しいリスク評価をしてから、適切な治療法を選択することが大切です」と語る古賀文隆さん PSA(前立腺特異抗原)検診が普及し、前立腺がんは早期発見が可能になった。限局性前立腺がん(いわゆる早期がん)は、どのような治療法があり、どう選択されるのだろう。体への負担を少なくする治療法はあるのだろうか。最先端で治療に当たる専門医に伺った。 PSA検査の普及で 早期発見が可能になった PSA(前立腺特異抗原...

2016年1月
「長い目で見ると、患者さんが受けやすいように照射回数を減らしていくという流れが次第にできるかもしれません」と語る萬さん 放射線療法において、1回の照射線量を増やして回数を減らす方法を寡分割照射法という。前立腺がんは前立腺の性質上、1回に高線量を当てるのが効果的とされている。一方で、高線量となると副作用も心配される。欧米では広まりつつあるが、日本ではまだ数施設で臨床試験として行われている段階で、今後...

2016年1月
「前立腺がんの治療で求められているのは、患者さんの個別化と治療の適正化です」と語る赤倉さん 初回ホルモン療法が効かなくなった状態を「去勢抵抗性前立腺がん」というが、従来はそうなった際の対策は限られていた。しかし、2014年に3つの新薬が承認され、治療風景は大きく変化した。一方で、延命効果はあるものの、薬価が非常に高いという医療経済上の課題も指摘され始めている。専門医に、去勢抵抗性前立腺がん治療にお...