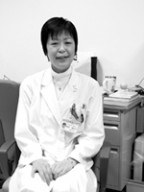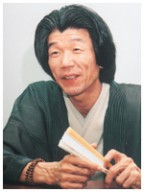2011年7月
あんどう まきこ 1971年生まれ。大学卒業後、社会人経験を経て、1999年から鶴巻温泉病院、静岡県立静岡がんセンターに勤務。2006年から現職。日本言語聴覚士協会、日本摂食・嚥下リハビリテーション学会会員 がんの手術によって、言葉や聴覚などのコミュニケーション手段を失ったり、飲み込みがうまくできなくなる人もいる。慶應義塾大学病院リハビリテーション科の安藤牧子さんは、言語聴覚士としてこうしたかけが...


2011年5月
やまざき ゆうすけ 1973年生まれ。2002年より国立がん研究センター中央病院(当時)で造血幹細胞移植コーディネーターとして働き始める。2005年に4名で移植コーディネーターのネットワークを結成し、2009年に「クリニカル移植コーディネーターの会」を立ち上げる。現在は移植コーディネーターの普及・確立にも努めている 造血幹細胞移植には、患者とドナーを中心に、医師、看護師、バンクなど多くの人が関わっ...


2011年4月
みやうち かよこ 大学卒業後、1981年に国立公衆衛生院(現・国立保健医療科学院)で難病患者の家庭訪問をしたのを機に、ソーシャルワークに興味を持つ。1982年に帝京大学医学部付属溝口病院に入職、現在に至る 病気、生活、家族のこと……。入院患者が抱えているあらゆる不安や悩みに、社会福祉の知識を活用して一緒に解決を探ってくれるのがソーシャルワーカーだ。帝京大学医学部付属溝口病院医療相談室課長の宮内佳代...

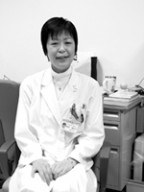
2011年3月
いなだ みわこ 2003年、龍岡介護老人保健施設入職。同年12月、臨床心理士の資格取得。その後富家病院を経て、2007年の緩和ケア病棟の立ち上げと同時に自治医科大学付属病院へ 今、緩和ケアにかかわっている臨床心理士は全国で350人ほど。自治医科大学付属病院緩和ケア科の臨床心理士・稲田美和子さんは「緩和ケアチームに、いわば医療には素人の私たちが入ることで、患者さんと医療スタッフ、またケアチームのなか...


2011年2月
あべ かずなり 1984年、作業療法士国家資格取得。1995年より千葉県がんセンター整形外科勤務(リハビリテーション担当)となる。その後、イギリス短期留学などを経て、2009年より現職 身体的なつらさはもちろん、精神的にもさまざまな葛藤にさらされる終末期。千葉県立保健医療大学健康科学部リハビリテーション学科准教授で作業療法士の安部能成さんは、緩和ケアの時期にこそ必要なリハビリがあり、その果たす役割...


2011年1月
神奈川県立がんセンター看護局長の渡邉眞理さん がん看護専門看護師と一口にいっても、今はそれぞれに専門分野を持つようになってきた。神奈川県立がんセンター看護局長の渡邉眞理さんは、この春まで医療相談室の室長として活動してきた医療連携のスペシャリスト。がん患者は何に悩み、どういう支援を受けられるのだろうか。行き場を失う患者「がん」という診断が伝えられると、早期がんか進行がんかに関わらず、患者はさまざまな...


2008年10月
乳がんのセルフサポートグループ、VOL-Netと製薬会社のノバルティスファーマ株式会社との共催によるキャンサー・サバイバー・フォーラム、「子供に親のがんをどう伝え、どう支えるか」が7月19日に開催された。 がん患者が増える中で、子供に親のがんを伝えるべきなのか、伝えるとすれば誰が何をどう伝え、どう支えればいいのか。日本では、ようやく患者への情報提供が行き渡ったところで、子供への情報提供まではまだ手...


2008年9月
NPO法人 血液情報広場つばさ代表の 橋本明子さん 97年から5000人以上の電話相談を受けてきた、血液がん患者団体「NPO法人血液情報広場つばさ」代表の橋本明子さん。 今年6月には、血液がんと乳がんに相談領域を広げて、NPO法人「日本臨床研究支援ユニット」が事務局機能を担う 「がん電話情報センター」にて、電話相談にあたっている。日々受けている電話相談から感じた、血液がん患者さんの苦悩や言いた...


2008年8月
アメリカはがん治療の分野で最先端を走っている。日本で使えない抗がん剤や外科手術の実績の数や放射線治療にも秀でている。 さらに、ドクターを中心にナースや麻酔医などのチーム医療も日本よりも進んでいる。 MDアンダーソンを始めアメリカで先端がん治療を受けることを望むなら、患者はどのようにすればいいのだろうか。 そのサポートをする2つの法人を取材し、そのシステムを聞いた― 海外からの患者受け入れ体制も整...

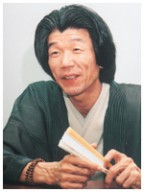
2008年3月
聖路加看護大学教授の 小松浩子さん 乳がん女性の心のケアの必要性が叫ばれるなか、聖路加看護大学では、乳がん女性を対象としたサポートグループを定期的に開催。 患者さんの体験や知恵を分かち合う話し合いに医療者が伴走し、患者さんにもサポートプログラムの運営にも参加してもらいながら、より患者さんのニーズに沿った取り組みを行い、成果を挙げています。そのサポートプログラムを見てみましょう。 サポートプ...