
メタボリック関係因子も関わる注目のタイプの肝がん
2014年12月
「生活習慣病の影響を最も受ける臓器は肝臓だと思います」と話す建石良介さんつい最近まで、原発性肝がんの9割はB型やC型の肝炎ウイルスの持続感染によるもので占められていたが、その分布構造は過去のものとなり、これから急激に増加していくのが「非B非C型」だ。生活習慣に原因があるもので、様々な危険因子が絡まって発症する。どのように対処すればよいのか、予後はどうなのか。 ウイルス感染による肝がんは今後減少 図...
肝臓がん

2014年12月
「生活習慣病の影響を最も受ける臓器は肝臓だと思います」と話す建石良介さんつい最近まで、原発性肝がんの9割はB型やC型の肝炎ウイルスの持続感染によるもので占められていたが、その分布構造は過去のものとなり、これから急激に増加していくのが「非B非C型」だ。生活習慣に原因があるもので、様々な危険因子が絡まって発症する。どのように対処すればよいのか、予後はどうなのか。 ウイルス感染による肝がんは今後減少 図...

2014年12月
「intermediate stageは症例の対象が広すぎるのが問題です」と語る泉 並木さん肝がんの病期分類で国際的に影響力が強い*BCLC(バルセロナ臨床肝がん)病期分類。ところがその中でintermediate stage(インターメディエイト・ステージ:中間期)と呼ばれる、いわゆるステージBに属するものは対象となる症例範囲が広く、様々な治療法が行われており、当然、それによって生存率も異なって...

2014年12月
「効果のある薬をしっかり使うことが大切です」と話す国立がん研究センター東病院の池田公史さん進行した肝がんでは、まずは肝動脈化学塞栓術(TACE)が治療の基本となる。しかしやがてそれも効かなくなる。そのとき登場するのが化学療法だ。延命効果が確認されている薬がある中、いかに肝機能を維持し、適切なタイミングで効果のある薬剤をしっかり使うかが重要だという。 手術やラジオ波焼灼療法ができない場合の治療法 肝...

2013年10月
「4年ぶりとなる改訂では治療法に大きな変更が加えられます」と話すガイドライン改訂委員長の國土典宏さん 第2版の『肝癌診療ガイドライン』が出版されて4年。その作成後にも新たなエビデンス(科学的根拠)が数多く登場。それらの成果を反映した第3版が近々刊行される。その内容は、肝がん治療にどんな変化をもたらすのだろうか――。肝がん診療の指針・案内役となるガイドライン■図1 ガイドラインの推奨度とは?グレード...
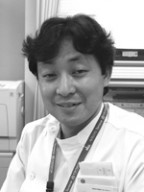
2013年10月
「TACEからネクサバールへ切り替えのタイミングが重要」と話す池田公史さん肝がんの治療は着実に進歩している。その証しの1つとなる5年生存率を見ると、1978~1985年には9.5%だったものが、1996~2005年には39.3%まで上昇している(日本肝がん研究会データ)。この背景には、検査法と治療法のめざましい進展がある。ここでは、進行肝がんに焦点を当て、最近の動向やトピックスを紹介する。肝臓の状...
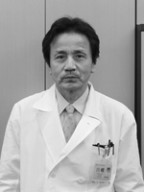
2013年5月
肝切除術と肝移植手術を数多く手がける川崎誠治さん 手術でがんを切除できても、再発率が高いのが肝がん。ただし、再発しても再び手術できるほか、ラジオ波焼灼療法や肝動脈塞栓術、肝動注化学療法、さらには肝移植や分子標的薬による治療などもある。患者さんの状態に合ったより適切な治療選択が可能となっている。5年後の再発率は8割■図1 肝がんの特徴肝がん(肝細胞がん)は再発の割合が高く、切除手術でがんを取り切れて...

2013年1月
肝がんの主因はC型肝炎とB型肝炎です。しかし、優れた薬剤の導入で、これらウイルス性肝炎の治療成績は飛躍的に向上している。また、難敵だった進行肝がんの治療も、分子標的薬の登場によって大きく変わろうとしている。先ごろ医療関係者を対象に千葉で行われた「東葛北部肝炎・肝がん診療連携講演会」では、こうした肝炎、肝がんの最新事情が紹介された。 肝がんの主因はC型、B型肝炎 地域の医療機関が連携し、肝がんの...

2012年10月
「チームネクサバールが診療科の壁を越えるモデルなれば」と話す 淺岡さん 分子標的薬ネクサバールは治療開始比較的早期に皮膚の副作用が出やすく、それが重症化すると治療が継続できなくなることがあります。 そこで、東京大学医学部付属病院では、医師、薬剤師、看護師が連携し、チーム医療で副作用のマネジメントに取り組み、大きな成果を上げています。 肝がん、主体は手術などの局所療法肝がんで亡くなる人は、年...

2012年10月
「再発肝がんの治療は集学的治療が大切」と語る野見武男さん肝がんの再発率は高い。とはいえ、手術で再切除が可能なら、根治を目指せるし、切除できない場合でも、肝動脈塞栓術、ラジオ波焼灼療法など、さまざまな治療がある。がんの状態や肝機能に応じて、適切な治療を選んでいくことが大切だ。再発と闘い続けるのが肝がん治療[図1 初回再発部位]肝細胞がん(以下、肝がん)は初めての治療で肝切除をした後、2年のうちに4~...

2012年1月
肝がんの治療法は多彩で、 しかもめざましい進歩を 遂げていると話す 高山忠利さん 最近の肝がんの治療法は、以前に比べ格段に向上しています。その1つがネクサバールという分子標的治療薬の成果で、生存期間や病気が進行するまでの期間を延長する効果につながっています。 肝がんの主因は肝炎ウイルス毎年、肝がんと診断される人は全国で約3万5千人。その95パーセントが「肝細胞がん」で、一般的に肝がんと呼...