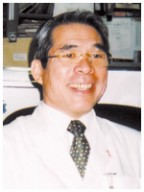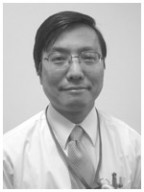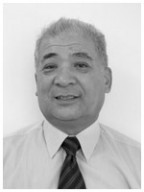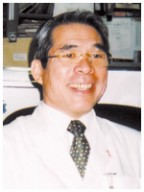
2009年8月
大阪大学大学院 生体機能補完医学講座 特任研究員の 福田文彦さん 抗がん剤の副作用として起こる手足のしびれや痛みといった末梢神経障害。 生活が不自由になるばかりか、抗がん剤の減量や投薬の中止といった事態にもなりかねない。 今、この末梢神経障害にハリ治療が効くというエビデンス(科学的根拠)が出始めているという――。 伝統的な治療法・鍼灸の特徴 ハリや灸は昔からある身近な補完代替医療の1つ。 人...


2009年8月
音楽療法は第2次世界大戦後、心に傷を負った兵士に対して行われたのが始まりといわれている。 米国ではすでにがん患者の心のケアにも取り入れられている。日本でもようやく導入されつつある。日常生活に溢れている音楽。 これががん患者にとって、どのような効果をもたらすのだろうか。心の傷を癒やし、ありのままの自分を受け入れられる力となる監修:新倉晶子 救世軍清瀬病院ホスピス緩和ケア病棟 音楽療法士私の生きている...


2009年8月
関西医科大学名誉教授の 上山泰男さん 健康食品は本当にがんに効果があるのだろうか。どのような効果があるのだろうか。 どこまで効くのだろうか。科学的に検証してみた。 健康食品の科学的な検証とは 補完代替医療には漢方、ハリ、アロマテラピー、気功……とあるのに、わが国では、補完代替医療といえば健康食品と思っている人がほとんどであることは、すでに見てきた通りである。 では、健康食品は、本当にがんに効...

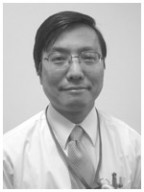
2009年8月
癌研有明病院 消化器内科部長の 星野惠津夫さん がんの治療において漢方が実力を発揮する場面はあるのだろうか。癌研有明病院で「漢方サポート外来」を担当する消化器内科部長の星野惠津夫さんは、長年それを検討してきたが、漢方にはがん患者さんの「元気」を回復したり、症状を和らげたり、西洋医学による治療の副作用を減らす効果が期待できることが、次第に明らかになってきた。 リンパ節、肺転移の患者が元気に が...

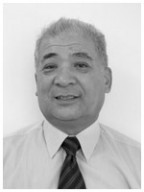
2009年7月
もりやま のりゆき 1947年生まれ。1973年、千葉大学医学部卒業。米国メイヨークリニック客員医師等を経て、89年、国立がん研究センター放射線診断部医長、98年、同中央病院放射線診断部部長で、現在に至る。ヘリカルスキャンX線CT装置の開発で通商産業大臣賞受賞、高松宮妃癌研究基金学術賞受賞。専門は腹部画像診断 患者プロフィール 65歳の男性Bさん。咳がなかなか止まらないので、近くの病院にて診察を...

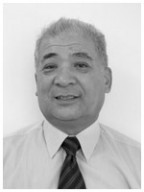
2009年6月
もりやま のりゆき 1947年生まれ。1973年、千葉大学医学部卒業。米国メイヨークリニック客員医師等を経て、89年、国立がん研究センター放射線診断部医長、98年、同中央病院放射線診断部部長で、現在に至る。ヘリカルスキャンX線CT装置の開発で通商産業大臣賞受賞、高松宮妃癌研究基金学術賞受賞。専門は腹部画像診断 患者プロフィール カゼをこじらせたわけでもないのに咳がとれない、と気がかりだった47歳...

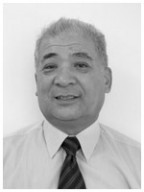
2009年5月
もりやま のりゆき 1947年生まれ。1973年、千葉大学医学部卒業。米国メイヨークリニック客員医師等を経て、89年、国立がん研究センター放射線診断部医長、98年、同中央病院放射線診断部部長で、現在に至る。ヘリカルスキャンX線CT装置の開発で通商産業大臣賞受賞、高松宮妃癌研究基金学術賞受賞。専門は腹部画像診断 患者プロフィール 66歳の女性Qさん。6カ月前に咳が止まらず、近所の病院に受診。カゼに...

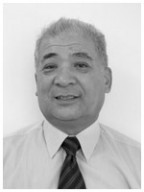
2009年4月
もりやま のりゆき 1947年生まれ。1973年、千葉大学医学部卒業。米国メイヨークリニック客員医師等を経て、89年、国立がん研究センター放射線診断部医長、98年、同中央病院放射線診断部部長で、現在に至る。ヘリカルスキャンX線CT装置の開発で通商産業大臣賞受賞、高松宮妃癌研究基金学術賞受賞。専門は腹部画像診断 患者プロフィール 62歳の男性Aさん。1年ほど前から断続的に上腹部の違和感と食欲不振を...

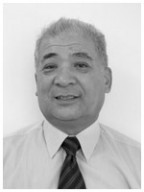
2009年3月
もりやま のりゆき 1947年生まれ。1973年、千葉大学医学部卒業。米国メイヨークリニック客員医師等を経て、89年、国立がん研究センター放射線診断部医長、98年、同中央病院放射線診断部部長で、現在に至る。ヘリカルスキャンX線CT装置の開発で通商産業大臣賞受賞、高松宮妃癌研究基金学術賞受賞。専門は腹部画像診断 患者プロフィール 35歳の女性Wさん。2カ月ほど前から上腹部に痛みを感じるようになり、...


2009年3月
横浜市立大学付属 総合医療センター 乳腺・甲状腺外科部長の 石川孝さん はやし整形外科院長の 林毅さん 乳がんのホルモン療法でアロマターゼ阻害剤の治療を受けていると、関節の痛みやこわばり、骨粗鬆症などの副作用が現れ、日常生活に支障が出ることがある。そうした場合、治療を中止せざるを得なくなる場合があるが、こうした副作用を他の診療科との協力によって見事にコントロールして乗り切っているケース...