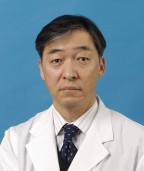2019年2月
「切除可能例については、術前化学療法がこれからの標準治療になっていくでしょう。さらにオプジーボの承認は一次治療が効きにくい肉腫型や二相型の患者さんにとっても朗報だと思います」と語る木島貴志さん 希少がんである悪性胸膜中皮腫は、保険適用で使用可能な抗がん薬が少なく、予後不良の疾患である。外科的切除の適応となる症例は少なく、また手術自体の意義についても一定した見解はなく賛否両論であるが、兵庫医科大学で...


2018年12月
「免疫チェックポイント阻害薬の副作用は、チーム医療で取り組み、早めの対処が重要です」と語る日本医科大学付属病院がん診療センター長の久保田馨さん 本庶佑・京都大学特別教授のノーベル医学賞受賞により、一般にも知られるようになった免疫チェックポイント阻害薬オプジーボ。この薬剤は、がん細胞を直接攻撃するこれまでの細胞障害性抗がん薬や分子標的薬とは異なる作用機序でがんと闘う。効果が長期間持続し、副作用の頻度...


2018年11月
「グアデシタビンやリゴセルチブが承認されて使えるようになったら骨髄異形成症候群の治療の幅がグッと広がると思います」と語る照井康仁さん 低リスクと高リスクでは、治療法も心構えも違う骨髄異形成症候群(MDS)。いずれも、完治には造血幹細胞移植しか方法はないが、年齢や状況的に移植を受けられないことも多い。今のところ、高リスクの決定打はビダーザだけだが、今後、RAS遺伝子にピンポイントで作用する分子標的薬...


2018年11月
「一部の患者さんは新しい分子標的薬の登場で骨髄移植を行わなくても治癒する可能性が出てきます」と語る矢野真吾さん かつては不治の病の印象が強かった血液のがん、白血病は、近年、化学療法の進歩により、根治を見込めるがんへと変わりつつある。その中の急性骨髄性白血病についても化学療法の選択肢が増えつつある。現在、有効性の高い1剤が保険承認され、7剤もの分子標的薬の臨床試験が日本で行われている。そんな急性骨髄...


2018年9月
「再発卵巣がん治療の難しさは今も変わりませんが、リムパーザを使うことで6年以上という長期間、再発せずにいける人が増えてくるはずです」と語る竹島さん 卵巣がんに、新たな分子標的薬リムパーザが承認された。がん細胞のDNA修復機構を壊し、がん細胞自体が死に至るよう導くという機序(メカニズム)を持つ。今年(2018年)4月に発売開始されて現時点で4カ月。リムパーザのメカニズムと可能性、そして、副作用の出方...


2018年9月
「いつもと違うと感じたときは、婦人科にできるだけ早く相談して、自分の体は自分で守るという気持ちが大切です」と話す石川光也さん 子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がん。妊娠・出産に関わる、女性にとって重要な臓器に発症するがんだ。近年、あらゆるがん治療で、その治療法が進化するなか、女性特有のがんであるこれらのがん治療の現状はどうなのか。そして今後の展望は? わが国の婦人科がんの臨床・研究をリードする、国立が...


2018年9月
「今回の試験の結論としては、術前化学療法が、全ての患者さんにおいて、手術先行治療に対する代替療法として、常時位置づけられるのは難しいということになりました」と語る恩田貴志さん 多くの固形がんを根治に導くには、手術が必要だ。昨今では、早期がんであれば、後遺症を考慮して、機能温存のための縮小手術も行われる。しかし、卵巣がんは、大部分が他臓器にも転移を有する進行がんで、周囲の臓器を含め、徹底的に切除する...

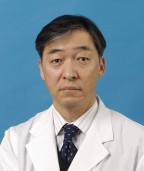
2018年8月
「アバスチンは、シグナル分子VEGFを捕獲することで、血管新生阻害だけでなく、免疫機能アップに関与していると考えられます」と語る高橋俊二さん 現在、化学療法との併用で使われることがほとんどのアバスチンは、分子標的薬の中では少々、特殊な存在かもしれない。がん細胞に直接作用するのではなく、がん細胞を巡る環境に働きかけるアバスチンのメカニズム(作用機序)と今後の可能性に焦点を当ててみた。 アバスチンとは...


2018年8月
「肝細胞がんの治療がやっと次の時代に突入したかなという感じです」と語る池田公史さん 今年(2018年)3月、マルチキナーゼ阻害薬レンビマが、「切除不能な肝細胞がん」に日本で承認された。これは、切除不能な肝細胞がんに対する世界で最初の承認であり、肝細胞がん全身化学療法の1次治療薬としては実に約9年ぶりの新薬になるという。肝細胞がんの治療において、この新薬の位置づけはどのようなものだろうか。また、今後...


2018年8月
「今後、さらに免疫の仕組みが解明されていくことで、免疫チェックポイント阻害薬をはじめとするがん免疫療法の開発はますます前進していくことでしょう」と語る北野滋久さん 分子標的薬は、分子生物学的知見に基づいてデザインされた抗体薬だ。免疫チェックポイント阻害薬も同様の知見に基づいてデザインされた同じ抗体薬であるが、作用機序(メカニズム)が異なるため両者を区別するケースが多い。免疫チェックポイント阻害薬は...