
制吐療法の新しい展開 薬剤師主導の臨床試験で第2世代制吐薬の優位性を証明
2016年12月
「制吐薬の個別化医療を進めていきたい」と語る鈴木賢一さん 抗がん薬治療による副作用の代表格と位置付けられてきたのが、悪心・嘔吐。日本癌治療学会が「制吐薬適正使用ガイドライン」を作成したのは2010年で、15年には第2版が出されるなど重要視されている分野だ。さらに、薬剤師の視点から独自に治療薬の効果を確かめる臨床試験を行う動きもある。 シスプラチン投与時の悪心・嘔吐を防ぐ 日本で「制吐薬適正使用ガイ...
抗がん薬治療

2016年12月
「制吐薬の個別化医療を進めていきたい」と語る鈴木賢一さん 抗がん薬治療による副作用の代表格と位置付けられてきたのが、悪心・嘔吐。日本癌治療学会が「制吐薬適正使用ガイドライン」を作成したのは2010年で、15年には第2版が出されるなど重要視されている分野だ。さらに、薬剤師の視点から独自に治療薬の効果を確かめる臨床試験を行う動きもある。 シスプラチン投与時の悪心・嘔吐を防ぐ 日本で「制吐薬適正使用ガイ...

2016年7月
「FOLFIRINOX療法は、将来的には標準治療の第一選択になる可能性があります」と期待を語る伊佐山浩通さん 胆汁を十二指腸まで運ぶ胆道に発生するがんは早期に発見することが難しい。罹患者に高齢者が多いこともあり、手術で切除することが難しく、化学療法が選択されるケースも多い。現在は3剤による組み合わせで対応されているが、新しくFOLFIRINOXという4剤併用療法の臨床試験(先進医療B)が計画されて...

2016年7月
「ネクサバールの副作用である手足症候群は予防が重要です」と語る池田公史さん 進行した肝がんでは、標準的な化学療法として血管新生阻害薬であるネクサバールが使用されている。しかし、ネクサバールには手足症候群、高血圧、肝機能障害などの副作用があり、これらが治療の休止や中止の一因になることがある。医療チームを立ち上げ、ネクサバールの副作用マネジメントに取り組んでいる専門医に話をうかがった。 世界で2番目に...

2016年6月
「薬物治療を進めていく上で、高齢者の機能評価ツールを活用できる可能性があります」と語る長島文夫さん 昨今、抗がん薬や分子標的薬の開発が進み、たとえがんが進行再発した場合でも、治療選択肢は増えてきた。そうした中、新たな問題も生じてきている。それが「いつまで治療を続けるか」という点だ。ここでは、実際にがん患者の多くを占める高齢者を対象に、機能評価の指標を用いて治療を行う専門医に、薬物治療を進めていく上...
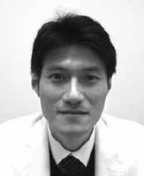
2016年5月
「術後補助化学療法は再発リスクの高い患者さんに対して行う意義があります」と話す鶴田雅士さん 大腸がんは手術でがんを取り切ることができれば、他のがん種よりも治癒率が高い。しかし、進行がんでは、CTやPETでも捉えられない微小ながんが残されている可能性が高く、これが再発のもとになる。そのリスクを下げるのが、手術後に抗がん薬を投与する術後補助化学療法だ。効果と副作用、ライフスタイルなどを踏まえ、患者にと...

2016年5月
「適切なストーマケアで化学療法を達成していただきたい」と話す工藤礼子さん 大腸がん治療では、術前、あるいは術後に抗がん薬や分子標的薬による化学療法を実施することが一般的な治療法として普及してきている。ただし、化学療法を行うと、皮膚障害、下痢、末梢神経障害など多様な副作用が現れることも少なくなく、ストーマ保有者には大きな問題となる。一方、抗がん薬治療を受けた患者の排泄物による曝露対策も、患者とその家...

2016年4月
やまだ みつぎ 千葉県がんセンター看護局通院化学療法室看護師長。2006年日本看護協会がん化学療法看護認定看護師認定。11年聖隷クリストファー大学大学院博士前期課程修了(看護学修士)。同年、がん看護専門看護師認定。13年より現職。日本がん看護学会、日本臨床腫瘍学会、日本看護研究学会所属 がん治療についてまわる「むくみ」。タキソテールやアリムタなどの抗がん薬で頻度の高い副作用ですが、いかに早くその徴...

2016年3月
「Ⅲ(III)期の治療法を決定する上で、専門の異なる複数の医師による検討は重要です」と語る中島崇裕さん 非小細胞肺がんのⅢ(III)期と言ってもその範囲は広く、治療の選択肢は多岐にわたる。放射線療法と化学療法を組み合わせた集学的治療がいいのか、そこに手術を加えたほうがいいのか、個々の患者の状況によって、判断が必要になってくるという。そしてその前提として、正確な診断・評価が重要になってくることは言う...

2016年3月
やまだ みつぎ 千葉県がんセンター看護局通院化学療法室看護師長。2006年日本看護協会がん化学療法看護認定看護師認定。11年聖隷クリストファー大学大学院博士前期課程修了(看護学修士)。同年、がん看護専門看護師認定。13年より現職。日本がん看護学会、日本臨床腫瘍学会、日本看護研究学会所属 1度、性機能にダメージが生じると、回復に時間がかかったり、場合によっては永久的に元に戻らないこともあります。だか...

2016年2月
「緊急受診時は、血栓症リスクの高い使用薬をまず伝えていただきたい」と話す岡元るみ子さん 血液がんの治療薬には、血栓症リスクを高める治療薬があり、また、高齢者に多い脳血管障害対策の抗凝固薬のワルファリンとの相互増強作用に配慮が必要なものもある。治療に際し、どのような対策が必要なのだろうか。そもそも、がんと診断され、治療を行うこと自体で血栓症のリスクが高くなるという、その基本事項から解説する。 がんの...