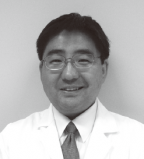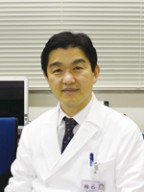2013年12月
「エビデンスを示すのは当然のこと」と話す岩瀬哲さん「AHCCの効果をさらに詳しく検証します」と話す半谷匠さん生命やQOL(生活の質)に影響を与える抗がん薬の副作用。乳がんの補助化学療法では、副作用を軽減させるために、代替療法の1つであるAHCCの効果が、科学的に検証され始めている。キノコ菌糸体AHCC副作用軽減に貢献かがん患者さんの多くは、治療に伴い、吐き気、嘔吐、口内炎、脱毛といったQOL(生活...


2013年12月
宇田川 晴司 虎の門病院消化器外科部長「根治・安全・低侵襲はもちろんのこと、術後の患者さんのQOLを考えた手術を行っています」と話す宇田川晴司さん食道がんの手術は、大がかりで体への負担も大きいことで知られる。これに対して、虎の門病院消化器外科部長の宇田川晴司さんは食道がん手術の9割に胸腔鏡と腹腔鏡を導入している。しかし「新しいことをするためではありません」という言葉どおり、手術で培った技術が随所に...


2013年12月
「がんと糖尿病は連携をとって治療に臨むことが大切です」と話す大橋健さんがん患者さんの中でも60歳以上の患者さんでは、3人に1人が糖尿病の可能性を秘めていると言われている。がんも糖尿病も、慢性疾患として日々の治療が重要となる。だからこそ、それぞれの治療の影響や兼ね合いについて、患者さんはもちろん、家族も知っておく必要がある。糖尿病サイト「糖尿病とがん」(大橋健さん監修)http://www.club...

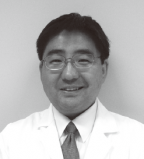
2013年12月
「がん治療にも影響する腎臓病をもっと知って下さい」と話す松浦友一さん健康な人でも歳をとるにつれ腎機能は低下するが、腎機能が悪いと、画像診断や一部の抗がん薬治療が行えないなどの不利益がある。また腎機能が正常な人に比べて、抗がん薬の副作用も強く出ることが知られている。そのような腎疾患・透析患者さんのがん治療とは――。腎疾患はがんの診断や治療を制限肝臓は病気があっても症状が出にくいことから「沈黙の臓器」...


2013年12月
「分子標的薬の治療はベネフィット・リスク・コストを考慮することが必要」と話す田村研治さん細胞の増殖や浸潤・転移にかかわるがん細胞特有の分子(タンパク質を基に構成されている酵素など)を標的とする分子標的薬。同薬の出現は、「個別化医療」を現実のものとし、2000年以降、がん薬物療法のキーファクターとなっている。しかし、いくつかの課題もあるという。現在開発されているのはほとんどが分子標的薬がんの薬物療法...


2013年12月
国立がん研究センター中央病院乳腺・腫瘍内科科長田村研治さん個別化治療の鍵となる分子標的薬。しかし、どんなに素晴らしい薬剤でも、それを使い続けるといずれ効果がなくなる。そのようなとき、どうしたらよいのだろうか。効いていた分子標的薬もいずれ効かなくなる離れた臓器に転移がある進行がんの状態になると、従来型の抗がん薬でも、分子標的薬でも、基本的に完治させることは困難になってしまう。そこで、このような場合の...


2013年12月
「患者さんにとって本当に役立つチーム医療を目指したい」と語る相羽惠介さん“チーム医療”が脚光を浴びる昨今、本当に患者さんの役に立つチーム医療を目指し、化学療法の副作用対策を進めている東京慈恵会医科大学腫瘍・血液内科。そこでの現状と、副作用ケアに欠かせない制吐薬の進化について、専門家に聞いた。チーム医療で幅広い診療対象に対応東京慈恵会医科大学の腫瘍・血液内科は、血液内科と腫瘍内科の2つの機能を併せ持...


2013年12月
がん研究会有明病院消化器内科化学療法担当部長の水沼信之さん進行・再発大腸がんの3次治療以降に用いることができ、さらにGIST(消化管間質腫瘍)の3次治療以降に対しても投薬が承認された分子標的薬*スチバーガ(一般名レゴラフェニブ)。先ごろ都内で開かれたバイエル薬品株式会社主催のセミナーで、大きな期待の寄せられているスチバーガをより安全に、継続的に服用するための取り組みについて、がん研究会有明病院「チ...


2013年11月
「患者さんの心の痛みを癒したい」と乳房再建を始めた佐武利彦さん。手術は慎重で美しく、向上を重ねている佐武利彦 さたけ としひこ1989年久留米大学医学部卒業。東京女子医科大学形成外科、鹿児島市立病院形成外科、川口市立医療センター外科等を経て、2008年から横浜市立大学附属市民総合医療センター形成外科准教授。2000年より穿通枝皮弁による乳房再建術を手掛ける。日本形成外科学会認定形成外科専門医、日本...

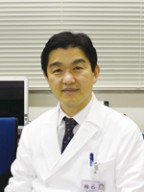
2013年10月
椎名秀一朗 しいな しゅういちろう1982年東京大学医学部卒業。同大学第二内科医員、助手などを経て、2004年同大学消化器内科講師。エタノール注入療法など、肝がんの低侵襲治療を実施してきたが、米国のベンチャー企業が開発したラジオ波治療に注目、1999年に日本に導入し、約9000例とその実績は世界一となっている。2012年より順天堂大学大学院医学研究科画像診断・治療学教授、医学部附属順天堂医院消化器...