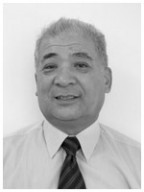
膵島腫瘍(膵内分泌腫瘍)CT検査 影の白っぽいのが、膵がんと見分けるポイント
2011年2月
もりやま のりゆき 1947年生まれ。1973年、千葉大学医学部卒業。米国メイヨークリニック客員医師等を経て、89年、国立がん研究センター放射線診断部医長、98年、同中央病院放射線診断部部長で、現在に至る。ヘリカルスキャンX線CT装置の開発で通商産業大臣賞受賞、高松宮妃癌研究基金学術賞受賞。専門は腹部画像診断 患者プロフィール 45歳の男性Sさん。人間ドックの腹部超音波検査で、膵臓に腫瘍と思われ...
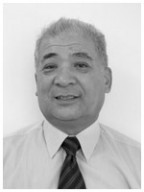
2011年2月
もりやま のりゆき 1947年生まれ。1973年、千葉大学医学部卒業。米国メイヨークリニック客員医師等を経て、89年、国立がん研究センター放射線診断部医長、98年、同中央病院放射線診断部部長で、現在に至る。ヘリカルスキャンX線CT装置の開発で通商産業大臣賞受賞、高松宮妃癌研究基金学術賞受賞。専門は腹部画像診断 患者プロフィール 45歳の男性Sさん。人間ドックの腹部超音波検査で、膵臓に腫瘍と思われ...
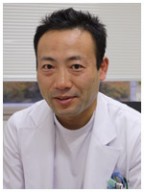
2011年2月
国際医療福祉大学 三田病院外科・ 消化器センター准教授の 首村智久さん 最近、肝臓がんの新たな術中検査法として注目されているのが、ICG蛍光検査法と呼ばれる方法だ。肝臓がんに蓄積して蛍光を発するICGの性質を利用して手術中に特殊カメラでがんをとらえて取り残しを防ぐのだ。 大腸がんの肝転移を切除し、完治を目指す 朝9時過ぎ、65歳の患者さんは車イスに乗って手術室に現れた。笑みを浮かべて挨拶する...

2011年2月
金沢大学大学院医学系研究科 臨床研究開発補完代替医療学講座 特任教授の鈴木信孝さん “がんに効く”といわれるサプリメントが巷に溢れる中、どれを選べばいいのか頭を抱える人も多いだろう。 その場合、選択基準として重視したいのが「安全性」と「ヒトに対する臨床研究」だ。 この2つをクリアするサプリメントは数少ないが、その1つとして、シイタケ菌糸体が今、脚光を浴びている。 体力や免...

2011年2月
早稲田大学先端科学・ 健康医療融合研究機構 客員准教授の 大野智さん 銀座東京クリニック院長の 福田一典さん 最近では、サプリメントについてもエビデンスが重視され、臨床試験が進められている。 しかし、がんを改善する“ 抗がん効果” が認められたものはいまだ皆無に等しい。 ただし、副作用の軽減やQOL(生活の質)の向上など、がん医療を補完す...

2011年2月
爽秋会 クリニカルサイエンス研究所代表の 瀬戸山修さん がんになってから食事に気をつけたいと思う人は多い。 しかし、具体的にどんな食事を、どのように食べたらいいのかとなると、なかなか難しい。 食事に関するさまざまな情報が飛び交う中、きちんとしたエビデンス(科学的根拠)のある食事は何か――これを機会に整理しよう。 がんと食事に関する基本的な考え方 がんの治療法というと、手術、化学療法、放...
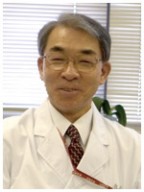
2011年2月
千葉県がんセンター センター長の 中川原章さん もし口からものが食べられなくなったら……。なんて味気ない、なんて楽しみのない人生だろうか。 これはがん患者さんにとっても同じだということが、今がん医療の現場で再認識されだしている。 食べられない患者さんにも、食べられるように食材や調理法に工夫を凝らす努力が行われ出したのだ。 「食べる」ことから始まるがんとの闘い 人は食べることで生命を、健...

2011年2月
静岡県立静岡がんセンター 栄養室長の 稲野利美さん 抗がん剤治療や放射線治療中の患者さんやご家族の多くが、さまざまな副作用のため食べられないことに悩んでいる。 そこで、静岡県立静岡がんセンター栄養室長の稲野利美さんに、副作用の症状別の、食べられないときの食事の工夫を伺った。 「がん患者の食事は特殊」と考えられているが…… 抗がん剤治療(化学療法)や放射線治療には、さまざまな「食べられな...

2011年2月
藤田保健衛生大学医学部 外科・緩和医療学講座教授の 東口髙志さん がんの進行によって現れる食欲低下や体重減少によるやせ衰えた状態、あるいは倦怠感、腹水、胸水といった症状は「悪液質」と呼ばれます。これまで有効な対処法はありませんでしたが、適切な栄養管理を行うことで症状を抑え、生存期間を延長する例もみられるようになってきました。 明確でない「悪液質」の定義 「悪液質の定義は、実はいまだ明確...
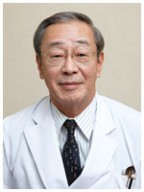
2011年1月
東京医科大学病院 泌尿器科主任教授の 橘政昭さん アメリカでは、泌尿器科の手術の多くが「ダヴィンチ」によるロボット手術で行われている。日本でも、東京医科大学病院で前立腺に続いて、ようやく膀胱がんのロボット手術が始まった。膀胱がんのロボット手術とは? なぜロボット手術が必要なのだろうか。 巨大なカニの足のよう 膀胱全摘術に適応が広がった手術支援ロボット「ダヴィンチ」 執刀医は、ベッドから...

2011年1月
東京大学医学部付属病院 泌尿器科・男性科准教授の 久米春喜さん 進行・再発腎がんの薬物治療は、分子標的薬の登場により大きく変わりつつある。しかし、つらい副作用に耐えられず、治療を断念してしまう患者さんも少なくない。副作用と上手に付き合いながら、治療を続けていくコツを伺った。 進行腎がんの治療を一変させた分子標的薬 超音波やCTなどの検査の普及によって、近年、腎がんが小さい段階で見つかるこ...